「犬小屋」「花の名前」「かわうそ」の三つの短編小説
それぞれ二十枚前後の短い作品によって、第八十三回の直木賞を貰った。
その一年のち、昭和56年8月航空機の事故で死の世界に入ってしまうとは・・・・・・
~本当に信じ難かった。まさかまさかが、現実に起きるなんて!~

『思い出トランプ』に入っている【だらだら坂】短編小説の十三編
どこにでもある様な身辺の材料から、みごとな技術で日常生活を感情や心の底まで描写する才能は、
日常の生活を温かく愛していたからだと思う。
中小企業の社長の庄治はマンションに女を、囲っている。
マンションといっても中古の4畳半と6畳である。
中小企業ではあるが社長の肩書を持ち運転手付きの車を持つようになった今でも、
タクシ-のメ-タ-が上がる手前で降りてしまう。
体も、男としては小柄でせかせかしているので「鼠」というあだ名がついているが、
自分でも笑いたい気分になる。
マンションに女を囲っている身分になったと思うと、弾むものがある。
男の花道と言う言葉もある。
花道はゆっくり歩いたほうがいい。
庄治は、タクシ-を降りると角の煙草屋でタバコ1つ買う。
これが庄治の優等な芝居の幕開けなのである。
(愛人)の元に通う緩やかな坂道は、昔は麻布の元お屋敷町で坂の両わきには昔ながらの
古びた家を労りながら住んでいたり、思い切って建て替えた家もあり庭付きのかなりいい家がある。
石壁には、つたが絡んでおり庭には百日紅、ハクモクレン、山吹雪、
久し振りに庄治は沈丁花の匂いをかいだ。
庄治にとってはこの坂は四季である。
(愛人)トミ子は会社の女子事務員の試験で知り合ったが、大きすぎ太っりすぎていて野暮ったく
不採用になったが、
何故か庄治を引き付けるものがあり、トミ子の住所、電話番号を、手が独りでに動いて今の関係になった。
庄治は50歳、トミ子は二十歳で色が白いだけがとり得である。
トミ子が服を脱ぐとさらにおおきなピカピカの白い体に鼠がよじ登っているようで、
庄治はまるで鏡餅のようだと思った。
言われなければ、何もしないが、言われたことだけはやる。
先回りして気を遣わせないので庄治は気が休まるのである。
トミ子も庄治の言うことはなんでも聞き、慎ましく生活をしていた。
そんな、ところも、庄治は気に入っていた。
ただ《隣近所とは付き合うな》と命じておいたのだが、
隣のスナックの雇われママとのガス湯沸かし器のつけ方など教わったりで口を聞くようになった。
トミ子は、そろばんも出来るので帳簿整理などを手伝っていた。
庄治は、だんだんと女の好みまで親父に似てきたものだと思う。
家系のせいか年と共に、体もしぼんでくるのでますます「鼠」に似てきた。
{鼠}だって血が騒ぎ肉が躍る時だってあるものだと思った。
庄治が、仕事を兼ねて海外出張を一日早く繰り上げてトミ子を喜ばせようとマンションを訪ねると、
隣の雇われママの勧めでトミ子は目の整形手術をして、村芝居で観たお岩様のように目をはらしていた。
怒る庄治にトミ子は一言も謝らなかった。
庄治は『あの、細い目が、お袋の手のあかぎれのような細い目が好きだったのに』
~私には、トミ子の気持ちが分かる。生まれ変わって出来るものなら整形手術をしてでも
全てを変えて
これからの、人生を華やかに輝いて生きていきたい。~
庄治は、トミ子が少しずつ変わり綺麗になっていくと感じ始めていた。
トミ子はだんだんと明るくなり、口数も多くなり自分に自身が付き表情も豊かになってきた。
その分だけ庄治は疲れやすくなってきた。

日々変わっていくトミ子に惜しい気持ちと、ホッとした気持ちが半々になってきた。
だらだら坂を下りるとき、つま先が無意識に先に降りていく。
下から上っていくときとは違い馴染んだ景色ではない。
眼の下には今まで見たこともない商店外,屋根、.看板、全てが、みかん色に輝いている。
夕焼けである。
丁度1年、この坂を今までは上る時は日に背を向け帰りは闇である。
夕焼けの街を見たこともなかった。
トミ子のマンションに寄らず庄治は坂の下まで行って、煙草屋でたばこを1つ買いそのまま家に帰ろうか。
坂の途中で庄治はポケットの中の小銭をさがした。
~庄治は、〈トミ子に惜しい気持ちと、ホッとした気持ち〉が半々になってきた。
この気持ちは、「潮時」を感じた気持ちだと思う。
庄治との関係も庄治の手からトミ子は離れていきだした。
庄治も夕焼けを見た時今まで何も感じなかったものが胸に迫ってくるようになった。
誰しも持つ哀愁のような心理、気持ちが離れていくときの感じる虚しさ、寂しさ、
向田邦子は人間の奥深い心に潜むものを巧みに言葉に
替えて表現できる才能豊かな小説家だと思う。~


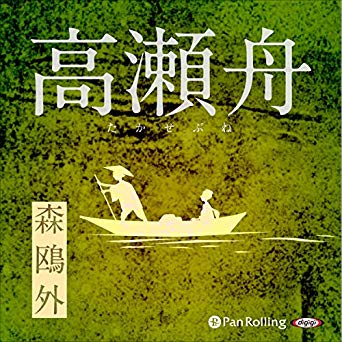
コメント