
~郷土を愛した宮沢賢治は、岩手に由来するイ-ハトヴという名の
理想郷を舞台にして詩や童話などに独自の作品世界を築いてきました。
しかし、中央の文壇からはあまり注目されることはありませんでした。
存命中に発表された作品は決して多くなく、出版された単行本も、
大正13年に自費出版した詩集『春と修羅』と、
創作童話集【注文の多い料理店】のみです。~

~子供のころ読んだときは、何か不気味というか怖かった記憶があります。
店の中にはいくつもの、扉があり変わった注文が書かれていました。
そのたびに、びくびく恐々しながら読んでいました。
でも、大好きな本です。~
~今、読み返しますと、私も若い二人の紳士と同じで(おかしい)とは思いながらも
自分の都合のいいように解釈してしまう自分がいます。
同じようなことをしていたかも?と思ったりしてしまいました。
大人になりますと、子供のころの感性とは大分違うものだと思いました。~
《あらすじ》
二人の若い日本人紳士が、すっかりイギリスの兵隊のかたちをして
ピカピカする鉄砲をかついで、それぞれ白熊のような犬を二匹つれて
だいぶ山奥の、かさかさしたところを歩きながら、
「鳥も獣も一匹も居やがらん。なんでも構わないから、早くタンタア-ンと、
やってみたいもんだなぁ。」と彼らは話します。

それはだいぶ山奥でした。
案内してきた専門の鉄砲打ちも、どこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。
それに、あんまり山が物凄いので白熊のような犬が、二匹一諸にめまいを起こして、
しばらく唸って、それから泡を吐いて死んでしまいました。
それを見た紳士たちは、
「じつに僕は二千四百円の損害だ」犬の瞼をかえしみて、言いました。
「僕は二千八百円の損害だ」と、
もうひとりの紳士が悔しそうに、頭をまげて言いました。
鳥も、獣も、見当たらないし
腹は空いてきたし戻ろうと思いましたが、困ったことに見当がつかなくなってしまいました。
風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はかさかさ、木はごとんごとんと鳴りました。
二人の紳士は
「歩きたくないよ。ああ困ったなぁ、何か食べたいなぁ。」
「食べたいもんだなぁ」
ざわざわ鳴るすすきの中でこんな話をしていました。

その時、後ろをみますと立派な一軒の西洋造りの家がありました。
そして玄関には
〔レストラン西洋料理店ワイルドキャットハウス山猫軒〕
という札がでていました。
二人の紳士は、お腹がすいているので入ってみることにしました。
二人は戸を押してそこはすぐ廊下になっていました。
その硝子戸の裏側には、金文字で
「ことに太ったお方や若いお方は、大歓迎いたします」
二人の紳士は大歓迎というので、もう大喜びです。
ずんずん廊下を進んで行きますと、今度は水色のペンキ塗りの扉がありました。
二人の紳士はその扉をけようとしますと、上に黄色な字で
「当件は注文の多い料理店ですからそこはご承知ください」
二人の紳士は
「なかなか流行ってるんだ、こんな山の中で。」
と言いながら、その扉をあけました。
するとその裏側に、
「注文はずいぶん多いでしょうが一々こらえて下さい。」
ところが、どうもうるさいことは、また扉が一つありました。
「お客さまがた、ここで髪をきちんとして、それから、はきものの泥を落してください。」
そこで二人の紳士は、きれいに髪をけずって、靴の泥を落としました。
早く何か暖かいものでも食べて、元気をつけないと、
もう途方もないことになってしまうと、二人の紳士は思ったものでした。

扉の内側に、また変なことが書いてありました。
「鉄砲と弾丸をここへ置いて下さい。」
「なるほど、鉄砲を持ってものを食うという法はない。」
二人の紳士は鉄砲をはずし帯皮を解いて、それを台の上に置きました。
また黒い扉がありました。
「どうか帽子と外套と靴をお取り下さい。」
「仕方ない、とろう。たしかに、よっぽどえらいひとなんだ。奥に来ているのは」
扉の裏側には、
「ネクタイピン、カフスボタン、眼鏡、財布、その他金物類、ことに尖ったものは、
みんなここに置いてください」
と書いてあり、
扉のすぐ横には黒塗りの立派な金庫も、ちゃんと口を開けて置いてあり
鍵まで添えてあったのです。
二人の紳士は眼鏡をはずしたり、カフスボタンをとったり、
みんな金庫の中に入れてぱちんと錠をかけました。
すこし行きますと、また扉があって、その前に硝子の壺が一つありました。
扉には
「壺の中のクリ-ムを顔や手足にすっかり塗ってください。」
すると、すぐその前に次の戸があり
「早くあなたの頭に瓶の中の香水をよくふりかけてください。」
ところがその香水は、どうも酢のような匂いがするのでした。
二人の紳士は奇妙な注文が続き、不審には思いますが
それでも従い続けます。
最後の扉には
「お気の毒でした。もうこれだけです。
どうかからだの中の塩をたくさんよく揉み込んでください。」
ここで二人の紳士は、要約話の内容に気が付きます。

「たくさんの注文というのは、向こうがこっちへ注文しているんだよ。」
「西洋料理店というのは、来た人に食べさせるのではなくて、
来た人を西洋料理にして、食べてやる家とこういうことなんだ。」
悟りだすと、ガタガタガタ、震えだしました。
二人の紳士は逃げ出そうとしましたが、扉は動きません。
奥の方には大きな扉があって、大きなかぎ穴が二つつき
銀色のホ-クとナイフの形が、切り出してあって
おまけにかぎ穴からは、きょろきょろ二つの青い眼玉がこっちをのぞいています。
二人の紳士は、あんまり心を痛めたために
顔がまるでくしゃくしゃの紙屑のようになり、ぶるぶる、ふるえ声もなく泣きました。
そのとき、後ろからいきなり死んだはずの、
白熊のような2匹の犬が扉を突き破って室の中に入ってきました。
白熊のような2匹の犬は
「ワン、ワン、ぐわぁ」とうなり
かぎ穴の青い眼玉はたちまちなくなり、白熊のような2匹の犬どもは
吸い込まれるように飛んで行きました。
すると、室は煙のように消えて
二人の紳士は寒さにぶるぶる震えて草の中に立っていました。
見ると、上着や靴や財布やネクタイピンは、
あっちの枝にぶらさがったり、こっちの根もとにちらばったりしています。

白熊のような犬がふうと、唸って戻ってきました。
蓑帽子をかぶった専門の猟師が、草をざわざわ分けてやってきました。
そこで二人の紳士はやっと安心しました。
しかし、さっき一ぺん紙くずのようになった二人の顔だけは東京に帰っても、お湯にはいっても、
もう、もとのとおりにはなおりませんでした。
《私の感想》

~宮沢賢治は、コスモポリタニズム(理性をもっている人間はみな平等という思想)
の持ち主であるため、作品にもその色がでています。~
~宮沢賢治の作品は、宮沢賢治独特の世界に誘われます。~
~イギリス風の兵隊の恰好をした、若い日本の紳士は東京から山にやって来ました。
「鹿の黄いろな横っ腹なんぞに、二・三発、お見舞もうしたら、ずいぶん痛快だろうねぇ。」と、
野蛮なことを言ったり、犬を粗末(もの)に扱った二人の紳士たちです。
犬が死んだときは、犬の値段を、言うような(心、侘しい二人の紳士)が
最後は、犬に助けられるという皮肉なお話です。~
~自然を、大切にしない、二人の紳士の代償は
紙くずのようになった顔がもとに、もどらなくなってしまったことではないでしょうか。~
~宮沢賢治は、岩手県出身で農業学校の先生もしていました。
自然を、破壊したり、動物の命を大切にしない人が増えるこなど、
社会が変わっていくことの、不安を感じていたと思います。~

宮沢賢治(1896~1933)
昭和8年9月21日に急性肺炎で
世を去った。
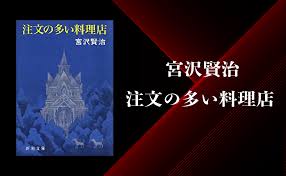
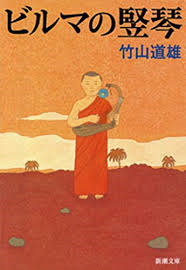
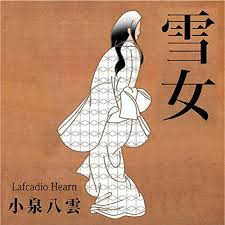
コメント