【高瀬舟】は、森鴎外が大正5年(1916年)1月の〔中央公論〕で発表された。
財産の観念「満足すること」
安楽死の考え方「安楽死は、許されるかどうか」
【高瀬舟】はこの二つの大きな問題をはらんでいると思う。

京都には高瀬川という川があり、高瀬舟とは島流しにされる罪人を乗せ、京都から大阪へと送られる。
京都町奉行の同心の羽田庄兵衛は、
弟殺しの罪で島流しとなった喜助を護送するため、
高瀬舟に同乗したが喜助の様子がおかしい、と思った。
一般的に高瀬舟に乗せられたものは、悲しそうな素振りをするのだが
喜助の様子は妙で罪人とは思えぬ楽しそうにしている。
同心はただ、勤めを果たすべく罪人と話すことは通例がないが
羽田庄兵衛はこらえ切れなくなって喜助にことの次第を聞いてしまう。
喜助は、《今までの辛く苦しい暮らしに比べれば、お牢では何の仕事もせずに食べ物が食べられ、
はじめて自分の自由になるお金を戴きまして、それを島の仕事の元手に出来ることが有難い》と言う。
弟を殺したのは、自殺をはかったが死にきれず苦しんでいたので弟に頼まれてのことだったと
羽田庄兵衛に話した。

幼い頃に両親を流行病でなくした喜助と弟は2人で助け合って生きてきた。
2人で京都の西陣の織場で働いていた時、弟が病で働けなくなってしまった。
ひとり仕事場に出る兄にいつも「申し訳ない」と言っていた。
喜助は生まれてから今まで貧しい暮らしで、骨を惜しまず働いても、銭はいつも右から左へと
人手に渡す生活であった。
それが、罪人になった今はお牢で、食べ物が食べれ自由になるお金まで戴ける、と
喜びを感じている喜助だった。
~私は自分に置き換えて、今まで「満足すること」の生活が出来たか、考えてしまった。
欲しいと思ったものは何が何でも手に入れたいと、「欲ばかりが先行していたのでは」と思う。~
羽田庄兵衛もただ漠然と、人の一生というような事を思ってみた。
人は身に病があると、この病がなかったらと思う。
その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。
万一の時に備える蓄がないと、少しでも蓄があったらと思う。
蓄があっても、又その蓄がもっと多かったらと思う。
かくの如くに先から先へと考えて見れば、人はどこまで往って踏み止まることが出来るものやら分からない。
それを今日、目の前で踏み止まって見せてくれるのが、この《喜助》だと羽田庄兵衛は気が付いた。
喜助は、弟と2人きりで生きてきたが、ある日、弟は自殺をはかっていた。
けれど、剃刀で切りどころが悪く死ぬ事が出来ない。
喜助に《自分を殺してほしい》と頼むがその申し出にためらった。
医者を呼ぼうとする喜助だが、弟の懇願により、殺しの手助けをしてしまった。
その場面を近所のお婆さんに見られてしまった。
~私は、喜助は弟の手助をしてしまったが、これは殺人といえるのか?
私には、わからない・・・・・・・・・・・・~

弟を《苦》から救うために命を絶った。
それが罪であろうか。
殺したのは罪に相違ない。
しかし《苦》から救うためであったと思うと、そこに《疑》が生じてどうしても解けぬのである。
羽田庄兵衛はお奉行様の判断を、そのまま自分の判断にしようと思ったのである。
そうは思っても、どこやら《腑》におちぬものが残っているので、
なんだかお奉行様に聞いて見たくってならなかった。
次第に更けて行くおぼろ夜に沈黙の人、
二人を載せた高瀬舟は、黒い水の面をすべって行った。
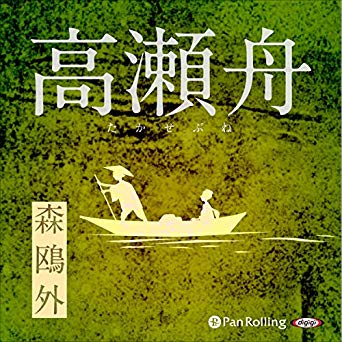
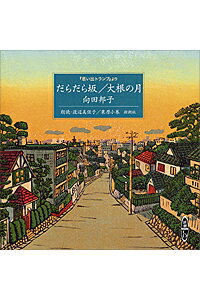

コメント