
~昭和十年代は大きな充実期で、昭和十八年には前年「婦人公論」で発表しました、
時代小説「日本婦道記」が第十七回直木賞に選ばれました。~
~しかし、山本周五郎は受賞を辞退し、以降一度も文学賞をうけることはありませんでした。~

~【さぶ】は複雑な男女の心理、周りの人たちの絆、
人間ひとりでは生きていけないことを教えてくれます。~
~無実の罪という試練に立ち向かう中で生まれた真実と友情を通して
ひたむきに生きていく姿~
~時代長編ですが、切なく、泣けてきます。~
~時代小説に、興味がなくってもとても読みやすく素直に感動できると思います。~
~あらすじは長いですが、物語としての形をとってますので読みやすいと思います。~
~何より、山本周五郎は庶民の目線で問いかけているので心に響くものがあります。~
《長いです!あらすじ》
小雨が靄のようにけぶる夕方、両国橋を西から東へ、(さぶ)が泣きながら渡っていた。
双子縞の着物に小倉の細い角帯、色のあせた黒の前掛をしめ、頭から濡れていた。
雨と涙とでぐしょぐしょになった顔を、ときどき手の甲でこするため、眼のまわりや頬が黒く
まだらになっている。ずんぐりした身体つきに、、顔もまるく、頭が尖がっていた。
彼が橋を渡りきったとき、うしろから栄二が追って来た。
こっちは痩せたすばしっこそうな身体つきで、面長な顔の濃い眉と、小さなひきしまった唇が
いかにも賢そうな、そしてきかぬ気の強い性質をあらわしているようにみえた。

この時、(さぶ)と栄二はともに十五歳。
二人は江戸の小舟町にある表具屋「芳古堂」の奉公人です。
不器用で口下手な(さぶ)は、奉公に上がってからの三年間、ずっとしかられ通しでした。
今日は、身に覚えのないことで責められ、揚げ句に「へまばっかりする小僧だ」とまで言われ、
店を飛び出したのです。
同じ年の栄二が後から追いかけて来て、慰めてくれたのでした。
実家に帰ると言って聞かない(さぶ)に、栄二は思いがけないことを話し出しました。

栄二は帳場の銭箱から、金を盗ったことがあるのです。
大好物のうなぎが食べたいための出来心でしたが、繰り返すうち、おかみさんに見っかってしまいました。
おかみさんはとがめもせずに、お金が欲しいなら自分のところに来いと言っただけでした。
栄二は、八つのときに火事で兄弟を失って行くところがありませんでした。
(さぶ)は「ごめんよ、栄ちゃん」
その話を聞いてようやく帰る気になりました。
五年が過ぎ(さぶ)と栄二は、二十歳になりました。
この頃栄二はめっきり腕を上げ、兄弟子の屏風や襖の仕事を手伝えるようになりました。
(さぶ)は糊の仕込みの腕こそ、驚くほど素晴らしいのですが、
いつまでも表具にかからせてもらえませんでした。
栄二と(さぶ)は堀江町の「すみよし」という小料理屋に、時おり飲みに出かけるようになります。
二人は、この店で働く(おのぶ)という十八歳の女と親しくなります。

栄二は(さぶ)にいつか二人で店をはじめようと話しますが、(さぶ)は首を縦に振りません。
栄ちゃんの重荷になるだけだと思っていました。
それから三年、
栄二はようやく一人前に仕事ができるようになりました。
その冬は、「芳古堂」の上得意、「綿文」の仕事をまかされました。
栄二は、十三の時から兄弟子について仕事に来ていましたから、家の者とは馴染みでした。
娘の(おその)と(おきみ)とは年齢が近いこともあり仲がよく、
栄二がどちらかの娘をもらうのではと、うわさされるほどでした。
しかし栄二はこの店の女中、(おすえ)のことをずっと思っていたのです。
ところが途中で、栄二は突然「綿文」の仕事から外されてしまいます。
なぜなのか納得できない栄二は、兄弟子の(和助)に相談に行きまず。
(和助)が言うには、
「綿文」の主人の大事にしていた古金襴の切が盗まれ、
それが栄二の道具箱からでてきたと言うのです。
親方は、小舟町へ行って考え、おかみさんに相談をしました。
おかみさんは、何かの間違いだろうと話しあっているうちに、
七年か八年のまえのことが、思いうかびました。
おかみさんは、以前栄二がうなぎを食べたいばかりに
帳場から金を盗んだことを思いだしたのです。
やけを起こした栄二は、何日も女遊びをした揚げ句、
べろんべろんに酔って「綿文」に乗り込みました。
けれど、店先でそのまま寝込んでしまい、ついに「芳古堂」から縁を切られてしまいました。
どうしても濡れ衣を晴らしたい栄二は、再び「綿文」を訪ねます。
直接旦那と話しをさせて欲しいと頼み込みましたが、
姿を現したのは印ばんてんに腹掛、ずんどうに紺の股引をはいている三人の男でした。
男たちは栄二を引きずり出し、ところ構わず殴りつけ、
栄二を番小屋に連れて行きました。
目明しに十手で、散々打ちすえられてしまいます。
そこにちょうど立ち寄った町周りの与力が、栄二の酷い姿に同情し、
身元引き受け人がいればこのまま帰してやろうと言います。
しかし、既に自暴自棄になってしまった栄二は、
石川島の人足寄場へ送られることになったのです。

人足寄場は、道を踏み外した人間を更生させるための場所です。
収容者は、罪人と見なされず手に職があるものは、
その仕事を許され、また、希望すれば身につけることもできました。
何も言わない栄二は、力仕事専門のもっこ部屋に回されました。
もっこ部屋の栄二は相変わらず誰も寄せ付けず、
けんかになると、徹底的に相手を締め付けていました。
三月ほどたったある日、どこで調べたかのか、突然(さぶ)が面会にやって来ました。
しかし、栄二は(さぶ)を見た途端に部屋を出てしまいます。
「栄ちゃん、どうしたんだ」
と(さぶ)は追いすがります。
それでも(さぶ)は、その日から五日ごとにやって来るようになりました。
しかし、栄二は(さぶ)に決して会おうとはしませんでした。
一方で栄二は、この人足寄場に来ている連中と少しずつ話をするようになると
彼らの身の上を知り、人がそれぞれ背負っている業の深さを思いました。
次第に栄二は、心を開くようになっていったのです。
何カ月かして、(おすえ)が面会にきても、栄二は「綿文」や、
(目明し)たちに復讐するのだと、言って聞きません。
涙を浮かべる(おすえ)に、栄二は自分のことは諦めて、もう二度と来るなと言いました。
七月のある夜、石川島は酷い大嵐に見舞われました。
建物はつぶされ、人足寄場は高波にのみ込まれました。
我を忘れて逃げ出そうとする人足たちを、栄二はうまく説得して、
病人と女を先に避難させました。
こうして、栄二は島の役人から一目置かれ、
人足仲間からも頼られる存在になったのです。
十月になり、護岸修理の工事をしていた時のことです。
栄二は突然崩れた石垣の下敷きになり、右足を折ってしまいます。
栄二はそのまましばらく病人置き場から動けなくなってしまいました。
その間、栄二は仲間たちから手厚い看護を受けます。
夜になると、大抵、
六、七人集まって来て、栄二を元気づけてくれます。
栄二は、この人たちには何もしていないのに、
おれのために心配してくれると繰り返し思いました。
気まぐれでなく親身の兄弟同様ではないか。
やがて栄二は仲間たちはそういう気質で、
栄二が気が付くようになっただけなのだと、思い当たります。
栄二は、世界が少しだけ開けたような気がしました。

しばらく顔をみせなかった(さぶ)が再びやって来るようになりました。
栄二のもとに通っていることが店に知れて、暇をだされていたのです。
年が変わった二月、
(さぶ)は栄二に二人で働く仕事場を借りたと告げました。
役人も栄二は、人足寄場から出た方が良いと言って、とにかくここを出て欲しいと頼みます。
栄二はなぜこれほど、自分ばかり心配されるのかと、(さぶ)に尋ねます。
(さぶ)は口もごりながら
「人間のすることに、いちいち訳がなくっちゃならない、ってことはないんじゃないか
お互い人間てものは、どうしてそんなことをしたのか、
自分でもわからないようなことをするときがあるんじゃないだろうか」
そして、一生に一度くらい自分の頼みを聞いてくれてもいいだろうと、詰めよる(さぶ)でした。
それから間もなくのこと、
栄二は与力に呼び出され、(さぶ)が引き受人を探し、
商売の手掛かりまでつけてくれたというのです。
与力は、今栄二にとって大切なのは過去の出来事を一切忘れて、
真面目な職人になれるかどうかなのだと論します。
栄二は、「芳古堂」のこと、「綿文」のこと、「目明し」のことを思っても、
前には血が煮え立つような怒りにおそわれたものでした。
けれども、今は心も騒がず
小さな残り火のように記憶の底のほうに消えかかっていました。
こうして栄二は(さぶ)と(おすえ)に引き取られて、新しい家にかえったのです。
それから二週間後、栄二と(おすえ)は祝言を挙げ、
(さぶ)と栄二は念願の二人の店を構えることができました。
しかし、何のつてもない新しい店に、すぐにまとまった仕事が入るはずもありません。
二人の店は、半年たっても赤字続きでした。
十月のある日、
栄二は「すみよし」の(おのぶ)から腕のいい表具師をさがしているという、客を紹介してもらいます。
江の島にある大きな料理屋での願ってもない仕事でした。
栄二は、早速仕事の準備を始めます。
しかし、(さぶ)は母が危篤という知らせを受けて、実家に帰ったまま何日も戻ってきません。
(さぶ)なしではいい仕事ができないと待ち続けていた栄二でしたが、
(さぶ)の仕込んだ糊を確かめようとした、そのとき壺のふたの裏に走り書きがあることに気付きます。
「おらがわるかった、栄ちゃんがあの切のことで島送りになったのは、おらの罪だ、
一生かかっても、おらはこの罪のつぐないをしなければならない」
栄二は、愕然としました。
しかし(おすえ)は、盗んだのは絶対に(さぶ)ではないと言い切ります。
こんなことを書いたのは、貴方を守れなかったことに責任を感じているに違いないと言うのです。
そして、(おすえ)は自分のひざを見つめながら、ささやくような声で
「あたし、謝ることがあるの」
と話し始めました。
「済みません、堪忍して下さい」
(おすえ)は板の間へ両手を突いて金襴の切を道具箱の中に入れたのは、あたしです」
栄二が「綿文」の娘のどちらかと夫婦になるという、うわさを聞いて(おすえ)は、ずっと思い悩んでいたのでした。
「自分でも分からないんですけれど、
「綿文」の旦那さまが、あの切を大切にしているのを知っていたので、それで、ふらふらと」
栄二は
「もういい」と言って、
「あとは聞かなくっても分かってる」
「ごめんなさい」
「泣くな」と言って、(おすえ)の身体を両手で抱きました。

(おすえ)は声を上げて泣き出しました。
「初めに行ったろう、おれの女房はこの世でおめえ一人だって、わすれたのか」
「おかしなことをいうようだが、笑わずに聞いてくれ」
栄二は静かに言いました。
「おれは島へ送られてよかったと思っている、人足寄場であしかけ三年、
おれはいろいろなことを教えられた、普通の世間ではぶっかることのない、
人間どうしのつながりあいや、気持ちのうらはら、生きてゆくことの辛さや苦しさ、そういうことを現に、身にしみて教えられたんだ、
読本、話でもない、なま身のこの身体で、じかにおしえられたんだ」
「人足寄場でのあしかけ三年は、しゃばでの十年よりためになった。これが本当のおれの気持ちだ。
嘘だなんておもわないでくれ、おれは今、おめぇに礼を言いたいくらいなんだよ」
(おすえ)は突然、両手で栄二の首に抱きつきながら「あんた」と叫びました。
そのとき、表の雨戸を叩く音がしました。
「いるかい、栄ちゃん、いま帰ったよ」
「さぶだ」
と栄二が言いました。
「おふくろがいま、息をひきとるか、
いま、息をひきとるかっていうありさまで、つい今日まで延び延びになっちまったんだ、
悪かったよ、栄ちゃん、勘弁してくれ、
おらだよ、ここをあけてくんな、さぶだよ」
《私の感想》
若いときに読んだときとは大分違い、年を重ねて再読すると、
改めて山本周五郎は私たち、庶民の生きていく応援歌のような気がしました。
庶民の生活、庶民の心、人間の奥深いところまで巧みです。
生きていくことは、色々なことに出会うものです。
その時は、無我夢中で乗り越えて、嵐が過ぎ去っていくと
妙に考えぶかくなってしまうものです。

山本周五郎(1903~1967)
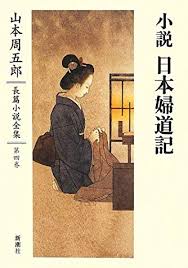
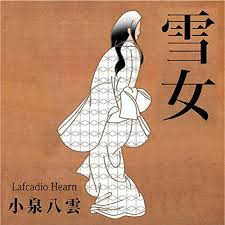
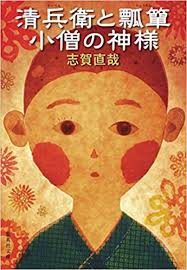
コメント