【秋】は、『中央公論』〔大正9年・4月]に連載され、
作品集〔夜来の花]に巻頭作品として初めて収録された。
芥川龍之介が当時のマンネリズムを脱するために試みたとされる、
≪近代≫ ≪現代≫ を題材とした心理の作品です。
幼馴染の従兄(俊吉)をめぐる姉(信子)と、妹(照子)の三角関係の愛と葛藤の物語です。
従兄(俊吉)を愛する姉(信子)は、妹(照子)に従兄(俊吉)を譲るため自ら身を引いた。
姉(信子)の視点から、三者の心理描写の揺れ動く心理が、高雅な趣で姉妹の心の揺れを見事に表現されている物語です。

信子は女子大学生にいた時から、才媛の名声になっていた。
彼女が早晩作家として文壇に打って出る事は、殆んど誰も疑はなかった。
彼女には俊吉と言う従兄があった。
彼は当時まだ大学の文科に籍を置いていたが、やはり将来は作家仲間に身を投ずる意志があるらしかった。
昔から親しく往来していた。
それが互いに文学と言う共通の話題が出来てからは、いよいよ親しみが増したようであった。
信子と従兄の俊吉との間柄は、勿論誰の眼に見ても、来るべき彼等の結婚を予想させるのに十分であった。
所が女子大学を卒業すると、信子は彼らの予期に反して、大阪の或商事会社へ近頃勤務する事になり
高商出身の青年と突然結婚してしまった。
信子はその間に大阪の郊外へ幸福なるべき新家庭を作った。
彼らの家はその界隈でも最も閑静な松林にあった。
松脂の匂いと日の光と、信子はそう言う寂しい午後、時々理由もなく気が沈むと針箱の引出しを開けては、
その底に畳んでしまってある桃色の書簡箋をひろげて見た。
妹の照子は姉が、別の男と結婚したのは自分が俊吉を好きだから姉が身を引いたのだという事を解っていた。
照子はその事を詫びる手紙を、嫁ぎ先の大阪に旅立つ姉に渡した。
信子はこの少女らしい手紙を読み返すたびに涙がにじんだ。
信子の結婚生活は徐々に心が離れていくようになってきた。
信子の夫は身綺麗で優しい夫だが、何かと細かい事(出費など)にねちねち文句を言ったり、
信子が小説を再開しょうとするとそれを理解するどころか皮肉を言う夫だった。
~文学と言う共通するものがあった俊吉と信子は、展覧会や音楽会へ行ったり気兼ねなく笑ったり話したりした。
だが、夫は文学には興味もなく、まして小説を書く事など、全く面白くもなく好まない。
結婚当初こそ、幸福を感じていたものの信子の心は夫からがだんだんと遠ざかっていく。
毎日が寂しい重くるしい日々の中、自分の感傷に慕っている信子。
私は、自己犠牲の上には結婚生活は成り立たないと思うが・・・・・・・~


照子と俊吉とは師走の中旬に式を挙げた。
信子はその翌年の秋、社命を帯びた夫と一緒に久し振りに東京の土を踏んだ。
忙しい夫とは外出も出来ないので信子一人で妹・照子の新居に行ったが、声に応じて出て来たのは意外にも従兄の俊吉であった。
照子と女中は留守であった。
かれこれ二年越しの気まづい記憶は、思ったより信子を煩はさせなかった。
一つ火鉢に手をかざしながら、いろいろな事を話し合った。
二人とも言い合わせたように、全然暮らし向きの問題には触れなかった。
それが信子には一層、従兄の俊吉と話していると強くさせた。
そのうち照子が帰って来た。
彼女は姉の顔を見ると、手を取り合わないばかりに嬉しがった。
間もなく信子は、妹夫婦と一諸に晩御飯の食卓を囲む事になった。
信子はこの楽しい食卓の空気にも、遠い松林の中にある寂しい茶の間の暮方を思い出さずにはいられなっかた。
信子はとうとう泊まることになった。
夕食の後、俊吉は誰をよぶともなく「ちょいと出て御覧。好い月だから。」と俊吉と信子は二人で散歩した。
俊吉は「鶏小屋へ行って見ようか。」
二人は肩を並べながら、ゆっくり鶏小屋まで行った。
俊吉は覗いてみて、殆んど独り言かと思うように
「寝ている。」と信子に囁いた。
「玉子を人に取られた鶏が。」
信子は草野なかに佇んだまま、そう考えずにはいられなかった。・・・・・・・・・・

~「玉子を人に取られた鶏が。」これは、玉子は(俊吉)人に(信子?・照子?)鶏(照子?・信子?)
俊吉は、何を言いたかったのか。・・・・・・・・・・・「寝ている」は俊吉は何を、意味しているのか?・・・・~
その間、照子は夫の机の上に、ぼんやり電燈を眺めていた。
青い横ばえがたった一つ、笠に遣っている電燈を。
翌日俊吉は一張羅の背広を着て、何でも亡友の一周忌の墓参りをするとかで信子に
「好いかい。待っているんだぜ。昼頃までにはきっと帰って来るから!」俊吉は外套を必掛けながら信子に念を押した。
姉妹二人だけになり愉しいはずの会話をしていたが、ふと照子は姉の沈んだ様子に気がついた。
柱時計が十時を打った時、信子はもの憂さそうな眼を挙げて「俊さんは中々帰りそうもないわね。」
照子は、ちょいと時計を仰いでこれは存外冷淡に「まだ-」とだけしか答えなかった。
信子には、その言葉の中に夫の愛に飽き足りている新妻の心があるような気がした。
そう思うと、信子は憂鬱に傾かずにはいられなかった。
「照さんは幸福ね。」信子は自然と忍び込んだ、真面目な羨望の調子だけは、どうすることも出来なかった。
照子は「お姉様だって幸福の癖に。」と、甘えるようにつけ加えた。
その言葉がぴしりと信子を打った。
姉の結婚生活が不幸なことを察すると照子は泣きだした。
信子は妹を慰めながら残酷な喜びを感じていた。
照子は昨夜の夜の夫と姉の散歩に《嫉妬》していた。
信子の心は静かであった。
静かさを支配するのは《寂しい諦めだった。》和解は新しい涙とともに、容易く二人を元の通り仲の好い姉妹に返した。

信子は従兄の俊吉を待たずに幌俥の上に揺られていた。
信子は妹とは永久的に他人になった心もちが意地悪く、信子の胸の中に氷を張らせていたのであった。
ふと眼を挙げた。
その時従兄の俊吉が見えた。
信子は動悸を抑えながら俊吉に声をかけるのをためらい幌俥はすれ違った。
【秋―】信子はうすら寒い幌俥の下に、全身で寂しさを感じながら、しみじみ思わずにはいられなかった。

~信子は《現実》を自覚し《全身》で《寂しさ》を感じたのである。
【秋】は薄ら寒く寂しいという季節に信子の《現実》の《寂しく虚しい諦め》
を、登場人物の心理を、象徴的に描いた作品だ。
はたして、信子は《現実》を自覚して生きていけるのか?・・・・・・・
《人》はいくら身を引いたとは言え、《人》は簡単に諦めきれるのであろうか?・・・・・・・
夫とは心が通わない生活に、信子は(絶望的な虚しさ)を、味わったまま
夫との生活を、果たして、出来るのだろうか?・・・・~

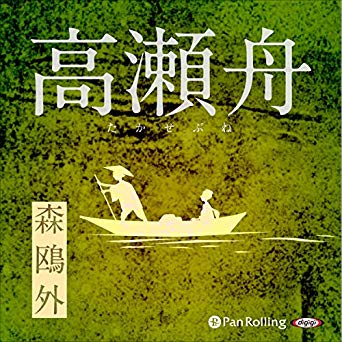
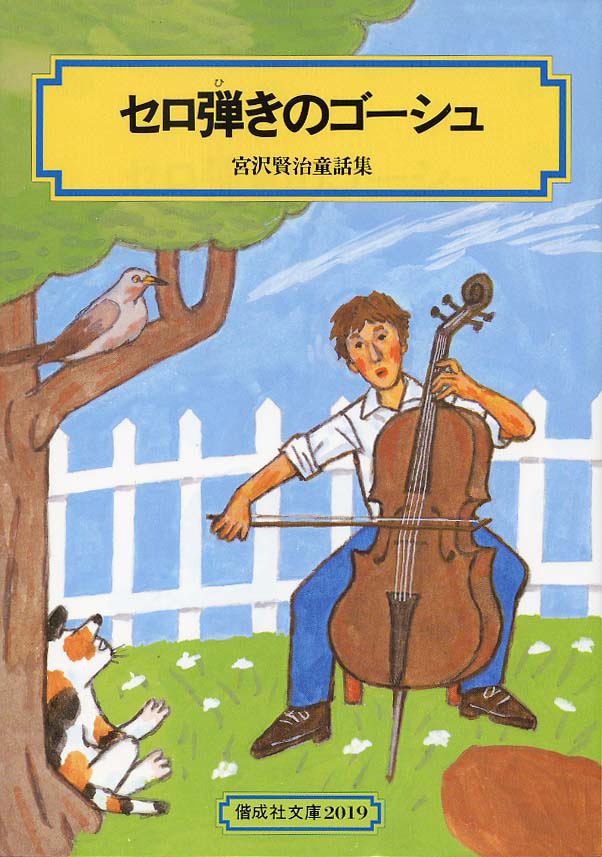
コメント