【今昔ものがたり】は、もともと11世紀後半に、
古くから日本に伝えられている、
あちこちの民話を集めて編纂(へんさん)されたもので、
実際に誰が行ったことなのかは、はっきりしていません。
ようするに、日本におけるグリム童話のようなものです。
「舞茸」
あらすじ
今はむかし、京都住まいの木こりたちが四、五人そろって
北山(きたやま)に遊びに出かけたところ、どうしてか道を、
間違えて、どちらへ行ったらどこへ出るか、途方に暮れていた。
大木(たいぼく)の茂る山の中で、方角がわからず、
「そちらへ行ってみょぅか」
とひとりがいえば、べつの木こりが、
「そちらへ行くと丹波(たんば)(今の京都府と兵庫県東部)
に出てしまう。こちらのほうはどうだろう」
「いや、こちらは比良山(ひらさん)に行ってしまうかもしれん」
「困ったぞ」
「困ったな。日がくれたら、狼がでるし」
と、どちらへ進むこともできず、しばらく立って嘆(なげ)いていた。
ふと、山の奥から人の気配(けはい)が近づいてきた
それもひとりではなく、数人らしい。
「何ものだろう。こんな深い山奥にまともな人間がくるはずがない。
山賊(さんぞく)か鬼じゃなかろうか」
とひそひそ、ささやき合っているうちに、
木陰(こかげ)の細道からあらわれたのは
意外にも墨染(すみそめ)の衣(ころも)を着た
上品な尼(あま)さんではないか。
それも四、五人が列をつくって、すごく優雅(ゆうが)な
手ぶり足つきで舞(まい)を舞いながら近づいてくる。
木こりたちはこれを見るとぶるぶる震えだした。
「この深山(しんざん)の中をあんなに舞を舞い歌を歌いながら
やってくるとは、あの尼ども、ぜったいに人間じゃない。
天狗かおにが化(ば)けているんだぜ。どうしょう」
と思って、ただながめていると、尼たちは舞いながらも、
木こりどもを見つけてそばに寄ってくる。
木こりたちは、きみ悪く、内心こわくってたまらないけれど、
今さら逃げるひまもなく、すぐそばまできた尼たちに
「これはこれは」
とていねいに声をかけた。
「どこの尼さま方(がた)で?どうしてこんなに舞いを歌いながら、
深山の奥から出ていらっしゃったのでございます?」
尼たちがこたえるには
「あたしたちが、こんなに舞い歌いあがらやってきたので、
おまえさんたちも、きっとこわがっているのでしょう
(木こりたちはうなずいた)
そうでしょうね。しかしあたしたちは、この近くの尼寺に住んでいる
尼僧(にそう)ですよ。
花を折てきて仏に捧げようと思って、一緒に山に入ったけれど、
道を踏(ふ)み迷って、山から出られなくなりましてね。
食べものを用意しておらず、困っていたところ、
茸(きのこ)が生えているのを見つけたのです。
おなかがへっていたので
『これを取って食べたらあたりはしないだろうか』
と、思いながらも
『飢え死にするよりは、あたってもましでしょう。
さあ、取って食べましょう』
と、その茸を取って、焼いて食べてみたところ、
すごくおいしかった。
よいものを見つけたとたくさん食べたら、ひとりでに手足が動いて
舞いを舞わずにいられなくなったのです。
心では、ふしぎですねぇとお互いにいいながら、
このとおり舞い歌うのをやめられません。ふしぎですねぇ」
そう語りながら舞い続けているのを、木こりたちはあきれてながめていた。
ところが木こりたちも、腹ぺこだったので、
尼たちが残して持っていた茸に目をつけて、
「飢え死にするよりは、この茸をいただけませんか。
食べてみます。」
と、もらって食べるや彼らもまた、ひとりでに舞を舞い始めて、
やめることができなくなった。
尼たちも木こりたちも
「とまらない」
「とまらない」
と互いに舞いながら、笑った。
それでしばらく舞っていたところ、酒の酔いからさめたように、
どんな道を通ったか知らずに、それぞれ自分の家に帰っていた。
それ以後、この茸を舞茸というようになった。
今では踊り茸(たけ)とか、笑い茸(たけ)とかいっている。
近ごろも舞茸という、きわめて美味(びみ)のきのこがあるけれど、
これを食べてけっして舞いだすことはない。
ふしぎなことだと語り伝えている。
《私の感想》
日本の昔話は、ファンタジックで夢があります。
ハイテクの時代ですので昔話には中々触れることは
ないですがたまには読んでみるのも一息つけます。
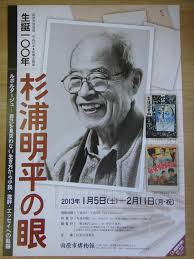







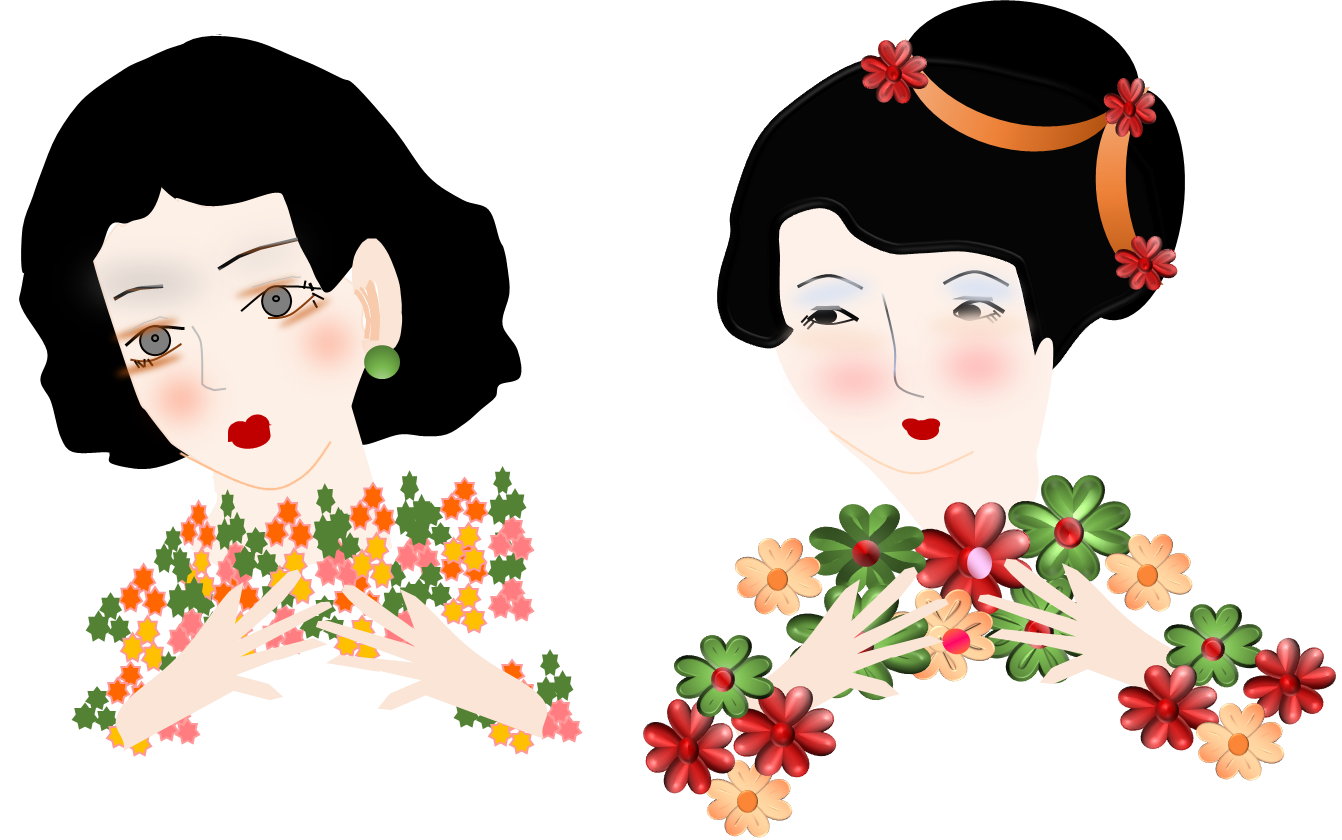

コメント