
~芥川龍之介の【蜜柑】は、短編小説です。
「心温まる」作品です。~
~芥川龍之介の体験が物語になっています。
物語の情景と、場面場面が鮮やかに目に浮かんでくる小説です。~
~この、物語の登場人物は、(私)芥川龍之介と(娘)の2人です。~
《あらすじ》

ある曇った冬の日暮れである。
私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろして、ぼんやり発者の笛を待っていた。
とうに電燈のついた客車の中には、珍しく私の外に一人も乗客はいなかった。
が、やがて発車の笛が鳴った。
ところが、けたたましい日和下駄の音が、改札口の方から聞こえ出したと思うと
間もなく車掌の何か罵る声と共に、私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて
13歳~14歳の小娘が慌ただしく中へ入って来た。
巻煙草に火をつけながら、始めて、物憂い目蓋をあげて、
前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一べつした。

それは油気のない髪をひっつめ、銀杏返しに結って、
横なでの痕(あと)のあるひびだらけの両頬を、
気持ちの悪い程赤く火照らせてた、いかにも田舎者らしい娘だった。
しかも、垢じみた萌黄色の毛糸襟巻が、だらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあった。
その又、包みをだいた霜焼けの手の中には、三等の赤切符が
大事そうにしっかりにぎられていた。
私はこの小娘の下品な顔だちを好まなかった。
それから彼女の服装が不潔なのもやはり不愉快だった。
最後に、その二等との三等の区別さえわきまえない、愚鈍な心が腹立たしかった。
だから巻煙草に火をつけた私は、この小娘の存在を忘れたいと言う心もちもあって、
ポケットの夕刊を漫然膝の上へひろげて見た。
それから幾分か過ぎた後であった。
ふと何かに脅かされたような心もちがして、思わずあたりを見まわすと、
いつの間にか例の小娘が、思い硝子戸を中々思うようにあがらないらしい。

しかし汽車が今まさに隣町の口へさしかかろうとしている事は、
蒼色の中に枯草ばかり明るい山腹が、間地かく窓側に迫って来たのでも、すぐに合点の行く事であった。
にも関わらずこの小娘は、わざわざ閉めてある窓の戸を下そうとする、
この理由が私には呑み込めなかった。
すると間もなく、凄まじい音をはためかせて、
汽車が隣道へなだれこむと同時に、小娘の開けようとした硝子戸は、とうとうばたりと下へ落ちた。
そうして四角な穴の中から、すすを溶かしたようなどす黒い空気が、
にわかに息苦しい煙になってもうもうと車内へみなぎり出した。
元来、喉を害していた私は、ハンカチを顔に当てる暇さえなく、
この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけない程、咳こまなければならなかった。
しかし、汽車はその時分には、もう安々と隣町をすべりぬけて、
枯草と山と山との間にはさまれたある貧しい街はずれの踏切に通りかかっていた。
踏切の近くには、いずれも見すぼらしい藁屋根や瓦屋根が、ごみごみと狭苦しく立て込んでいた。
やっと、隣町を出たと思う、その時、
踏切りの柵の向こう私は頬の赤い三人の男の子が、目白押しに並んで立っているのを見た。
彼らは皆、そろって背が低かった。
そうして又、この町はずれの陰惨たる風物と同じような色の着物を着ていた。
それが汽車の通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を挙げるか早いか、
いたいけな喉を高くそらせて、何とも意味の分からない、かんせいを一生懸命にほとばらせた。

するとその瞬間である。
窓から半身を乗り出していた例の娘が、あの霜焼けの手をつと、のばして、
勢いよく左右に振ったと思うと、
たちまち心を躍らすばかりに暖かな日の色に染まっている蜜柑が
およそ五つ六つ、汽車を見送った子供たちの上へばらばらと空から降って来た。
私は思わず息を呑んだ。
そうして刹那(せつな)に一切を了解した。
小娘は、恐らくはこれから奉公先へ、おもむこうとしている小娘は、
その幾らかの蜜柑を窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りにきた弟たちに
労を報いたのである。
蒼色帯びた町はずれの踏切と、小鳥のように声を挙げた3人の子供たちと、
そうしてその上に乱落する、鮮やかな蜜柑の色と、
―すべては汽車の窓の外に、またたく暇もなく通り過ぎた。が、
私の心の上には、切ない程はっきりと、この光景が焼きつけられた。
そうしてそこから、ある得体のし知れない朗らかな心持ちが湧き上がって来るのを意識した。
私はこの時始めて、言いようのない疲労と倦怠とを、
そうして不可解な、下等な、退屈な人生を僅かに忘れる事が出来たのである。

《私の感想》
私は、【蜜柑】を読んでいて心が温かくなりました。
でも、娘の気持ちを思うとなんとも言えない寂しく、切ない気持ちになってしまいました。
13歳か14歳の娘がこれから先、親、兄弟と離れて奉公にでることは、
どんなにか大変なことか胸が熱くなります。
芥川龍之介が、見事な表現で娘が蜜柑をばらまくシーンは、私も読んでいて目に浮かびます。.
芥川龍之介の心の変化のとらえ方、表現力の素晴らしさは、本当に凄いと思いました。
.

芥川龍之介の死の八年後の昭和十年、
当時「文藝春秋」を主宰していた菊池寛は、龍之介の文学への大きな貢献を記念して
純文学の新人賞「芥川龍之介賞(通称芥川賞)」を設立しました。

芥川龍之介(1892~1927)

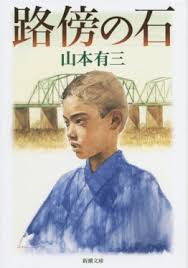
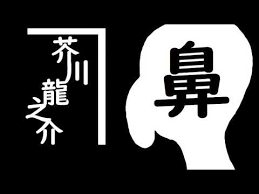
コメント