
~【赤いろうそくと人魚】は、以前、絵本で読みました。
〈人魚の〉美しさと、純粋な心が痛いほど伝わってきて、切なくなった思いです。
今、本で読んでみて〈人間〉のエゴイズムが見事に綴られ、
善い人も時と場合によって変貌するものだということが、
リアルに描かれています。~
《あらすじ》
北の暗く寂しい海に身重の人魚が棲んでいました。
産まれる子供には、自分のように寂しい思いをさせたくないと思ってました。
人間のすんでいる町は美しいというし、人間はやさしいと聞く。
子どもには明るく優しい人間の町で暮らしてほしいと考えた人魚は、
ある夜のこと神社の石段に赤ん坊をうみおとしました。
赤ん坊は、神社のふもとにある貧しいろうそく屋の老夫婦に拾われました。

人魚の子は、大切に育てられ、美しい娘に成長しました。
娘が、店の白いろうそくに赤い絵を描くとたちまち評判になり、
ろうそく屋は、大繁盛しました。
神社に納めたろうそくを灯して漁に出ると、どんな大暴風雨の日でも
決して死ぬような災難がなく、無事に帰って来れるということが、
いつからともなく、噂になり評判はますます高まっていきました。
ある時、赤いろうそくのうわさを聞きつけた行商人(香具師)が、
人魚の娘に目をつけ、莫大な大金を持って、老夫婦に売ってくれないかとせがみます。
老夫婦は、「神様から授かった子だから。」と、最初のうちは断っていました。
やがて、「人魚は、不吉なものだ。今のうちに手放さないと、きっと悪いことがある。」と言う、
行商人(香具師)の言葉を信じてしまい、莫大な大金にも心を奪われ、
とうとう娘を売る約束をしてしまいました。
娘は、「私は、どんなにでも、働きますから、どうぞ知らない南の国へ売られてゆくことは、許してくださいまし」
鬼のようにな心持ちになった老夫婦は娘のいうことを聞きません。
娘は、最後のろうそくは、急き立てられるので,悲しい思い出に3本赤く塗ってしまいました。
ほどなくして、行商人(香具師〉がライオンやトラなどを入れる檻をもってきました。
娘は、檻に入れら連れていかれました。

それから、後、色の白い女が赤いろうそくを買いに来ました。
その夜のことです。
急に空模様が変わって近頃にない大暴風雨になりました。
嵐はますますひどくなり、娘を檻の中に入れた船も難破してしまいました。
その後、毎晩神社に灯る赤いろうそくは死を招く不吉と言われ、
それを見たものは海で溺れ死んでしまうと言われました。
神社は、鬼門として忌み嫌われました。
幾年もたたずしてふもとの町は滅びて、なくなってしまいました。
《私の思い》
~色の白い女が、赤いろうそくを買いにきたのは母親だと思います。
赤いろうそくを見て全てを悟ったと思います。
母親は、檻に入れられた、娘を助けに行ったと思います。
ろうそく屋の老夫婦は欲にくらんで娘を売り飛ばしました。
色の白い女(母親)が、神社も町も滅びさせ、なくならせてしまったと思います。
色々と考えてみますと、大金を目の当たりにして人間は
ちょっとした弾みから一舜目がくらんで、欲に走ることもあるような気もします。
この物語は大人が読んでも、考えさせられると思います。~

小川 未明(おがわ・みめい)
1882年4月7日~1961年5月11日
小説家・児童文学作家・本名小川 健作(おがわけんさく)
「日本のアンデルセン」 「日本児童文学の父」とよばれる。
娘の岡上鈴江も児童文学者。
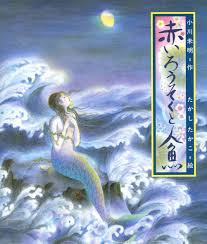
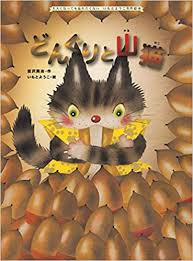
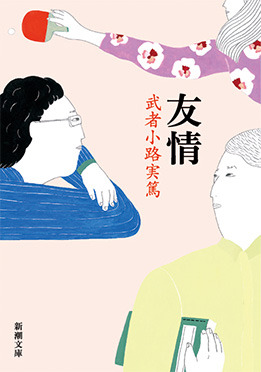
コメント