
~山本有三の代表作【路傍の石】(ろぼうのいし)は、日中戦争の始まった。
昭和12年に「朝日新聞」紙上で連載を始め、厳しい検問を受け連載中止に追い込まれます。~
~翌13年には「主婦之友」で「新編・路傍の石」として、続きを書き始めましたが、
これも検問により昭和15年の7月号で連載中止になり未完で終わっています。~
~【路傍の石】という言葉は朝日新聞にて1937年に連載が開始された、
山本有三が中期の明治時代を舞台に書いた【路傍の石】が、
この言葉の語源であります。~

~【路傍の石】とは、
その辺の道に落ちている石のように、存在感のないものに使われる言葉です。
そのあたりに転がっている石のように居ても居なくても同じもの、
その程度の価値のものと、いった意味を持っています。~
《あらすじ》
愛川吾一は、とある田舎の高等小学校2年生です。
家は13代続いた旧家でしたが、今ではすっかり没落していました。
しかし武士の家柄を誇りとする父の庄吾は、地道に働こうとせず家庭も顧みません。
さらに村役場を相手に訴訟を起こしていつも東京に行っており、
母が袋貼りの内職で家計を支えている始末でした。
生活は苦しく、成績優秀な吾一を中学校に進学させる余裕などありません。

吾一の将来を案じた担任の次野先生の計らいで、昔から吾一を可愛がってくれた
稲葉屋という本屋の主人が、中学校の学費を出してくれることになりました。
しかし、父は「武士の子が他人の金で中学に行くな」と猛反対します。
結局、吾一はあれほど堅く誓った進学を断念せざるを得ませんでした。
そして父が残した借金のカタとして、同級生の秋太郎の両親が営む
呉服屋、伊勢谷に奉公へ出ることになりました。
伊勢谷では、吾一は名前を(五助)に変えられ下働きとしてこき使われます。
自分より成績が劣っていた秋太郎を(坊ちゃん)と呼び、
宿題を手伝わされ、自分を慕っていた(おきぬ)にも、見下されてしまいます。
奉公先で前かけを一枚しめるだけで、吾一の立場はひどく低くなってしまったのです。

しばらくして、母が倒れたとの知らせが吾一に届きました。
吾一は急いで駆け付けますが、過労で弱っていた母は心臓発作で亡くなってしまいます。

ある朝、吾一は、使いで外に出たことを機に伊勢谷を逃げ出し、
東京行きの汽車に乗り込みました。
本郷にいるはずの父を訪ねましたが、姿をくらましていました。
行くあてのない吾一は、そのまま父のいた下宿先に置いてもらうことにしました。
しかし、そこではランプ掃除やら雑巾がけやら、使いにだされるやらと、何かと雑用に使われました。
しかも「小僧」とよばれ、伊勢谷にいたときよりもひどい待遇を受けたのです。

同じ下宿人で両学生の黒田は、吾一のためにダルマのポンチ絵を描いてくれました。
そこには「自分の足で歩いてごらん」という文字が書きそえられていました。
やがて吾一は黒田のおかげで、印刷所で原稿に従って活字を選び出す、
文選工の見習いの仕事に就きます。
仕事はとても辛く、吾一は何度も泣きましたが、黒田が教えてくれた
「かんなん、なんじを玉にす」
つまり、人は多くの苦しみや困難を経て初めて立派な人間になるという意味の言葉を胸に辛抱しました。
印刷所の炊事場にいる、「じいや」もまた、吾一を慰めてくれました。
「じいや」は「出世をしたいと思ったら人より多く働きなさい」とも言いました。

ある日、吾一は再会した次野先生から、自分を可愛がってくれた
稲葉屋のおじさんが亡くなったことを聞きました。
稲葉屋のおじさんは吾一の中学校への援助にと、次野先生にお金をあずけていましたが、
先生は
「実はのその学費を遣い込んでしまった」
と言いにくそうに告白したのです。
吾一は、次野先生のことを許すと共に、信じ続けるとも言いました。
その後、19歳になった吾一は先生の計らいで、夜学の商業学校にへ通うことになりました。

印刷所が休みの日、先生の家を訪ねると、東京の女学校へ通う、
伊勢谷、秋太郎の妹(おきぬ)と、ばったり顔を合わせました。
「てまえ」という言葉を強いられてきた少年にとって、
「ぼく」という一人称は実に尊いものでした。
吾一は、もはや奉公の小僧だった(五助)ではないのです。
印刷所で日給取りになった吾一は、商業学校を卒業し、
私立大学の夜学に進学しました。
やがて吾一は、手帳を売って生計を立てる貧しい少年と、
出会い彼の家の屋根裏部屋に間借りすることになりました。
家には少年の姉(およね)と、兄の(得次)が暮らしており、
吾一は清純な(およね)に好感を持ちました。

ある風の強い晩、火事が起こり印刷所に燃え移りました。
吾一は、火が回る前に大切な原稿が焼けてしまわないようにと、
原稿を入れた箱を安全な製本所に運び込んでいました。
印刷所が燃えた主人はそれを知って喜び、褒美に金時計をくれると言います。
しかし、吾一は身分不相応だからと遠慮し、結局支配人が預かることになりました。
吾一はただ一生懸命働いていただけなのに、これ以来、
他の文選工から「ゴマすり」だと言われるようになってしまいました。
やがて、吾一は社員に抜擢されます。
吾一は事務職になりました。
身体が楽になり収入も上がったので、速記を習いはじめます。
ある日、速記の練習のために、家で(およね)がおとぎ話を朗読してくれました。
吾一の手がしびれて動かなくなると、(およね)は、吾一の手を
自分のあごの下に入れて温めてくれました。
そのとき、吾一はまるでおとぎの国にいるような気持になり、
自分が(およね)に惚れていることに気づきました。

秋になって、何年も行方の知れなかった父が、突然訪ねてきます。
身勝手な年老いた親を放っておけず、(およね)と離れることはさびしく思いながらも
家を借りて父と暮らし始めました。
父と生活するお金を稼ぐため、吾一は印刷所の仕事のほかに、
身につけた速記を生かして副業をはじめました。
やがて、その実力を認めてくれた出版社に入社します。
ある日、吾一は次野先生に呼び出され、料理屋へ行きます。
すると先生は、以前使い込んでしまったお金の半分を、自分の原稿料で返してくれました。
しかし、そのお金は、またしても父が使い込んでしまいました。
それでも吾一は、印刷所の支配人に預かってもらっていた金時計を担保にして
出版社興しました。
経費を減らすため、自分で活字をひろい、社長でありながら職工も務めました。
自分で速記した原稿の文字を自分でひろうことに吾一は喜びを感じました。
雑誌の名前は「成功の友」。
多くの人に買ってもらうため、定価の格安の十銭にするなどの工夫もしました。

吾一は、次野先生に会社を興して雑誌を作ることを知らせ、小説の連載を依頼します。
しかし、先生の反応は予想外のものでした。
吾一は、次野先生に読者の血をわかすような小説を書いてもらいたかったのですが、
「成功」「立身出世」などに、嫌悪感を持つ先生は怒りをあらわにするばかりでした。
次野先生にまくしたてられ、吾一は一舜黙ります。
しかし、強い思いがあふれ出し興奮してこう言いました。
「先生、わたしは何も成功しようとか、出世しようとか思っているわけじゃありません。
わたしはただ見返してやりたいのです。ぶんなぐられたまま、蹴っ飛ばされたままで、
死んでしまうわけにはいきません。石の下におっこちた種は、石をもちゃげてでも伸び
て行かなくちゃいられません。わたしのようなものは……….わたしのようなものは……」
吾一の顔は真っ赤になっていました。
雨が激しく降るある晩のこと、落雷による停電で真っ暗になった工場で、
吾一はひとり立ちつくし、考えました。
「いかに生きるか。」が第一だと先生はいった。しかし「いかにして生きるか。」が、おれたちの
ようなものにはもっと問題ではないだろうか。
先生はついに先生だ、おれはおれだ。どんづまりのところへ行けば、人間やっぱし一人一人だ。
先生のような人とだって別々だ。
先程まで轟いていた雷鳴はいつの間にか消え、強く降り続いていた雨も絹糸のように弱くなりました。
やがて辺りはだんだん明るくなっていきました。
向こうの空が兎の耳のように、薄く色づいてきた。
軒先にはまだ絹糸のようなものが何本かゆるく垂れていた。「パン、パ-ン。あまいパン。あったかいパン。」
行商のロシヤ・パン売りの声が、もう往来の方から響いてきた。
《私の感想》

~「たったひとりしかいない自分を、たった一度しかない一生を、
本当に生かさなかったら、 人間、生まれてきたかいがないじゃないか」
【路傍の石】の一節です。~
~山本有三は続きを書こうとしましたが
当時軍国主義だった日本は個人の主張は認められない時代です。~
~自分の夢のために奮闘するこの物語の主人公の生き方は、
軍国主義では通らなかったと思います。~
~自由な表現が規制された時代、昭和初期の軍国主義の理不尽さ、
山本有三にとって、どんなに息苦しく、大変な時代だったかと思います。~
~続編が出来ないのはとても残念ですが、逆境に負けない吾一は
夢と、希望を、持って、自分の人生をひたすら歩んでいくと、考えると
未完としても楽しめると思います。~

山本有三(1887~1974)
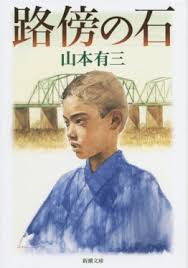
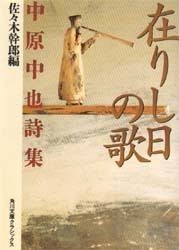

コメント