
~竹山道雄の子ども向け小説【ビルマの竪琴】は、昭和22年(1947年)の3月から
翌年の2月まで中断を挟みながら雑誌「赤とんぼ」で連載されました。
昭和21年に創刊されたばかりの児童雑誌で編集帳の藤田圭雄の要請に
応えて連載がはじまりました。~
~物語は、完全なフィクションで、ビルマ(現在のミャンマ-)の風俗や景色なども
資料を基にした竹山道雄の想像です。~
~【ビルマの竪琴】は、児童文学なので、綺麗にまとめてますが、戦争の無情さや
やるせなさをイギリス民謡「はにゅうの宿」に込められています。~
《あらすじ》
第二次世界大戦時の1945年、ビルマ(現在のミヤンマ-)に
この部隊の隊長は音楽学校を出たばかりの若い音楽家で、ビルマにいた間
兵隊たちに合唱を教えていたのです。
おかげで、部隊は規律を保つことができ、お互いの仲間意識を強くしていました。

合唱には、自分たちが作った楽器で伴奏もつけました。
一番よく使われていたのは、竪琴です。
これは、ビルマ人が弾く竪琴をまねて作ったもので、水島という名の上等兵が
この竪琴の名人でした。

幾度も恐ろしい目に遭い、もう駄目だと思った
時水島上等兵の竪琴が不思議なほど役に立ったのです。
水島上等兵は一人で部隊から離れ、竪琴を演奏して
敵兵を遠くへ誘ったり、時にはビルマ人になりすまして偵察に行くこともありました。
そこが安全か、危険かを、奏でる曲を合図にして部隊につたえるのです。
彼らはイギリスで生まれた「はにゅうの宿」を歌い終え、
いよいよ隊長が突撃の号令をかけようとした、その時です。
声が聞こえました。
森の中から歌う声が聞こえてきました。
ついに大合唱になったのです。
やがて、森から広場へ人影がぱらぱらと走りでてきました。
イギリス兵でした。
兵士たちは郷愁に誘われたのです。
その夜、我々はもう3日も前に停戦になったことを知りました。
日本は降伏したのです。
この日からイギリス軍の捕虜になりました。

それから数日後、隊長が水島を呼びました。
まだ山の中に立てこもって戦闘を続けている日本兵がいる。
イギリス兵と協力して、彼らを説得してきて欲しいと言うのです。
更に隊長は、この役目を果たした後、
ムドンという町の捕虜収容所で合流すように水島に、伝えました。
水島は、直ぐに、身支度をして竪琴をかついで、
はるか崖の下を歩いて行くのが見えました。
しかし、その後何日経っても、水島はもどってきませんでした。

そんなある日、隊長は水島によく似た顔つきと表情があまりに似た僧侶をみかけました。
肩に青いインコをのせていて、話しかけても返事をせずに行ってしまいました。

その晩のことです。
収容所に帰った我々のもとに知らせが来ました。
「おーい。おれたちは日本に帰ることになったぞ!
ムトンにいる捕虜にはみな帰還命令がでた。出発は、今日から5日目だ!」
日本に帰ることが分かってからというもの、
我々は収容所の庭に出て合唱を続けながら、あの僧を柵越しに探していたのです。
そしていよいよ明日帰還するという日、声のかれるほど歌っていると、
両肩にインコをのせたビルマの僧が、姿を現しました。
我々は、「はにゅうの宿」を歌い始めました。
近くにいた少年の竪琴を、手に取ると、
あの「はにゅうの宿」の伴奏を激しくかき鳴らしたのです。
このビルマの僧はやっぱり水島上等兵だったのです。

歌がすむと、戦友たちは、内の柵のところへ走っていって、
そこから身をのりだし手を差し伸べて叫びました。
「水島、我々は明日、日本に帰るのだぞ!」
「よかったなぁ!とうとうもどってきて」
「さあ、早くこちらに入ってこいよ!」
しかし水島は無言のまま柵の向こうで黙ってうつむき、
「仰げば尊し」を奏で始めました。
弾き終えると、水島は淡々と頭を下げ身をひるがえして、去って行きます。

帰国の日、ビルマ人の物売りの婆さんから、水島から託された
隊長あての手紙を出しました。
日本に向けて船が出発して3日目、
隊長は納骨堂に安置された日本の箱を見て水島の気持ちが分かったのだと
一同の前で明かしました。
そこには、隊長と別れてから水島が体験した出来事が記されていました。
水島が仲間の降伏の説得に、出発してからの出来事と、
ビルマの地で命を落とした日本兵を弔うために
ビルマに留まることを決心したこと、など、
出家をして僧侶になったことなど仲間への感謝の気持ちが綴られていました。
隊長が、長い手紙を読み終えました。

水島の本心が分かった我々は、何かしっかりした覚悟が決まったように思いました。
我々は低い声で歌い始めました。
潮騒の音が船をつつんでいます。
波は飛沫をあげてくだけて、
そこの方から、歌にあわせる竪琴の音が上がってくるかと思われました。

《私の感想》
~戦争中一高(現在の東京大学)の教師であった竹山道雄は、
自身は軍隊の経験はほとんどなかったが、徴兵され出征していった教え子たちの戦死の報に
いつも心を痛めていたという。~
~私は、竹山道雄氏の気持ちを思うと、胸に迫ってくるものを感じてしまいました。
水島上等兵は、戦没者の追悼を込めて、ビルマに留まり僧侶になりました。
異国の地で白骨化した多くの自国民たち。~
~彼らをこのままにしておくのは、忍びないと思う気持ちと、意志の強さを深く感じました。
ビルマで朽ち果てた日本人を、葬る気持ちも理解できますが戦争は悲惨すぎます。~

竹山道雄
作品は市川崑監督によって、
昭和31年と60年に、2度映画化された。

無謀と言われたインパ-ル作戦 戦慄の記録
上層部の人間関係が優先された意思決定
かつてビルマと呼ばれていた、インドシナ半島西に位置するミャンマ-
1944年3月に決行されたインパ-ル作戦は、
川幅600mにも及ぶ大河と2000m級の山を越え、
ビルマからインドにあるイギリス軍の拠点インパ-ルを3週間で攻略する計画だった。
しかし、日本軍はインパ-ルにたどり着けず、
およそ3万人が命を落とした。
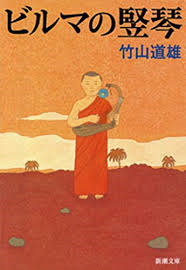

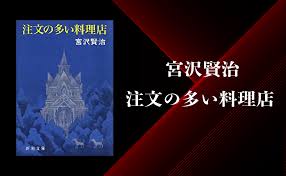
コメント