
~私は、松本清張の作品が、大好きです。
サスペンス仕立ての物語の展開が鮮やかで、
読者を誘うミステリ-の手法がふんだんに盛り込まれていて
読むごとに引き付けられます。
時代小説であっても、息を呑むほどで
[お見事]と思わずにはいられません。~

~『無宿人別長』は、
昭和32年(1957年)9月号から翌年8月号まで
「オール読物」で連載された松本清張の連作時代小説。
全十編からなってます。
それぞれ無宿人を主人公にした、その中の一編です。
無宿人とは、江戸時代の戸籍帳簿です。
(人別帳)に名の記載されていない者のことです。~
≪あらすじ≫
江州無宿の与太郎が、博奕場での争いで
人を斬って伝馬町に入牢しました。
与太郎は、その晩から腹を押さえて苦しみだしました。
江州草津の与太郎が、五日間飲まず食わずの苦しい修行をして
仮病を遣い、牢付医者の袖の中に二分銀を落としたのは、
溜め送りになりたいためでした。
いや、実は
それから先の第二段の目的がありました。

浅草の溜めに入ると、そこで出会った
信州無宿の市助と、若い無宿人二人、合わせて四人は、
それから二日して、外に雨の降っている真夜中に脱走をしました。
与太郎は、市助と連れ立っていたら、ろくなことしかないと思い、
隙をみて離れて、やろうと思っていました。
途中で、市助と与太郎は
駕籠かきを、おどかし、駕籠かきに変装をしました。
甲州街道を目指していましたが、駆け落ちの男に呼び止められました。

そこに、暗い中でも、すらりとして小股の切れ上がった女がいました。
裾をからげた素足がほの白く、市助は何となく唾を呑みこみました。
女を乗せることになったのですが、にわか駕籠かきの足どりは
危なっかしく、慣れないせいで直ぐに休んでしまいます。

市助と与太郎を不信に思った男は、二人に揉み合いになり
男が道中差しを出したとき、与太郎は取り上げ
道中差しを背中に向けて振りおろしました。
与太郎は、灼けるようなものが走り、痛みになり、
左手の人差指と中指の2本が消えたように脱落してしまいました。
しかも気付いた時は、市助は男の財布と女を奪って逃げていたのです。
五年後、与太郎は信州岡谷で博奕打ちになっていました。
あれから、信州に流れ込むと
盆の上の鮮やかな手際を売り物にしているうちに
岡谷で一番勢力を張っている、粟津の久兵衛という
貸元の身内になっていたのです。
溜抜けをした手配書は、このあたりにも流れていたはずですが
探索手は与太郎には、及びませんでした。
与太郎は、市助を探し出さずにはおられませんでした。
指二本を失ったのも、
もとはといえば市助のせいです。
仕返しに、せめて市助の指二本を切り落とさずには気が済まなかったのです。
信州を流れ歩いたのは、市助が信州松代生まれと聞いたからです。
与太郎が、粟津の久兵衛の子分になって四年目、
久兵衛が中風で倒れると、与太郎はその跡目に座りました。
親分としての貫禄も、次第に上がってきました。

その年の秋、紅葉見物をかねて貸元連中で、
甲州の身延山参りをしょうと話が出て、信州の親分株が
四人に子分が一人付き、総勢八人で、無事に身延山の参詣が終わると、
帰りに下部の湯を浴びることになりました。
八人は、崖ふちに立っている大門屋という宿に泊まることにしました。
その宵、与太郎は少し気分が悪いからと言って、狭い部屋をとり
この土地に一人しかいない、あんまを呼びました。

「あんまさん、おめえはこの土地に、昔から居るんだろうね?」
与太郎は肩を揉ませながら、訊きました。
「生まれたときからですよ。あんまり自慢にはなりませんが。」
五十近い盲人は、言いました。
色々と話しをしているうち、あんまが煮え切らないので、
与太郎は、紙入れから一朱銀を出して握らせました。
「こ、こんなに頂いちゃ」と
頭を二、三度下げましたが、あんまは、それから口がほぐれました。
思っていた通り、この宿屋のおかみが、
五年前の雨の晩、下谷で駕籠やにのせた女でした。
市助は、あの時連れて逃げた女と夫婦になっていたのです。
しかし、与太郎はどうも女の気持ちが分かりませんでした。
あんまと話しているうちに、与太郎はあんまに
「夫婦は仲が好いかね?」と、何気なさそうに訊くと
「それが親分、今は亭主が変わっているのですよ。」と
あんまは、揉む手をやめてささやきました。
与太郎はびっくりしてしまいました。
市助は、今は嘉助と名乗っています。
「嘉助さんは、一年前に死にました。
この奥の谷から堕ちてね。夜中に急に家から姿が見えなくなって、
夜が明けて村のものが見つけて、
それは、ひどい死に方だったそうです。」
市助は、死にました。与太郎は茫然となりました。

あんまは、言い続けました。
「今の亭主はね。もっと若い男です。房吉さんといいますが。
嘉助さんが死んだあとにすぐに、入り婿になったのです。
それが、妙なのです。
死ぬ三日前、ここに房吉さんが来ていたのです。
この辺では、房吉さんに殺されたのではないかという噂もありますよ。」
一朱銀の効き目で、あんまは、なんでも低い声で喋りました。
「喜助さんが谷から落ちた晩、
二階に泊まっていたはずの房吉さんの姿はみえなかったそうです。
内儀さんは、前の亭主より今の房吉さんとの仲がずっといいのですよ。」

朝、与太郎は湯小屋に下りていきました。
皆は昨夜遅くまで騒いで疲れたのか、まだ眠っていました。
湯小屋には、一人の男が首までつかっていましたが、与太郎を見ると、
「お早うございます。」と丁寧な挨拶をしました。
痩せて、優しそうな顔をしています。
与太郎は何となく動悸がうちました。
与太郎は、この男が房吉という亭主だろうか、それとも湯治客だろうか、
与太郎は迷っているときに、湯小屋の外で女中の声がしました。
「旦那さん、そこですか?お内儀さんがさがしていますよ。」
「おう」と、
男は湯気の中から返事をしました。
ざぶりと湯を騒がせて彼は上がりました。
亭主の背中が、はっきりと与太郎の眼の正面にうつりました。
首筋の下、五寸ばかりのところから、
黒い刀きずが斜めに、みみずのようにはっていました。
与太郎の眼が恐怖になりました。

下を流れる川の音が、あの晩の雨の音に似ていました。
《私の感想》
~『因果応報』、この言葉が私の心に突き刺しました。
原因によって生じた、結果や報い。
与太郎は、この恐怖は生きている限り続くと、
私は思いました。
松本清張は、社会の底辺、法の外で
生きる人々、無宿ゆえに差別される彼ら。
でも、誰もがそうした身に転落しないとは?言い切れないと私は思いました。~

松本清張
明治四十二年(1909年)平成四年(1992年)
肝臓がんにより、そのエネルギーギッシュな
生涯を閉じた。八十二歳であった。
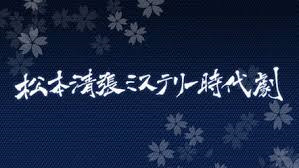
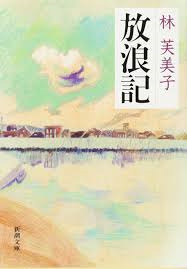
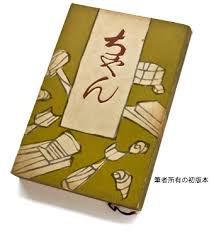
コメント