
~明治三十九年(1906年)に発表されました。~
~【野菊の墓】は、伊藤左千夫の処女小説です。~
~当時伊藤左千夫は数え歳で四十三歳。~
~歌人としてはすでによく知られていたが、遅い小説家デビュ-でした。~
~当時の文壇は、リアリズムや写実的な描写を重視した
自然主義が叫ばれた時期であり
【野菊の墓】も自然主義の影響を、強く受けて書かれています。~

~物語の舞台は、千葉の松戸に近い矢切村。~
~江戸川を挟んだ向かいは、柴又帝釈天。~
~伊藤左千夫の実家も小説と同じ千葉の農家であり、
農家における昔ながらの家族関係やしきたりなどが
リアルに描かれています。~
~上京してからの自身の恋愛経験がもとになっています。~
~【野菊の墓】は、千葉と東京の境にあたる
伊藤左千夫お気に入りの場所、矢切が舞台。
古い家族関係やしきたりに翻弄された若い二人です。~
~処女作【野菊の墓】は、俳句誌「ホトトギス」の明治三十九年
一月号で発表されました。~
~同じ時期に「ホトトギス」に「吾輩は猫である」を連載中だった
夏目漱石に賞賛され、多くの一般読者を獲得しました。~

《あらすじ》
後の月という時分が来ると、どうも思わずにはいられない。
幼いわけとは思うが何分にも忘れることができない。
もう十年余(よ)も過ぎ去った昔のことであるから、
細かい事実は多くは覚えていないけれど、心持ちだけは
今なお昨日(きのう)のごとく、その時の事を考えてると、全く当時の心持ちに立ち返って、涙が留めどなくわくのである。
悲しくもあり楽しくもありという状態で、忘れようと思う事もないではないが、
むしろ繰り返し繰り返し考えては、幻想的の興味をむさぼっている事が多い。
そんなわけからちょっと物に書いておこうかと気になったのである。
舞台は、明治末期の千葉県矢切村です。
政夫の斎藤家は、松戸から二里ばかり下った矢切村。
この界隈で矢切の斎藤といえば誰もが知る旧家でした。
正夫(まさお)の母は久しく病をわずらっていたため、市川の親類の戸村家から
民子が仕事の手伝いやら、母の看病のためにこの屋敷に通って
来ていました。
民子は政夫より二つ年上の十七で、やせぎすですが、丸味のある
顔に白い肌が艶やかで、いつでも活き活きとした少女でした。
二人はいつも一諸に遊んでいて、民子は仕事の合間に、

政夫の部屋までちょかいを出しに来ます。
政夫も遊びに来られるのが楽しく、それが二人の日課のようなものでした。
政夫の母も民子がお気に入りで、娘のように可愛がりました。
もちろんこのとき、政夫も民子も恋愛の気持ちはまったくありませんでした。
母もそれをわかっていて仲良くさせていたのですが、政夫のそばを
離れようとしない民子を見て、二人の関係をうわさする者も
少なくありませんでした。
そこで、母は枕元に二人を呼んで、政夫は十一月からは中学にあがって
寮に入るし、どちらも、もう子供ではないのだから、民子は気安く政夫の
部屋に出入りしてはいけないと意見します。
政夫は不平を言いますが、母はまだ若い二人の行く末を心配していたのです。
「お前たちに何のわけもないことはお母さんも知ってるがネ、人の
口がうるさいから、ただこれから少し気をつけてというのです。」
このことがきっかけで、民子は急によそよそしくなりました。
ある夕方、政夫が母に頼まれて畑で茄子を採っていると、
母から言いつかったと民子も畑にやって来ました。
政夫はこのとき、民子の働く姿を見て美しいと思いました。
二人の恋心は急速にふくらんでいきました。

民子は少し大胆になり、人の目を盗んでは政夫の部屋にやって来ます。
それは、政夫の方が親兄弟に気を遣うぐらいで、政夫がたしなめると、
今度は民子がふさぎ込むといった具合です。
二人は恋する気持ちを持て余していたのです。
それから何日か経った十月十三日、村祭り二日後に控えて、畑仕事の
手が足りなくなると、母は政夫と民子に山の畑の綿を摘んで来るように
言いつけました。
畑までの遠い道すがら、正夫はふと目に留めた道端の野菊の花を
一握りました。
先を歩いていた民子は、政夫がいないことに驚き
すぐさま政夫の方へ駆け戻ると、政夫が持っている野菊に気がつきました。
「まア政夫さんは何をしていたの。わたしびッくりして・・・まアきれいな野菊、
政夫さん、わたしに半分おくれッたら、わたしほんとうに野菊が好き」
「僕ももとから野菊がだい好き。民さんも野菊が好き・・・」
「わたしなんでも野菊の生まれ返りよ。野菊の花を見ると身ぶるい
のでるほど好(この)もしいの。どうしてこんなかと、自分でも思うくらい」
「民さんはそんなに野菊が好き・・・道理でどうやら民さんは野菊の
ような人だ」
民子は分けてやった半分の野菊を顔に押しあててうれしがった。
二人は歩きだす。
「政夫さん・・・わたし野菊のようだってどうしてですか」
「さアどうしてということはないけど、民さんは何がなし野菊のような
風だからさ」
「それで政夫さんは野菊が好きだって・・・」
「僕大好きさ」

綿摘みもそこそこに、山を歩きながら木の実や野花を集めます。
崖を登る民子に手を差し出す政夫、このとき初めて民子に
触れたのでした。

二人は時の経つのも忘れて一日を過ごしてしまい、急いで
十三夜の月が照らす夜道を帰りました。
帰りの遅い二人を待っていた母の心配はひとしおではありませでした。
家族は、皆、政夫と民子の罪を疑いませんし、母も、もう二人を
かばいません。
十一月まで待たず、祭りが終わったらすぐに学校へ行けという
母の命令に、うなずくしかありませんでした。
出発までの四日間、政夫は民子のことをずっと考えていました。
二人とも将来のことを語り合うほど大人でもなく、それがかえって
言葉をとおざけるのでした。
政夫は、出発の前の日に手紙を書いて、自分が去ってから読んで
欲しいと民子に渡しました。

朝からここへはいったきり、何をする気にもならない。
外へ出る気にもならず、本を読む気にもならず、ただ繰り返し
民さんの事ばかり思っている。民さんといっしょにいれば神様に
抱かれて雲にでも乗っているようだ。僕はどうしてこんなになったんだろう。
学問をせねばならない身だから、学校へは行くけれど、心では民さんと
離れたくない。民さんは自分の年の多いのを気にしているらしいが、
僕はそんなこと何とも思わない。僕は民さんの思うとおりになるつもり
ですから、民さんもそう思ってください。明日は早く立ちます。
冬期のお休みには帰ってきて民さんにあうのを楽しみにしてます。
十月六日 政夫
民子様
翌朝、矢切の渡まで民子は政夫を見送りに来ました。
そして、これが二人の生涯の別れとなったのです。
次に政夫が家に帰ったのは、その年の暮れでした。
久しぶりに民子に会えると楽しみにしていたのに、家に着いてみると
民子はいません。
考え込んでいる政夫に奉公人のお増が来て、民子は、政夫が戻る前の日
に市川に帰ったと教えます。
お増が言うには政夫が去ってからの民子は泣いてばかりで、政夫の
兄嫁には何かといじめられ、政夫が戻って来る前に実家に帰されてしまったと
いうことでした。
事情を知った政夫は、民子のさびしさとやるせなさを思い涙します。
年明け早々に学校に戻った政夫ですが、民子のいない家には帰る気が
しません。
その年は夏休みも帰らず、母からの催促で大晦日になってようやく
帰省しました。
家に帰った政夫に母は民子が嫁に行ったことを告げます。
不思議なことに、政夫の心は全く揺れませんでした。

政夫には、自分がそうであるように、民子がまだ自分を思っていてくれて
いると確信があったのです。
それから半年たった六月、政夫に「スグカエレ」という電報が届きます。
急いで帰ると、待っていた母は泣きながら政夫に許しを乞いました。
「政夫、堪忍してくれ・・・・民子は死んでしまった。・・・・
私がころしたようなものだ・・・・」
「そりゃいつです。どうして民さんは死んだんです。」
驚いた政夫が問いただすと、泣き崩れる母に変わって
兄嫁がことの次第をはなしました。
民子は、戸村家の誰もが望んだ縁談を、頑固に断り続けていました。
そこで政男の母が民子に、政夫と一諸にさせる気はないと引導を渡す
ように論したところ、民子はようやく嫁に行ったのでした。
しばらくして子供ができましたが、半年で流産してしまいそのまま回復
できずに民子は逝ってしまったのです。
責任を感じて気も狂わんばかりの母を、政夫は涙をこらえて慰めました。
翌朝早く、政夫が戸村家を訪れると一家で政夫を待っていました。
政夫はそのまま皆と墓に向かい、真新しい民子の墓に花を供えます。
あたりを見渡すと、不思議なことに民子が大好きだった野菊が繁って
いるのでした。

帰ろうとする政夫を民子の母は、「どうか、民子のいまわの話を聞いて
欲しい」とひきとめます。
奥座敷に集まると、民子の祖母が話し始めました。
民子が亡くなったのは、政夫が電報を受け取る三日前、六月十九日でした。
その前日、民子は苦しむそぶりもなく、笑顔さえ見せていました。
駆けつけた政夫の母に暇乞い(いとまご)をし
「自分は死ぬのが本望です。死ねばそれでいいのです。」と言うと、
それが最期のことばになりました。
そして翌日の明け方に息をひきとったのです。
「それから政夫さん、こういうわけです・・・夜が明けてから、枕を直させます時、
あれの母が見つけました。民子は左の手に紅絹(もみ)の切れに包んだ
小さな物を握ってその手を胸へ乗せているのです。それで家(うち)じゅうの人が
皆集まって、これをどうしょうかと相談しましたが、かわいそうなような気持ちも
するけれど、見ずにおくのも気にかかる、とにかく開いて見るよいと、あれの父が言い出しまして、皆のいる中であけました。それが政さんあなたの写真とあなたのお手紙でありまして・・・」
戸村家の誰もが、民子の情の深さを知り、無理に嫁に出してしまった自分たちの
無慈悲さを、深く悔いていました。
民子は余儀なき結婚をしてついに世を去り、僕は余儀なき結婚をして
長らえている。民子は僕の写真と僕の手紙とを胸に離さずに持っていよう。
幽明はるく隔つとも僕の心は一日も民子の上を去らぬ

《私の感想》
~若い時【野菊の墓】を読んだ時と、年を重ねて今読んだのでは~
感動の仕方がぜんぜん違いました。~
~この作品は千葉県矢切村が舞台。~
~素朴な農村で、自然な農村の風景、目に浮かんできます。~
~若い二人の恋、大人たちに翻弄されてしまう、余りにも純粋すぎてしまう恋~
~私は、強く胸を打たれてしまいました。~
~でも、哀しさはありますがその中に哀愁のような切ない思いもあります。~
~民子が大好きな野菊を、墓一面にに植えた政夫。~
~【野菊の墓】は、哀しい場面が多すぎますが、
その分、私の心も洗われていくようでした。~

伊藤 左千夫(1864~1913)
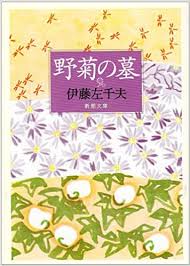
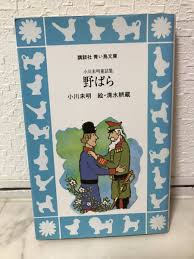
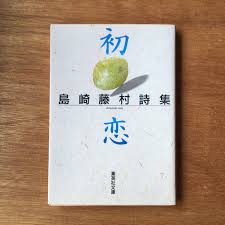
コメント