
下町の庶民を「家族」いう視点からとらえた小説に、
【かあちゃん】【あんちゃん】【ちゃん】
(昭和三十三年二月「週刊朝日別冊」)の三編があります。~
~【ちゃん】は、職人世界を生き生きと描き出した作品です。~
《あらすじ》
重吉は、『五桐火鉢』の桐の胴まわりに、
うるしと金銀で桐の葉と花の蒔絵をほどこした
腕の確かな職人です。
手間がかかる上、長持ちをしすぎる、
かっては珍重品でした。
が、流行の移り変わりで注文も減り出しました。
あげくに給金も少なくなってしまいました。

実入りも減る一方とあっては、飲まずにいられなくなりました。
酔ってクダを巻きます。
「おれは腕いっぱいの仕事をする、まっとうな職人なら誰だってそうだろう、
身についた能の、高い低いはしょうがねえ、けれども低かろうと、
おらあ、それだけを守り本尊にしてやって来た。」
重吉のクダは、意地、人間の誇り、ギリギリの自己主張でありました。
妻のお直と、四人の子供に貧乏暮らしを強いざるを得ませんでした。、
勘定日には酒を飲んで、夜中にくだをまき長屋に戻って来ます。

それ以外の日は、素直でやさしい父親です。
そのことを、長屋の住人は分かっており、暖かい眼で見守ってます。
何より、家族皆が、理解してます。
折角働いた給金なのに、飲んだくれ、お金を使いはたして長屋に帰って来ます。
勘定日の夜、長屋に重吉が帰って来たとき、入り口の戸の前でくだを巻くときのセリフです。
(「銭なんかない、よ」と、
重吉がひと言ずつ、ゆっくりと言う、「みんな遣っちまった、よ、みんな飲んじまった、よ」)
この読点「、」が【ちゃん】を、引き立てています。
重吉の酔っ払って、喋る、もったりした言葉の呼吸が見事に伝わってきます。

戸口の前で家に入りにくいため、くだをまくので
長男の良吉、かみさんのお直が父親を家にいれるのでした。
それでも、だめな時は、
お芳が「たん」父親のことです。「へんなって言ってるでしょ、へんな、たん。」
そう言って、何とか家に父親を家にいれるのでした。
また、金のない父親に、せがれの少年の良吉が
自分で稼いだお金で、飯屋に連れて行き、酒をおごるシーンは、
私は、良吉の男としてのやさしさ、
父親への感謝の思い{いいなぁ~}としみじみ思いました。
「ちゃんは、酒だ、肴はなんにする。」
そこには、息子が自分の父親におごると言う、誇らしさのようなものが感じます。
父親も戸惑いながらも、嬉しさを覚え、お酒を飲み始めます。

こうした、さり気ない日常のシーンがふんだんに盛り込まれています。
そして、ラストは父親が言います。
「おめえたちは、みんな、ばかだ。」
すると子供たちは、
「そうさ、みんな、ちゃんの子供だもの。」
要所、要所に登場する、末子のお芳の舌足らずの物の言い方が、
この作品を、などませてくれます。
重吉は、酒場で生き統合した男を家に連れ込み、
その男に長男の良吉が、少ない給金から母や、弟妹に買った、心尽くしの品物を持ち逃げされてしまいます。

重吉は、自分が嫌になり、出て行こうとしたところをお直に見つかります。
「貧乏でも、六人が一諸に住めばいいじゃないか。」と言われて一人、
独立して今、流行りの火鉢と、『五桐火鉢』も作れたらとの思いで
頑張る決心をします。
《私の感想》
~【ちゃん】は、人情物の話です。
懸命に生きる人々の生活を見事に描いてます。
私たちが忘れていた心の通いあった生き方、
そして、私達が忘れていた人間としての生き方を伝えていると思いました。
改めて山本周五郎は、凄い!
と思いました。~

山本周五郎
明治36年6月22日~昭和42年2月14日
山梨県生まれ。常に庶民の視点から人間の普遍的な姿を追い求めた
大衆文学。
時代小説の巨匠。
昭和18年に《日本婦道記》で直木賞に選ばれたが辞退。
戦後は、毎日出版文化賞、文藝春秋読者賞などにも推挙されたが固辞。
生涯にわたり庶民に使えるという文学的姿勢を貫いた。
代表作に『樅ノ木は残った』『青べか物語』『赤ひげ診療譚』
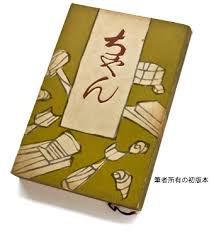
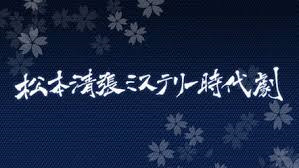
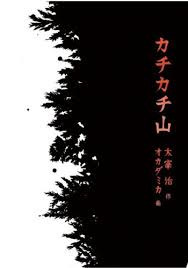
コメント