
~志賀直哉の作品【小僧の神様】は短編小説です.
20ページほどで文章も、読みやすく簡潔でとても面白いです。~

~物語は、寿司を食べてみたいと願う小僧と、彼に寿司をご馳走をしてあげたいと
思う若い貴族議員Aのお話です。~
~【小僧の神様】ですが、若い貴族議員Aが主人公のお話です~。
《あらすじ》
仙吉は、神田にある秤屋の店に奉公している小僧でした。
彼は、番頭たちが話していた旨い鮨屋やの話を聞き、いつか
自分もその店に行けるような身分になりたいものだと思っていました。
それから二・三日した暮れのこと、八銭の電車賃を渡されて使いに出ました。
帰りは歩くことがよくあるので、四銭が懐ではカチャカチャと鳴っています。
「四銭あれば一つは食えるが、一つ下さいとは言えないし・・・・・」
仙吉は諦めながら、店の前を通りすぎました。
しかし、用事を済ませた仙吉は何かしら惹かれる気持ちで来た道を
引き返し、寿司屋の方へ曲がろうとしました。
その時、屋台ですが例の名前と同じ鮨屋の暖簾をかけています。

屋台には若い貴族議員のAがきていました。
そこへ仙吉が忙しく辺りを見回し、
鮨屋の主人に「海苔巻はありませんか。」と、言いますと、
「ああ今日は出来ないよ。」と、太った鮨屋の主人はジロジロと小僧を見て言いました。
仙吉は少し思い切った調子で、三つ並んでいる鮪の鮨の一つを摘まみました。
主人が「一つ六銭だよ。」と言われ、仙吉は黙ってその鮨を又台の上へ置きました。
仙吉は、一寸動けなくなったが直ぐ勇気をふるい起して暖簾の外に出ました。
その様子を若い貴族議員Aが見ていたが、どうしてもご馳走してあげる勇気が出ず
その後も、胸がざわめいている感じで仙吉のことが妙に心に引かかっていました。
貴族議員Aには、幼稚園に通う子供がいました。
その成長ぶりを数字の上で知りたいと、秤屋を買いに行きました。
貴族議員Aが向かった先は、偶然にも仙吉が奉公している秤屋だったのです。

貴族議員Aは直ぐに、仙吉のことを鮨屋で見かけた小僧だと分かりました。
貴族議員Aはそこで、こじんまりした秤を購入し、
仙吉は秤を乗せた小さな手車をひいて、貴族議員Aの後をついて行きました。
貴族委員Aは、仙吉に
「お前も、ご苦労。お前には、何かご馳走ご馳走してあげたいから、その辺まで一諸においで。」と
笑いながら言いました。
随分歩いて貴族議員Aは、横丁の小さい鮨屋の前で立ち止まりました。
貴族議員Aは、鮨屋にお勘定だけ済ませて、
仙吉に「私は、先へ帰るから十分食べておくれ。」
こう言って逃げるように急ぎ足で電車の方に行ってしまいました。

仙吉は、飢え切った痩せ犬が不時の食にありついたかのように、
がつがつと、たちまち三人前の鮨を平らげてしまいました。
ほかに客がなく、若い品の、いいかみさんがわざと障子を閉め切って行ってくれたので
仙吉は見得も何もなく、食いたいようにしてたらふく食うことが出来ました。
貴族議員Aは、変に寂しい気がしました。
先の日の小僧の気の毒な様子を見て、心から同情し
今日は偶然の機会からご馳走することが出来たのに・・・・・
何でだろう。
この変に寂しい、いやな気持は。
丁度それは人知れず悪いことをした後の気持ちに、にかよっている。
一方、仙吉は、貴族議員Aが自分の食べたいと思っていた鮨を
知っていたことなどから、貴族議員Aを神様かそうでなければ仙人かもしれない。
もしかしてお稲荷様かも知れないと思うようになりました。

そして、仙吉は悲しい時、苦しい時必ず貴族議員Aを思いました。
仙吉は、いつか又貴族議員Aが思わぬ恵みを持って、自分の前に
現れて来ることを信じていました。

《私の感想》
~貴族議員Aが良いことをして、淋しくなる気持ちは、私も分かります。
心から、その人のためもあるかも知れませんが、
ひょんなことから、どこかで自分を良く見せたいと思う気持ちとかが
ぶつかり合って複雑な思いになるのかも知れないと思います。
仙吉の方は、神様、もしくは仙人かも、
もしかして、お稲荷様かもと思い、一生忘れない出来事として
辛い時も頑張っていこうと思うのですから、人生は、分からないものです。~

作品解説
【小僧の神様】と、志賀直哉がよばれる所以となった短編作品【小僧の神様】は、
大正九年(1920年)一月に雑誌「白樺」で初表された。
物語はとても簡潔で、お金がなく鮨が食べられない小僧を偶然見かけた貴族議員が、
身分を隠してその小僧にご馳走するというスト-リ-。
直哉は、予期せぬ幸運に神の存在を感じる小僧と、気まぐれから出た善行に居心地が
悪く、自己嫌悪すら感じてしまう貴族議員を好対照的に描いて、善行と偽善の意味を
読者に問いかけた。

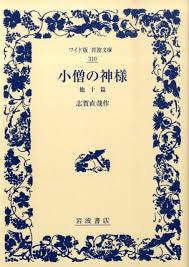
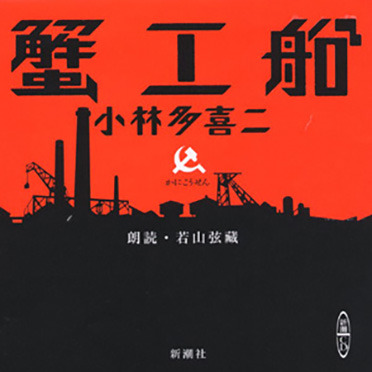
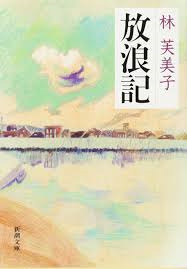
コメント