
明治十九年、父一禎と母かつの長男として、
現在の岩手県盛岡市に生まれる。
戸籍上は十九年だが、実際の生年はその前年ともいわれる。
本名は一(はじめ)
幼少時は、神童の名をほしいままにする。
盛岡高等小学校を経て、明治三十一年(1898年)、
岩手県盛岡尋常中学校(現在の盛岡第一高等学校)入学。
この頃から、中学の上級生で後に国語学者となる
金田一京助らの影響を受けて、「明星」を愛読するようになる。
明治三十五年、盛岡中学校を退学。

与謝野鉄幹の興した新詩社(詩歌結社)の同人となり、
啄木の筆名で詩編を「明星」に発表する。
名付け親は与謝野鉄幹だった。
明治三十八年に処女詩集『あこがれ』を刊行。
その年、堀合節子と結婚し、翌年渋民尋常高等小学校に
代用教員として勤務する。

しかし、かって父の起こした不祥事に起因する、渋民村の人々の迫害と
一家の貧乏に耐えかね、明治四十年、活路を見いだすため
北海道に渡り、新聞記者などをしながら道内各地を、転々とする。
明治四十一年、単身上京し金田一京助の援助をうけ、
彼と同宿しながら創作に専念。
同じ年、森鴎外の知遇を得、観潮桜歌会に出席する。
それに刺激されたのか、数日のうちに、二百首以上の短歌を書き上げた。

明治四十三年第一歌集【一握りの砂】刊行。
明治四十四に慢性腹膜炎が悪化し手術、退院したものの
明治四十五年、肺結核を、併発し、死去。
その二ヵ月後に第二歌集「悲しき玩具」が出版された。

石川啄木【ひと握の砂】
しつとりと
なみだを吸(す)へる砂(すな)の玉(たま)
なみだは重(おも)きものにしあるかな

はたらけど
はたらけど猶(なほ)わが生活楽(くらしらく)にならざり
ぢつと
手(て)を見(み)る
人(ひと)といふ人(ひと)のこころに
一人(ひとり)づつ囚人(しうじん)がいて
うめくかなしさ
いたく錆(さ)びしピストル出(い)でぬ
砂山(すなやま)の
砂(すな)を指(ゆび)もて堀(ほ)りてありしに

《私の感想》
~石川啄木は明治45年(1912)に26歳の若さで亡くなりました。~
~啄木の生活はいつも困窮していました。
病気がちでもあり、楽な生活をしたことはなかったと思います。
でも、夢をもって、もがき続けたと思います~。
~文学で身を立てたいという強い意志を持っていました。
小説では認められませんでした。
そんな中での、貧困による悲哀や絶望、望郷の念を思う場は短歌でした。~
~啄木は自分の短歌を、悲しき玩具だと言ったそうです。
短歌を詠(よ)んでいる時が心やすらぐ時だったのかもしれません~。

~私は天性の詩歌人だと思いました。~

石川啄木
(1886~1912)
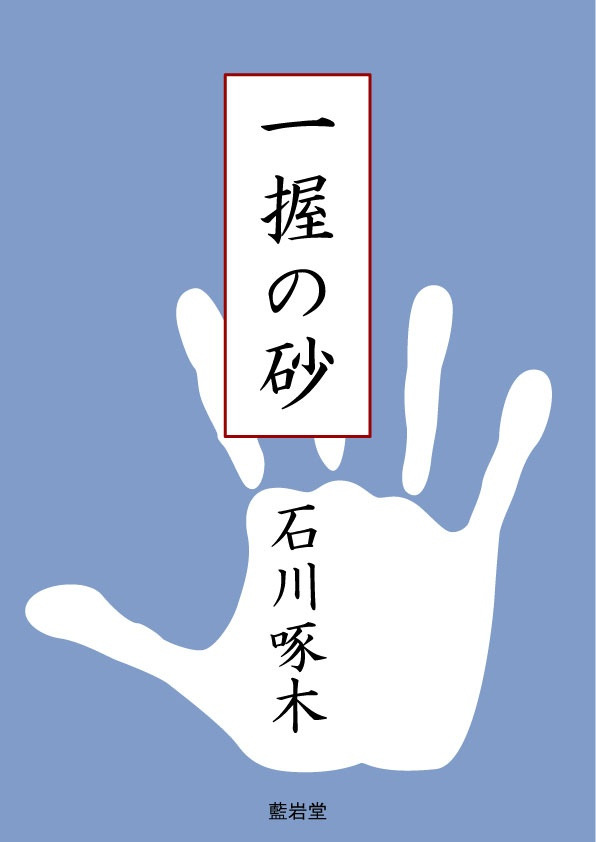
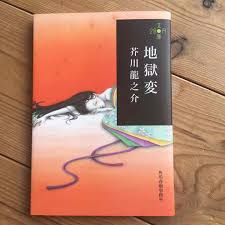
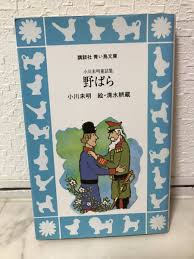
コメント