今日、八月十五日は、戦後七十六年の終戦の日。
戦争を考えて、平和を思うこの日。
【播州平野】を、読んで今の幸せを実感しました。

《あらすじ》
一九四五年八月十五日の日暮れ、
妻の小枝(さえ)が、古びた時計柱の懸(か)っている
茶の間の上に、大家内の夕飯の皿をならべながら、
「父さん、どうしましょう」
ときいた。
「電気、今夜はもういいんじゃないかしら、明るくしても―」
茶の間のその縁側からは、南に遠く安達太郎(あだたら)
連山が見えていた。
その日は、午後じゅうだまって煙草をふかしながら
山ばかり眺めていた行雄(ゆきお)が
「さあ・・・・・・」
持ち前の決して急がない動作で振り向いた。
そして、やや暫く、小枝の顔をじっと見ていたが、
「もうすこしこのまんまにして置いた方が安全じゃないか」
と云った。
「―そうかもしれないわね」
小枝は従順、そのまま皿を並べつづけた。
台の端に四つになる甥の健吉(けんきち)を坐らせ、早めのご飯を
たべさせていたひろ子は、この半分息をひそめていたような、
驚愕(きょうがく)から恢復(かいふく)しきれずにいる弟夫婦の
門答を、自分の気持にも通じるところのあるものとしてきいた。
作家であるひろ子は、十二年前に重吉(じゅうきち)と結婚をしました。
しかし、東京でのわずか二ヵ月の新婚生活の後、
重吉は思想犯として逮捕され、巣鴨刑務所に収監されてしまったのです。
それからの十二年間、ひろこと重吉は、手紙のやりとりと、
限られた面会だけで夫婦のつながりを維持してきました。
ひろ子が書いた手紙の数は千通を超えていました。
ある日のこと、ひろ子が重吉に送った手紙が、付箋つきで
戻ってきました。
その付箋には、重吉が網走刑務所に送られたと記されていました。
そこで、ひろ子は、東京の家を引き払い、いったん福島に住む
弟夫婦の家に身を寄せました。
そこで津軽海峡を渡る連絡船の切符が買えるまで、待つことにしたのです。
そして、八月十五日、正午に重大な放送があるから必ず聴くように、
と予告されていたため、ひろ子は弟たちと一諸にラジオに耳を傾けました。

ラジオから聞こえてくる天皇の声は
「ポツダム宣言を受諾せざるをえず」
と伝え、それにより日本の無条件降伏を知ったのです。
戦争が終わってからの、子供たちの遊びぶりがすっかり変わった。
警報が鳴り出すと、どんな親友でも、又どんなに面白いことをしている
最中でも、子供やは一散に家へ駆け帰ってしまった。
伸一は、それを悲しがって泣き出したことがあった。
少年たちが、心も体もとろかして、集まったり散らばたり、穴を
切り開いたタンクの胴に入って大海用上の舟を想像したりして
さわいでる光景は、ひろ子を感動させた。平和とは、人間の生活に
とって何であるか。それを深く感動させた。
ある日、ひろ子が居候している弟夫婦の家に、
一通の速達郵便が届けられました。
それは重吉の母からの手紙でした。
広島に入隊した重吉の弟、直次(なおじ)が、八月六日の爆擊を受け、
行方不明になっているというのです。
「絶望としか思えませんが、せめては死に場所なり知りたくて―」
手紙にはそう書かれていました。
ひろ子は、網走行きをいったんあきらめ、岩国近くの重吉の田舎に
向かうことにしました。
そこには、重吉の母と、直次の妻、つや子が暮らしています。
ひろ子は、列車を乗り継ぎ、大変な苦労をしながら、
下関(しものせき)方面を目指します。
車窓から見える景色は、廃墟ばかり。
その土地ならではの趣も、生活感も見あたりませんでした。
急行列者が止まる市街地は、熱海を除いて
ほとんどが廃墟となっておりました。
やっとの思いで重吉の田舎にたどり着き、
重吉の母とつや子に対面したひろ子は、二人の様子に胸の苦しさを覚えます。
九月の半ば、親戚の縫子(ぬいこ)」が訪ねてきました。
縫子とひろ子は気が合い、ひろ子が東京にいた頃は
一年半も一諸に暮らしたこともあります。
ひろ子が来ていることは知りませんでしたが、
昨夜(ゆうべ)見た夢が気になり、一里半離れた田原から歩いてきました。
縫子は、夢の中で
「直次がミヨシというところにいる」
という話を聞いたというのです。
そこでミヨシという地名を捜したところ、
広島から芸備線で二時間ほど離れた場所にそれがあったのです。
ひろ子と縫子は、三次(みよし)にいくことを決めます。
しかしその矢先、大雨が降り続いて、河川が氾濫。
ひろ子と縫子は三次に行くどころか、家の修繕に追われることになったのです。
水害に見舞われた四日目、ようやく落ち着いててくると、
疲れ果てた家の空気にいたたまれなくなっていたひろ子は、
三次行きの目処が立つまで縫子の家に行くことにしました。
ひろ子が田原の縫子の家ですごしている間に、
「近日中に治安維持法は徹廃され、処罰中の思想犯はすべて釈放される」
という報道がなされました。
そして、十月六日付けの新聞記事に、思想犯釈放の予告と、
釈放される人物の氏名が示されていました。
いてもたってもいられなくなったひろ子は、
早々に東京に向けて旅立ちました。

しかし水害の影響で道のりは厳しく、やっと姫路に着いたと思えば
列車は止まってしまいます。
破れ屋のような宿屋に泊まりながら、復旧を待ちますが
なかなか復旧の目処がたちません。
一歩一歩、東京に向かう道のりは本当にゆっくりしたものでした。
けれどそのことはかえって、ひろ子の気持ちを落ち着かせたのです。
網走からは、重吉も東京に向かっているはず。
十月十一日、ひろ子はようやく姫路を出ます。
列車が不通になっているところでは、トラックや荷馬車を利用せざるを得ません。
荷馬車の荷台に揺られながら加古川(かこがわ)から明石を目指す途中、
国道の両側には播州平野が、すき通るような秋の西日に照らされ
のびやかに広がっていました。
播州平野には、関東平野や那須野(なすの)あたりの原野とは違
う独特の趣がありました。
耕された畑の土は柔らかく軽そうで、遠くに望む山々の嶺がどこか軽々と
空にそびえるその景色は調和しています。
ひろ子は、荷馬車のゆっくりした歩みにも、一歩一歩着実に重吉に向かっている
快さを感じていました。
そしてひろ子の心に満ち溢れる様々の思いに節を合わせた。

この国道を、こうして運ばれることは、一生のうちに、もう二度とはないことであろう。
今すぎてゆく小さな町の生垣。赤石の松林の彼方に赤錆てたっている
大工場の廃墟。
それらをひろ子は消されない感銘をもって眺めた。
日本じゅうが、こうして動きつつある。
ひろ子は痛切にそのことを感じるのであった。
《私の感想》
宮本百合子の自らの戦争体験を、もとにした
【播州平野】
夫、宮本顕治(日本共産党元委員長)が、思想犯として収監されている妻の物語で
終戦日から始まり、夫(重吉)の釈放が伝えられて
妻の(ひろ子)が東京に向かうまでの日々が描かれています。
(ひろ子)のモデルは宮本百合子自身であります。
(重吉)もまた、長い獄中生活から解放された夫の(顕次)がモデルであります。
【播州平野】は、戦前のプロレタリア文学のながれに生まれたものです。
でも、プロレタリア文学的ではなく夫を思う
親の姿や子供を思う親の姿が綴られて深く感動をしました。


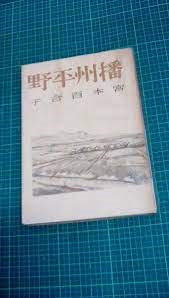
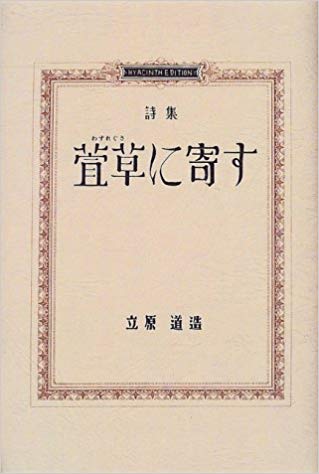
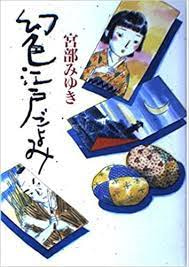
コメント