
《わたしの 読書感想》
井上靖の自伝的小説【しろばんば】は、大正時代初期の頃の伊豆の湯ヶ島の三村が舞台です。
小学校低学年の少年(洪作)が主人公です。
湯ヶ島の三村の中で、洪作は濃厚でかつ温かく複雑な人間関係に包まれながらゆっくりゆっくりと、成長していきます。
少年(洪作)の目線で物語は展開していきます。
洪作は、土蔵でおぬい婆さんと二人で暮らしています。
おぬい婆さんは、曽祖父の妾でありますが、洪作にとって、おぬい婆さんとの共同生活はごくあたりまえのこととして受けとめています。

おぬい婆さんの家の近くには、(上の家)母親の実家、曾祖母、祖父母、母親の妹弟達が住んでいます。
父親の実の兄は洪作の学校の校長であり隣の部落に住んでいます。洪作の父親は軍医で師団が豊橋にあるので、両親は豊橋に住んでいます。
両親や弟妹から一人離れて、のどかな村で暮らす少年の物語です。

洪作の思慕の対象は両親ではなくおぬい婆さんなのです。
【しろばんば】は、子ども達の遊びの世界からなっています。洪作の周囲には村の子ども達の遊び仲間がいます。洪作は、いつも彼らと行動を共にしています。
洪作達は、一年坊主から六年生まで同じ部落に暮らす全ての子ども達からなっています。子ども達は学校が始まる一時間以上も前に村に集合し、そこから集団で学校に
向かいます。ただ、歩くのではなく遊びながら歩きます。子ども達は、部落ごとに集団を作って登校します。
半里も、一理も離れた部落の子ども達が、それぞれやっぱし一塊になって新道や旧道に姿を見せます。途中で目があったりすると、互いにねめまわししながら、時には石をぶつけたり
します。子ども達にとって集団そのものが一つの群れのようなもので、他の集団は敵になります。子ども達の集団には当然年齢に応じて、支配服従関係が出来ます。
学校の中では、部落間の敵対意識は解消されます学校は子ども達にとって怖い存在となります。教師は訳もなく頭を小突いたり、殴ったりするのです。
耳を引っ張られて廊下に立たされたことも、洪作にはありました。いまだに、原因が最後まで分かりませんでした。
そんな、訳ですから子どもが悪さをした時、大人達は(学校の先生に言いつけるぞ)と、言われると子ども達は震えあがったものでした。

【しろばんば】を、面白くさせているのはおぬい婆さんの存在です。好き、嫌いが激しく人とぶつかるのはしょっちゅうです。
おぬい婆さんは、洪作に対する愛情も異常なほどです。洪作をとても誇りにも思っています
印象が強いのは、洪作が通知簿で二番になった時でした。
「こんな馬鹿なことに承知するもんかい。人を馬鹿にしとる。」「ちょくら学校に行ってくべえ。」
洪作はおぬい婆さんの足にしがみつきました。学校へ行かれてはたまらぬと思いました。
「ふざけた真似をするにもほどがある。坊がおとなしいと思って、坊をさしおいて光一を一番にしおった!おおかた泥棒でもして金まわりがよくなった木こりの
子ずら。坊、ここにいな。ばあちゃんが学校へ行って文句いってきてやる。」この場面でも、おぬい婆さんの洪作に対する気持ちが手に取るように分かります。

(上の家)洪作の実家、さき子の存在も大きいです。
母の妹さき子が恋仲となった同僚教師との間にできた子を、育てながら産後の養生をしています。

洪作が慕情を抱く姉のような存在である(さき子)さき子は、母の妹ですが、勝手に恋仲になり子どもを産み自分の心に素直に生きるさき子を田舎にはそぐわず村でも批判を受けています。
洪作は母の姿をさき子に求め幼い恋をしていましたが、さき子は同僚に恋をし子どもを産みました。
洪作には、大変ショックでした。そんな、さき子でしたが出産後、当時不治の病と言われた肺病を患ってしまいました。
「上の家」の二階で誰とも会わず養生をしていましたが、洪作は階下に誰の姿も見えないので二階の突き当りの部屋に入って行きました。
「誰。」と、言うさき子の声が聞こえてきました。「洪ちゃ。」と、洪作が答えると「わからずやね。お帰りなさいと言っているのに、どうして帰らないの。」
それは𠮟責の口調ではありましたが、どこかに弱々しいものが感じられました。洪作は、唐紙に手をかけ開けようとしたが唐紙は動きませんでした。
「開けて、開けて!」「だめよ。」
次の瞬間ぱっと細めに唐紙が開いたかと思うと、さき子の白い腕が一本とびだしてきて、洪作の頭をぽんと軽く叩くと、直ぐまた引っ込んで、唐紙はふたたび閉められ
てしまいました。洪作は四枚の唐紙を開けようと思いましたが、内側でどのような押え方をしているのか、今度はどこも、かたとも動きませんでした。
「帰りなさい。」今度のさき子の声は有無を言わせぬ厳しい口調をもっていました。

深夜さき子は、二台の人力車で母のたねと発って行きました。西海岸の夫の任地へ行き、そこで夫と赤ちゃんと一諸に暮らすことになりました。
さき子が、湯ヶ島にいた時よりも病状が悪くなったとかで、上の家の者たちは、入れ替わり立ち代りさき子のところへ出かけて行きました。
突然、さき子の訃報が上の家に届きました。さき子が、もうこの世にいないということを信じることが出来ませんでした。
皆が泣きだし、洪作は、はじめてさき子姉ちゃんは本当に死んだのだと思いました。
部落の子ども達二十人ほどで、さき子の葬式が行われる日、天城の峠へトンネルを見るために出かけました。
自分達の教師であったさき子の死を悼み、さき子から教わった幾つかの唱歌を、誰からともなく歌いだしました。

はじめて天城の斜面に初秋の風が伝わりました。雑木の葉裏がときおり銀色に輝いて、それによって、風の通道が分かりました。
【しろばんば】は、過ぎ去った少女時代を思い出しノスタルジックになりました。大人になった自分は、過ぎ去ってしまった少女時代が懐かしく思いました。
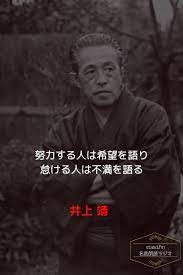
井上靖
1907年(明治40年)5月6日現在の北海道旭川市で長男として生まれます。1913年(大正2年)6歳のとき父母のもとから郷里湯ヶ島に預けられ、戸籍上の祖母にあたる(かの)に育てられることになります。以後、(かの)が死去する1920年(大正9年)まで2人は一諸に暮らすことになります。
【しろばんば】に登場する(おぬい婆さん)は、(かの)をモデルとしており、また(洪作)は、作者の小学校時代をもとに描いているといっていいと思います。
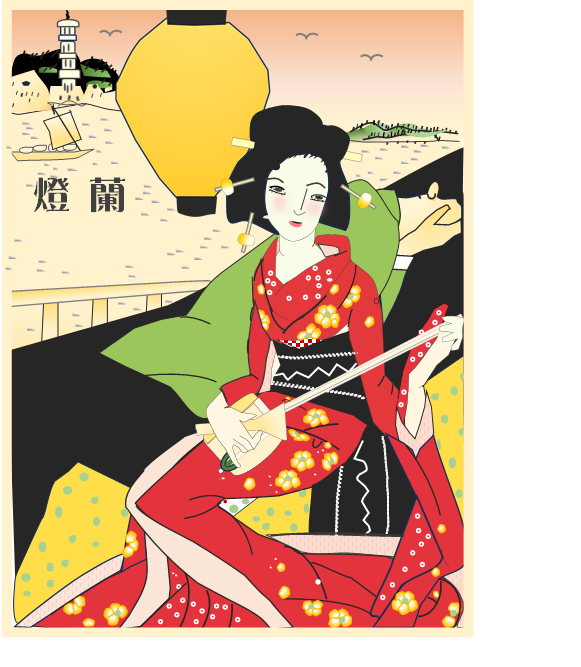
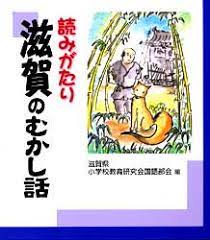
コメント