
~学生の頃、中原中也の詩を読み天才的な才能を持った人だと思ったこと、生い立ちを読んで衝撃的と言うか
驚いたことたことなど、
今改めて読んでみて学生の頃とはまた、違う意味で生きざまが凄いと思ってしまいました。~
~詩が独創的で、常に生きるとはどんなものかを問うような気がじてきました。~
《簡単に中原中也の紹介》
中原中也は、明治四十年(1907年)4月29日父・謙助と、母・フクの長男として、
現在の山口県山口市湯田温泉に生まれました。
父は軍医(後に病院の院長を務める)

長男だった中也は、厳格なしつけを受け、
母は武術で、父は陸軍式のしつけで教育を受けました。
小学生の頃は成績優秀で、周囲からは「神童」と呼ばれていました。
大正四年(1915年)、3歳下の弟・亜郎(つぐろう)が脳膜炎で亡くなりました。
中也が詩を作り始めたのは、弟の死を「自身の詩作の出発」と語っています。
中也は勉学には身が入らず、中学3年を落第(中学校は4年かかって終了)
京都立命館中学を18歳で卒業した中也は、下宿先で同棲していた女優の長谷川泰子と知り合い
ダダイストの詩を作り、1925年東京に出て、小林英雄に泰子を取られ詩作に没頭します。

京都で、東京出身の詩人・富永太郎と知り合ったことが、中也の人生に大きく影響します。
富永 栄太郎(中也が18歳の時に病死)師と、
仰いだフランス詩への興味を抱かせてくれた作家人生の師匠。
大学は浪人しながらも、なんとか日本大学予科文科に入学しますが直ぐに退学。
その後、現在の東京外語大学の仏語部に入学しなんとか卒業しました。
雑誌への投稿したり、歌集を発刊したり、同人誌に寄稿したり、
創作の方には随分力を入れていました。
商業的な発行物にこぎつけたのは、1933年中也26歳の時翻訳が初めてでした。
翻訳したものを出版し、翻訳者としても名を残すことができました。
中学の頃、両親に内緒で短歌会(末黒の会)に出入りし、
大人も出入りしているので、酒もタバコも覚えました。

中原中也は、酒乱であったとも言われてます。
(白痴群)という同人雑誌を出しており、その仲間との飲み会帰りに
民家の外灯を叩き壊して警察沙汰になったこともあったそうです。
中也は、母親からの仕送りを頼りにしていて、生活をしていました
上野孝子と結婚して、中原中也29歳の時に
長男(文也)2歳にして病死で亡くなってしまいます。
中也は遺体のそばを離れることが出来ず、泣きはらし精神が不安定になってしまいます。
その結果、幻聴や幼児退行な言動が出始めました。
わが子との死別から1年経たずして痛風になったり、視力障害を訴えたり、歩行困難になったりと、
入院しますが、結核性脳膜炎で30歳でこの世を去ってしまいます。

作品は「山羊の歌」を出版し、
「在りし日の歌」これは死の翌年に刊行されました。
350篇ぐらいの詩を残しました。

わが半生
私は随分苦労して来た。
それがどうした苦労であつたか、
語らうなぞとはつゆさへ思はぬ。
またその苦労が果して価値の
あつたものかなかつたものか、
そんなことなぞ考えてもみぬ。
とにかく私は苦労してきた。
苦労してきたことであつた!
そして、今、此処、机の前の、
自分を見出すばつかりだ。
じつと手を出し眺めるほどの
ことしか私は出来ないのだ。
外では今宵、木の葉がそよぐ。
はるかな気持ちの、春の宵だ。
そして私は、静かに死ねる。
座ったまんまで、死んでゆくのだ。

《私の感想》
~中原家は、男だけの6人兄弟です。
長男ということで、両親から医者になることを期待されていました。
現代なら問題になるような厳しいしつけ、
両親からの締め付けられて育ったことの反動が
中学生になり多感な時期に爆発してしまったと思います。
そして、大切な人を次から次へと亡くなってしまいます。
30歳でこの世を去ってしまう波乱すぎる人生。
【わが半生】も生きることの
苦しみ、悩み、悲しみが凝縮されているように思います。~
~30歳までの死にいたるまで、中原中也は常に生きるとはを、
詩にすべてを独自の世界で現していたと思います。~

中原中也
(1907~1937)
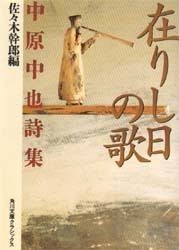
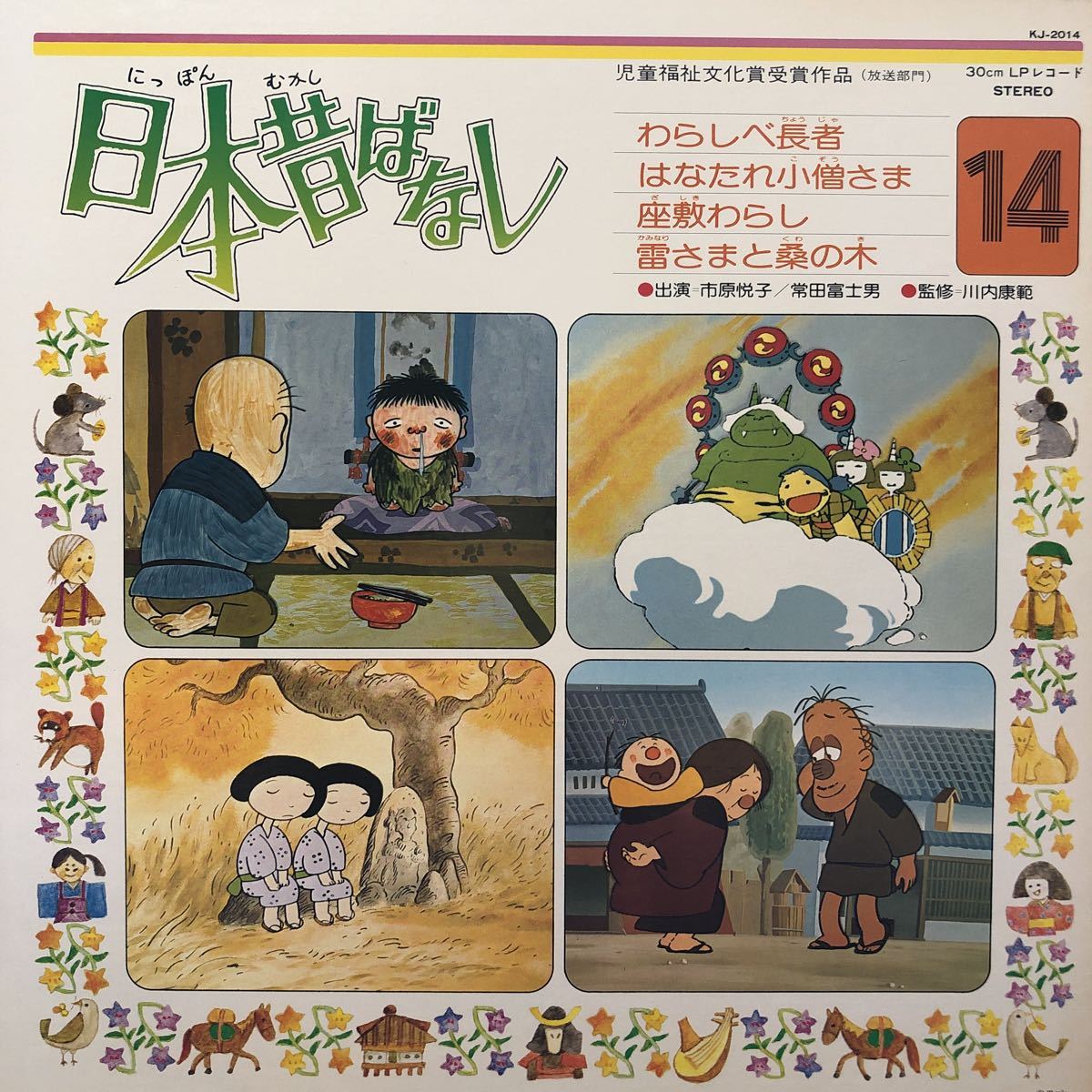
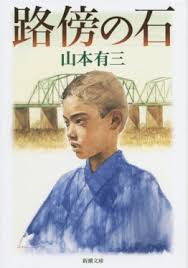
コメント