

《私の想い》
~戦後間もない(昭和24年)の日本。~
~【青い山脈】は、学園ものの小説ですが、
当時は日本国憲法施行されたばかりの頃です~。
~当時の封建的な考え方と新しい考え方がぶつかりあいます。~
~この物語の舞台は東北地方の女子高校生。~
~封建的な考え方の東北地方の田舎町。~
~新任教師の島崎雪子の奮闘する女性教師を描いてます。~
~教え子の寺沢新子からの偽のラブレタ-について
相談を受けます。~
~この偽のラブレタ-が東北地方の田舎町を、
巻き込む事件に発展していきます。~
~この頃は男女交際などは、まかり通らず
~まだまだ、根強い封建制度に縛られていた人々です。~
~男女交際は、不純だと思われていた時代。~
今では想像も出来ない考え方。
~【青い山脈】は、
新任教師、島崎雪子の
若く芯の通った理想をもった考え方に
あらたに、夢をもらいました。~

《あらすじ》
六月の、ある晴れた日曜日の午前であった。
駅前通りの丸十商店の店の中では、
息子の六助が、往来に背中を向け、
二つ並べたイスの上にふんぞりかえって、
ドイツ語の教科書を音読していた。
恐ろしくふきげんそうな様子である。
この九十商店に、海光(かいこう)女学校五年生の
寺沢新子(てらざわしんこ)が、卵を売るために九十商店に入りました。


店番をしていたのは、金谷六助(かなやろくすけ)
高等学校に通っています。
六助の両親は、昨日から留守で六助は空腹だたのです。
新子はどうしたものかと迷いますが、年の近い二人は話を
するに打ち解け、結局ご飯を作ってあげることにしました。
ご飯が出来上がると、ちょうどお昼時だったので、
新子は六助と一諸に食事をすることになりました。
新子の天真爛漫なところに好感を持った六助は、
これから新子が占い師のところに行くというので、ついて行くことにします。
二人は大通りの四つ角にある易者のところまで連れだって
歩いて行きました。
そして、偶然出会った二人は、次に会う約束をすることもなく別れました。
しかし、このことが騒動に発展するとは、
このとき二人は知るよしもありませんでした。
ある日、海光女学校の職員室で英語教師の島崎雪子(しまざきゆきこ)が
帰り仕度をしていると、受け持ちの生徒、寺沢新子が入ってきました。
新子は、差出人不明の手紙が届いたといって
胸ポケットから手紙を取り出します。
それは誤字だらけの、幼稚なラブレタ-でした。
新子は以前の学校で男子生徒との交際を疑われて、やむなく
この学校に転校して来たのです。
そのことを知った生徒が自分を試しているのではないかと言います。
雪子はこの手紙をあずかることにして、新子を家に帰すと、
手紙の筆跡と、クラスの作文帳とを丹念に照合し始めました。
紙と似た筆跡の生徒が見つかりました。
それは、ませた、お上さんタイプでクラスの中でも影響力をもっている
松山浅子(まつやまあさこ)でした。
雪子が職員室でボンヤリしていると、
そこへ沼田玉雄(ぬまたたまお)が入ってきました。
沼田は三十二、三歳の青年医師。
この学校の校医です。
沼田に、この事件のあらましを説明して、
明日この問題をクラスで話し合おうと思うのですが、と相談します。
美しい雪子に関心を寄せている沼田は、
「それぁまずいことになりそうだな」と言いながらも、経過報告をして欲しいと言いました。
翌日、雪子はクラスの生徒たちに
「今日は大切な問題を皆さんといっしょに考えることにしたいと思います。」
と切り出しました。

そして
「一体皆さんは恋愛について、どう考えているんですか」
と問いかけます。
一人の生徒が手を挙げて答えました。
「ハイ。昔は恋愛はわるいことに考えられておりましたけれど、
いまはいいことに考えられているんですか?」
「いまは民主主義だからです。」
(そうです、そうです)とそれに賛成する声が二つ三つ聞こえた。
「さあ、そういう形式的な返答では困りますね」
なぜいろいろな物事が変わらなければならないのか、
本質的なことは何一つ分からず民主主義という言葉を、
万能薬のようにふりまわしているのが、
いまの世の中なのだと思った。
ひと通り生徒たちの意見を聞いている途中、
松山浅子が隣の生徒に何かささやいて、
あごで寺沢新子をしゃくってみせるのが目につきました。
雪子はカッとしてしまい、話そうとしていた順序を、飛ばして
松山浅子に問いかけました。
「松山さん、貴女はこのごろ、男の学生の名前で、
寺沢新子さんに手紙を書きましたね。」
凍りついた教室の中、雪子は続けます。
「日本人のこれまでの暮らし方の中で、一番間違っていたことは、
全体のために個人の自由な意志や人格を犠牲にしておったと
いうことです。
学校のためという名目で、下級生や同級生に対して
不当な圧迫干渉を加える。
家のためという考え方で、家族個々の人格を束縛する。
国家のためという名目で、国民をむりやりに一つの型にはめこもうとする。
それもほんとうに、全体のためを考えてやるのならいいんですが、
自分たちの野心や利欲を満たすためにやっていることが多かったのです。」
この出来事は、その日のうちに学校全を体巻き込む事件に発展しました。
生徒たちが学校のことを考えて行動したことを、
雪子に侮辱されたといって校長のもとにおしかけたのです。
校長と教頭は、すぐに生徒たちに釈明するようにと雪子に迫りますが
雪子は謝罪するつもりはないとはねのけます。
その日、新子は、今や事態は自分の手から離れて大きくなっていることに
責任を感じ思い足取りで帰り道を歩いていると偶然、六助が通りかかりました。
ワラにもすがりたい新子は、ことの顛末(てんまつ)を六助に打ち明けます。
すると、そこに往診途中の沼田がやって来ました。
六助は先輩の沼田に新子から聞いた話を伝えると、
沼田は、予想通りだと言って、すぐに学校に向かいました。
新子が帰宅すると、家のまえに松山浅子と七、八人の同級生が群がっていました。
浅子たちは、おもむろに学校のため退学をするようにと新子に迫ります。

新子はくちびるをかみしめてこらえますが、浅子に
「本当はあんなラブレタ-がすきなんでしょう」
と言われると、ついカッとなって浅子の顔を殴ってしまいました。
雪子と生徒たちの対立は新聞にもとりあげられるほど、大きくなっていました。
雪子の進歩的な考え方に理解を示していた沼田は、
自分の家に、
雪子と新子と六助、
六助の友達で、読書家の富永安吉(とみながやすきち)
雪子を慕っている一年生の笹井和子(ささいかずこ)
を、集めて今後の作戦を練ります。
沼田は近いうちに校長たちが、父兄の意見を聞くために
理事会を開くだろうから大いに闘うつもりだと言います。
理事会の日。
父兄と学校側の関係者が集まった中には、
雪子はもちろん、沼田、富永もいました。
校長の理事進行で始まり、
教頭の経過報告が終わったところで、
父兄の一人が問題の手紙を、読んではどうかと提案しました。
年老いた国語の教師、一字一句原文のまま読みます、と
前置きして手紙の朗読を始めました。

「― ああ、ヘンすい、ヘンすい、私のヘン人・新子様
ぼくは心の底から貴女を、ヘン、すておるのです。」
「あっと、岡本先生。そのヘンすい、ヘンすい、というのは英語ですかな?
フランスゴ語ですかな?」国民服を着た、
赤ら顔のデップリ太ったお父さんが質問した。
岡本教師は、ちょつとあわてた様子で斜め後ろの黒板の前にズカズカと
歩いて行って、大きく、(恋)(変)とならべて書いた。
「つまり『恋』と書きべきところを国語力が幼稚でありますため『変』と
間違えて書いておるのであります」
そんな間違いだらけの手紙を読んでも仕方がない
ということになり、
要点だけ報告されたあと、今回の事件について議論が行われました。
古い考えの前に、立ち向かう雪子に沼田たちが加勢しますが、
議論は、最終的に生徒が正しいか、
雪子が正しいかを無記名で投票することになりました。
結果は、十四対三で島崎雪子に軍配があがります。
封建的な考えが、色濃く残るこの村で、
しかも今まで雪子への風あたりが強かっただけに思えたこの件で、
なぜこのような結果になったのか、
出席者のだれもが理解出来ませんでした。
けれどだれもが夜明けの空のように、
すがすがしい心のたかぶりを感じていたのでした。

理事会の結果が知れ渡ると、
生徒たちの島崎先生を排斥する熱は、しだいに冷めていきました。
そればかりか、この騒ぎで生徒たちは島崎先生に対して、
なにか新しい人格を感じていたのでした。
やがて生徒たちの間では、ラブレタ-事件が笑い話になっていきました。
ある日、新子は偽のラブレタ-を書いた浅子と学校で出会いました。
浅子は、新子にあやまりたい気持ちがあるものの、
いいだせないでいると、
新子は建物の壁をさして、目をつぶってこの壁を力いっぱい叩くように言いました。
浅子はこれで謝罪したことになるならと、
言うとおり目をつぶって力まかせに壁をたたきました。
すると、ピシャリッ!
壁ではない柔らかい物を打った音と感触が彼女の手のひらに感じられました。
そこには新子の顔がありました。
新子は
「これで貸し借りはなくなった訳ね。私、貴女と仲直りするわ」
と、言うと浅子は泣き出してしまいました。
夏が過ぎ、秋になりました。
ある土曜日の夜のことです。

沼田家に雪子、六助、新子、和子、富永が集まっていました。
すると沼田は相談したいことがあるからと、雪子を自分の書斎に呼びました。
「つまり、ぼくは貴女と結婚したいと思うんですけど、貴女の意志はどうでしょう。」「結婚?私と―?」
雪子は、胸の骨がボクンとなるほど、烈しく深い歓びを感じたが、
表面はサラサラした調子で
「貴方が私のことを十分観察された上で、そういうお考えになられたのでしたら、私はお受けしてもいいと思いますわ」っていた。
「ありがとう」と、沼田は心臓のふくらみがのぞかれるような、
生ま生ましい溜息をもらした。
結婚について語り合っていた、二人の話を
たち聞きしていた和子は、それを皆に知らせました。
畳にねそべって、このごろポケットに詰めこんでいる聖書を拾い読みしていた、
富永は、ふと声をあげてその一節を読み出した。
「― かかる故(ゆえ)に人は父母を離れ、その妻に合いて、
二人のもの一体となるべし。
はや、二人にはあらず、一体なり。この故に神の合せ給い(たま)
いしものは人これを離すべからず― 」
大地には、夜の雨がシトシト降りそそぎ、
室の中には、焼きグリの香ばしい匂いが、プンと漂っていた。


石坂 洋次郎 (1900~1986)
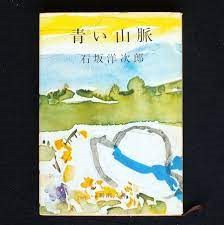
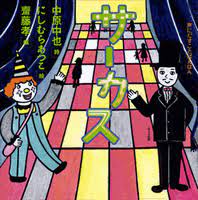
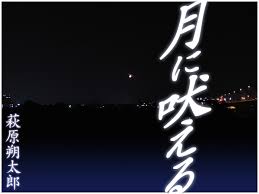
コメント