【今昔ものがたり】は、
平安時代に末期に作られた説話集です。
上は貴族・高僧から、下は盗人下人まで
様々な職業や地位の人々が登場します。
この頃、台頭してきた武士たちの姿も
鮮明に描かれています。
どれも(今は昔)と語り出されていますが、昔も今も
変わらない人間の生きる姿が、時には滑稽、
時にはリアルにいきいきと表現されています。
干し魚を売る女
《あらすじ》
今はむかし、三条天皇(さんじょうてんのう)が東宮(とうぐう)
皇太子だったとき、東宮御所の警備詰め所に、毎日魚を
行商にくる女がいた。
詰め所の士官(しかん)や下士官(かしかん)たちが
家来にいいつけて、買って食べてみると、脂(あぶら)がのっていて
なんともうまかった。
魚をひときれずつに切って干したものである。
とてもうまかったので、女が売りにくるたびに争って買い求め、
おかずにしていた。
さて、八月(今の九月から十月上旬)ごろ、
東宮御所勤務の士官・下士官たちは小さな鷹(たか)に小鳥をとらせる
小鷹狩(こたかがり)に北野へ出て遊んでいるうち、
偶然この魚売りの女に出会った。
士官たちは、この女の顏を知っていたから
「あの女のやつ、魚売りというのに、こんな野原でなにをして
いるのだろう」
と思って、走り寄ってみたら、女は左の手に大きな竹の籠(かご)を提(さ)げ、
右手には長い竿を一本にぎっていた。
この女は、東宮御所の士官たちを見て、お得意さんだから、
お愛想(あいそ)どもいうかと思ったら、反対に目をそらして、
あわてふためいた。
士官の家来たちが、女のほうへ寄って、
「その竹籠(たけかご)にはなにが入っているんじゃ。見せろよ」
とのぞきこもうとすると、女はいやがって見せようとしない。
「おかしいぞ」
と、家来たちは無理やり籠を奪(うば)い取って、のぞいてみたら、
蛇(へび)が四寸くらいの大きさに」
切りそろえて入れてある。
驚いて、
「こんな蛇をどうするんじゃ」
とたずねても、女は黙(だま)って立っていた。
あきれたことに、この女は、長い竿で草むらや藪(やぶ)の茂みを
つっいたりたたいたりして、
おどろいて、はい出してくる蛇をたたき殺して四寸ずつに切り、
家に持ち帰って、塩まぶしにしたうえ、
干物(ひもの)にして売っていた。
東宮御所の士官や下士官たちは、なにも知らずに、
蛇の干し物を争って買って、うまいうまいと食べていたのである。
蛇を食べた人はからだをこわすというが、
実際蛇を食べて中毒しないわけがない。
だから、原形もわからぬように
切れ切れになったような魚を売りにきたら、
それをうっかり買って食べるのはやめるほうがよい。
この話を聞いた人びとがそのように、
とりざたしていたと、語り伝えている。
《私の感想≫
【今昔ものがたり】(コンジャク)と読みます。
話のすべてが、
「今はむかし」
という形で語り始めています。
(結びは、・・・・なむ語り伝えたる。とやとなっています。)
平安時代の人々の生活や心を今に伝える
不思議で面白い話です。
また、機会がありましたら
【今昔ものがたり】を描いてみようと思います。
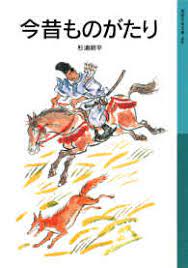






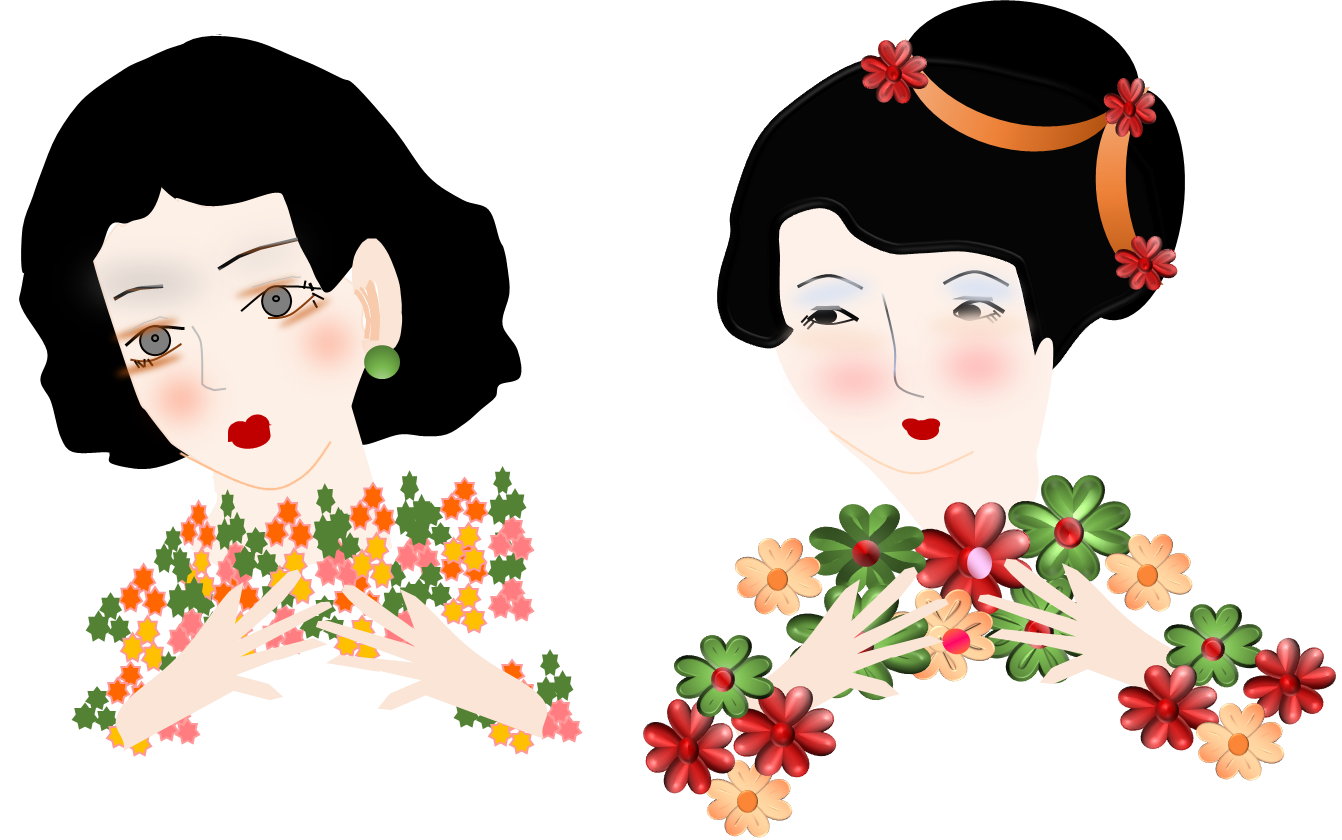
コメント