
~芥川龍之介は、作家として世に出るきっかけは、大学卒業の年の大正5年に
「新思湖」(第四次)で発表した【鼻】で作品は夏目漱石から絶賛されました。~
~「今昔物語(こんじゃくものがたり)」と「宇治拾遺物語(うじしゅういものがたり)」を
参考に書かれた【鼻】~
~芥川龍之介は、身体的コンプレックスについて書いてます。~
~「人の不幸を笑う」という人間の心理が鋭く描かれています。~
~🌟内供(ないぐ)とは宮に入り天皇に奉仕する高僧のことです。~
《あらすじ》
時代は、平安時代です。舞台は、池の尾の寺(京都宇治市)

禅智内供(ぜんちないぐ)の鼻と云えば、池の尾で知らない者はない。長さは
五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように
太い。云わば、細長い腸詰めのような物が、ぶらりと顔のまん中から
ぶら下がっているのである。
禅智内供(ぜんちないぐ)は若い修行僧の頃から自分の鼻の長さをずっと気に病んで
いました。
それは五十歳を過ぎ、内供という高い地位に就いた今になっても続いています。
内供が鼻を持て余した理由は二つありました。

一つは食事をする時でさえ、鼻がお椀の中に入ってしまい。一人ではたべられません。
そこで、内供は弟子の一人を膳の向こうに座らせて、食事の間中、
広さ一寸長さ二尺の板で、鼻を持ち上げてもらわなければ容易ではありませんでした。
弟子の代りに内供に鼻を持ち上げていた少年が、くしゃみをした拍子に手が震え、
鼻を粥の中に落としてしまったことがありました。
その話は宇治から京都まで広まったのです。
しかし、もう一つの方が内供にとって深刻でした。
内供には【鼻】のことで自尊心が傷つけられるのが耐えられなかったのです。

そんなわけで、人のいない時に鏡へ向かって、
いろいろな角度から顔をうつしながら熱心に工夫を凝らして見ました。
苦心すればするほど、【鼻】が短く見えた事は、これまでただの一どもありませんでした。
内供はこう云った消極的な苦心をしながらも、一方では、
積極的に【鼻】の短くなる方法も試しました。
カラスウリをせんじて飲みましたし、
ネズミの小便を【鼻】に塗り付けてみたこともありました。
しかし、何をやっても【鼻】はそのままでした。
ところがある年の秋、京に上った弟子の僧が、知り合いの医者から
【鼻】を短くする方法を教わってきました。
内供は、いつものように【鼻】など気にかけないと云う風にしていたが、
内心では弟子の僧が自分を説き伏せて、この法を試みさせるのをまっていました。
弟子の僧も、内供の予期通り、口を極めて、この法を試みる事を勧め出しました。

さて、鼻を短くする方法とは、ただ鼻をゆでて、その【鼻】を人に踏ませるという、
とても簡単なものでした。
弟子の僧は指も入らない熱湯を、おけに入れてくんできました。
じかに、この湯の中に【鼻】をいれるとなると、熱い湯気で顔をやけどする恐れがあります。
そこでお盆に穴をあけて、それをおけのふたにして
【鼻】だけは湯の中に浸しても、少しも熱くないのです。
鼻が茹で上がるとすぐに、弟子は内供を横にして、鼻を踏みつけ始めました。
弟子は、申し訳なさそうに作業を進めます。
むしろ、気持ちがいいくらいでしたが、鼻があまりに乱暴に扱われるので
内供は不愉快になってきました。
しかし、作業が終わってみると、なるほど鼻はかぎ【鼻】といえるくらいに短くなっています。
あくる日の朝早く、目が覚めた内供は【鼻】が伸びていないことに安心すると、
そこで、初めて、ここ数年なかった、のびのびした気分になりました。

ところが、二、三日すると、内供は意外なことに気が付きます。
よく知った貴族の従者は話も上の空で、
前よりももっとおかしそうに、内供の鼻ばかり眺めていたのです。
これが、下働きの僧ともなると、面と向かっている時は慎んでますが
内供が後ろを向こうものなら、直ぐにくすくす笑い出す始末です。
それも一度や二度のことではありません。
内供は、最初これは自分の顔があまりに変わってしまったからだと考えましたが、
どうもそれだけでは納得できないところがあります。
若い僧たちが笑うのは間違いなく鼻のせいですが
かれらの笑い方は、【鼻】が長かった頃とは何か違うのです。
内供は他に何か理由があるだろうかと考えました。

人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。
勿論、誰でも他人の不幸に同情しない者はない。ところがその人がその
不幸を、どうにかして切りぬける事が出来ると、今度はこっちで何となく物足りない
ような心持ちがする。少し誇帳して云えば、もう一度その人を、同じ不幸に陥れて
見たいような気にさえなる。そうしていつの間にか、消極的ではあるが、或敵意を
その人に対して抱くようになる。内供が、理由を知らないながらも、何となく不快に
思ったのは、池の尾の僧俗の態度に、この傍観者の利己主義をそれとなく感づいた
からに外ならない。
内供は日ごとに機嫌が悪くなりました。
そのしかり方も、あまり意地が悪かったので【鼻】を治した弟子の僧でさえ
陰口を言うようになりました。
風の強いある夜のことでした。
内供が寝つけないでいると、ふと【鼻】がむずがゆいのに気つきました。
手をあててみると、むくんでいて熱さえもっているようです。
殆、忘れようとしていた或感覚が、再内供に帰って来たのはこの時である。
内供は慌てて【鼻】へ手をやった。手にさわるのものは、昨夜の短い【鼻】ではない。
上唇の上から顎の下まで、五六寸あまりもぶら下がっている。昔の長い【鼻】である。
内供は【鼻】が一夜の中に、又元の通り長くなったのを知った。そうしてそれと同時に、
【鼻】が短くなった時と同じような、はればれした心もちが、
どこからともなく帰って来るのを感じた。
こうなれば、もう誰も哂う(わらう)ものはないにちがいない。
内供は心の中でこう自分に囁いた。(ささやいた)
長い【鼻】をあけがたの秋風にぶらつかせながら。.

《私の感想》
~短編小説でありながら、人間の汚い部分が見事に表現されていると思いました。~
~内供の内面的な心の変化と、第三者としての態度から、人間の利己的な部分
~人間のエゴイズムが【鼻】から読みとれます~。
~物語の最後に≪昔の長い【鼻】である。【鼻】が短くなった時と同じような、
『はればれとした心もち』が、どこからともなく帰って来るのを感じた。≫~
~内供は、【鼻】にたいしてのコンプレックスを、乗り越えられたと思います~。
~【鼻】を、読んでいて感じた事は人の批判や、一時的な欲などは本当に(幸せ)に
なれるわけではないと思いました。
芥川龍之介は、鋭く本質を捉える昨家だと思いました。~

芥川龍之介(1892~1927)
昭和2年(1927年)7月24日田端の自宅で多量の
睡眠薬(青酸カリ自殺の説もある)自ら命を絶った。
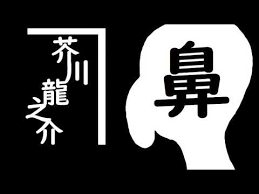

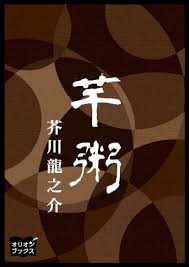
コメント