
芥川龍之介の【芋粥】は、大正五年「新小説」に
発表された初期の短編小説です。
【芋粥】を心ゆくまで(食べてみたい)主人公の望みを叶えるときの
主人公の気持ち・心の変化をつかんでいます。
今昔物語集の話を元にして作られています。
【芋粥】は平安時代においては高級なものでした。
《あらすじ》
平安朝という遠い昔が背景になってます。
その頃、摂政(せっしょう)藤原基経(もとつね)に仕えている
侍の中に、某(なにがし)と云う五位があった。

この五位は、年は四十を過ぎており、赤ひげの薄い、とても貧相な顔立ちで、背も低く、
全体が人並み外れてだらしない男でした。
しかし、ずっと前から、色のさめた衣になえた烏帽子(えぼし)をかぶって、
代わり映えのしない仕事を毎日繰り返してきたことだけは確かです。
五位は、同僚の侍ばかりか、下の者たちからも軽んじられていました。
上役に至っては、冷たい目で見下し、口を利かずに手振りだけで用事を言いつけるありさまです。
しかし、それでも五位は腹を立てませんでした。
五位は、不正な仕打ちを不正とも感じないほど、
いくじのない、臆病な人間だったのです。
五位は、五六年前から【芋粥】と云う物に、異常な執着をもっている。

【芋粥】とは、山の芋を中に切り込んで、それを甘葛(あまずら)の汁で煮た、粥のことを云うのである。
当時は、これが無上の佳味(かみ)として、上は万乗(ばんじょう)の君の食膳にさえ、上せられた。
従って、吾五位の如き人間の口へは、年に一度臨時の客の折にしか、はいらない。
その時でさへ、飲めるのは僅かに喉をうるおすに足る程の少量である。
そこで、【芋粥】を飽きる程飲んで見たいと云う事が、久しい前から、彼の欲望になっていた。

人間は、時として、みたされるか、また、みたされないか、わからない
欲望の為に、一生を捧げてしまう。
その愚を哂う(わら)者は、人生に対する路傍の人に過ぎない。
しかし、五位が夢想していた【芋粥に飽かむ】は、存外容易に
事実となって、現れた。
事の起こりは、ある年の正月基経の館で催された、
大きな宴が終わった後のことです。
五位は、他の侍たちに混じって残った料理の相伴にあずかっていました。
五位は、毎年、この時飲める【芋粥】を楽しみにしていました。
ただ、大勢の侍たちで分け合うので、いくらも口にすることができません。
ことに、今年は残りの【芋粥】が少なかったのです。
そして、気のせいかいつもよりおいしかったのです。
彼は、飲んでしまった後の椀をしげしげと眺めながら、
うすい口髭についている滴を、手のひらで拭いて
誰に云うこともなく、「いつになったら、これに飽ける事かのう」と、こう云った。

その声を聞きつけたのは、権力者の藤原利仁(としひで)でした。
気の毒なことだと、五位に同情してみせると、軽蔑と哀れみがこもった声で
「お望みなら利仁(としひで)がお飽かせ申そう」
と五位に云うのです。
けれど、いつも、いじめられている五位ですから躊躇している五位を見て
「お嫌なら、たってとは申すまい」
と言います。
五位は、慌てて「いや……かたじけのうござる」と答えたのでした。
それから四、五日後、
五位は、利仁と共に二人の従者を連れて馬を進めていました。
東山まで、【芋粥】をたべに行くとばかり思っていた五位でしたが
利仁は、自分の館がある越前の国、敦賀まで行くのだと言います。
遠い危険な道中を思い、五位はべそをかきそうになりました。
五位は、観音経を念じながら、利仁に従って進んで行きました。

「あれに、よい使者が参った。敦賀への言づけを申そう」
狐をとらえて、狐に、
(これから敦賀に館に行き、明日の巳時に琵琶湖の高島まで迎えを出すように伝えよ)
と命じて放り出します。
狐は一目散に走って行きました。
さすがは、狐です。
敦賀の館にいました奥方に、のりうつり伝言を伝えました。
が、それにもかかわらず、我五位の心には何となく釣合いのとれない不安があった。
第一、時間のたって行くのが、待遠い。
しかもそれと同時に、夜の明けると云う事が、
【芋粥】を食う時になると云う事が、そう早く、来てはならないような
心もちがする。
翌朝、庭に、二、三千本もあろうかという長芋が山のように積まれ、
煮え立つ大釜が五つ六つ据えられ、何十人もの女たちが料理の準備に大わらわでした。
五位は、自分がその【芋粥】を食う為に京都から、わざわざ越前の敦賀まで旅をして来た事を考えた。
考えれば考える程、食欲は、実にこの時五位の食欲はもう起きなくなってしまいました。

そうして一時間後、五位たちが膳につくと、そこには銀の提になみなみとつがれた【芋粥】が並んでいました。
しかし、芋と甘葛の臭い、立ち込める湯気の中で繰り広げられる
凄まじい芋粥作りの様子を、目の当たりにしていた五位は、食べないうちから、もう満腹を感じていたのです。
五位は、間が悪そうに額の汗をぬぐいました。
にもかかわらず、利仁の舅の有仁(ありひと)は、「どうぞ、遠慮なく召し上がって下され」と言うのです。

お代わりの【芋粥】が、つがれそうになるのを、五位は必至で断ろうとします。
すると突然、利仁が向かいの家の軒を指さして
「あれを御覧(ごろう)じろ」
と声を上げました。
見ると、そこにはあの坂本の野狐が座っています。
喜んだ利仁には狐にも【芋粥】を与えるよう男たちに命じました。

五位は、【芋粥】を飲んでいる狐を眺めながら、
此処へ来ない前の彼自身を、なつかしく心の中でふり返った。
それは、多くの侍たちに愚弄(ぐろう)されている彼である。
京童にさえ
「何じゃ。この鼻赤めが」
と罵られている彼である。
色のさめた干(すいかん)に、指貫(さしぬき)をつけて飼主のない、
むく犬のように、朱雀大路をうろついて歩く、憐れむべき孤独な彼である。
しかし、同時に又、【芋粥】に飽きたいと云う欲望を、唯一人大事に守っていた、幸福な彼である。
彼は、この上【芋粥】を飲まずにすむ、と云う安心と共に、満面の汗が次第に、鼻の先から乾いてゆくのを感じた。
晴れてはいても、敦賀の朝は身にしみるように、風が寒い。
五位は慌てて、鼻をおさえると、同時に銀の堤に向かって大きなくさめ(くしゃみ)をした。
《私の感想》
【芋粥】を、読んでいて、ゴーゴリの【外套】冒頭部分が似ていると思いました。

だんだんと、読んでいく、うちに【芋粥】に引き込まれていきます。
願望・望みは
叶うまでのものであって、その、望みが叶うと、〈虚しい〉気持ちが襲ってきます。、
夢は
手に届くようで届かない方が、ロマンがあるような気がします。
芥川龍之介は、人間の心の見たくない悪の部分も見事に描ける
〈さすが、芥川龍之介〉

芥川龍之介
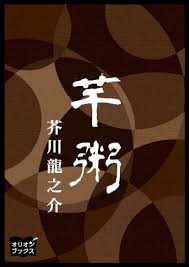
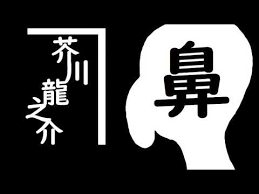
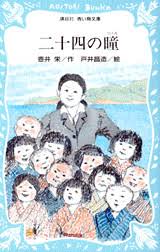
コメント