
【二十四の瞳】の瞳は、
昭和二十七年(1952年)にキリスト教雑誌「ニュ-・エイジ」の
二月号から十一月号に発表されました。
【二十四の瞳】は、昭和三年から昭和二十一年までの物語です。
約二十年間にわたる先生と生徒のたちの人生が描かれています。
それは、民主国家の日本が徐々に軍国主義に包まれ、ついには
世界戦争で国を滅ぼしかけた激動の時代でもありました。

壼井栄は、自分の分身である大石先生を、生徒たちの母のような存在として描き、
出征していく教え子たちには、生きて帰ってきなさいと語りかけます。
作品は、雑誌に発表された直後の、十二月に光文社から単行本として刊行されることになりました。
が、このときに加筆と修正が加えられ、反戦的な要素がはっきりと打ち出されることになりました。
また物語の舞台は、作品中では瀬戸内海の寒村とだけにされていました。

壼井栄は、故郷の小豆島をモデルに村の生活を描いています。
昭和二十九年に公開された、木下恵介監督による映画【二十四の瞳】でも、
小豆島がロケ地として選ばれ、壼井栄自身も撮影現場に出向いています。
《あらすじ》
昭和三年(1928年)4月4日、
瀬戸内海べりの一寒村へ、若い女の先生が赴任してきました。
分教場に赴任した、師範学校での若い先生の名前は大石久子先生です。
大石先生は、湖のような入江の大きな一本松のある村の生まれです。
一本松は、分教場のある岬の村から盆栽の木のように、小さく見えました。
大石先生は、母親との暮らしを優先させるため、片道八キロの距離を、自転車で通う決心をしたのです。
当時、自転車は珍しく、思い切って五か月の月賦で手に入れたものです。
洋服も自転車に乗りやすいようにと、母親の着物を黒く染め自分で縫ったものでした。
しかし、そうとは知らない岬の村の人たちは大石先生のことを、
最初は、おてんばでハイカラぶった、寄りつきがたい女と思っていました。

島の小学生は、四年生までは岬の分教場に通い、五年生からは本村の学校へ通う決まりになっていました。

分教場の新教師として大石久子先生は、一年生十二人を受け持つことになります。
教壇に立った大石先生は、点呼を取り、生徒が、はしゃぐので、皆のあだ名を名簿に書き込みます。
今日初めて教壇に立った大石先生の心に、今日初めて集団生活につながった
十二人の一年生の瞳は、それぞれの個性に輝いて、ことさら印象深くうつりました。
『この瞳を、どうしてにごしてよいものか』
と思うのでした。

二学期の最初の日、九月一日、嵐で岬の村が大きな被害を受けました。
波止場の入り口で漁船が転覆。
道路の上には何隻かの船が打ち上げられ、じゃりで自転車も通れない程、荒れていました。
学校に着いて、子供たちから被害の様子を聞いた大石先生は、
生徒たちを連れて被災した家にお見舞いに行き、そこで子供たちと道路のじゃり掃除を始めました。
子供たちと、先生が笑っていると、すると、よろず屋のおかみさんがすごい剣幕で走り寄ってきました。
「おなご先生、あんたいま、何がおかしいてわろたんですか。」
「人が災難におうたのが、そんなおかしいんですか。」
びっくりして二の句もつげないでいる先生を残して、
よろず屋のおかみさんは、ぷりぷりしながら引き返して行きました。
じっと突っ立って、二分間ほど考えこんでいた先生は、
心配そうにとりまいている生徒たちに気がつくと、泣きそうな顔で笑って、しかし声だけは快活に、
「さ、もう、やめましょう。小石先生失敗の巻きだ。浜で、歌でも歌おうか。」

浜に出て歌い終わった先生と子供たちが、帰ろうとしたときのことです。
大石先生は、ひと足後ろに下がった途端、
「きゃあっ」
という悲鳴をあげました。
落とし穴に落ちてしまったのです。
大石先生の怪我は思いのほかひどく、そのまま船で中町の病院に運ばれました。
それから十日過ぎても半月経っても、大石先生は姿をみせませんでした。
一年生の子供たちは、先生に会いたくってしかたありません。
子供たちは、大人たちには内緒で、とうとう先生の家のある一本末を目指して歩き出しました。
しかし道のりは、やはり遠く、疲れた子供たちは、泣き出してしまいます。
その時、前方から白い砂ぼこりを立てて、乗合いバスが走ってきました。
バスが目の前を通りすぎようとすると、その窓から大石先生の顔が見えました。
子供たちは、歓声をあげながらバスの後を追って走り出します。
バスから降りた大石先生は、松葉杖によりかかったまま、
「どうしたの、いったい」
と大きな声で言いました。

大石先生に、抱きつく子供たち。
笑っている大石先生の頬を、涙がとめどなく流れていました。
それから子供たちは、先生の家できつねうどんを、ご馳走になりました。
そして、喜んだ先生は、一本松を背に皆で記念撮影をして、
返ったのは、秋の日の傾いた頃でした。

大石先生は、足の怪我が長引き
結局、代わりの先生が、おなご先生として分校へ配属され、
大石先生は本校へ移ることになりました。
そして、四年後。
大石先生は、五年生になって本校に通い始めた子供たちと
久しぶりに会えることを楽しみにしていました。
しかし、全員そろっての再会とはなりませんでした。

その後、満州事変や上海事変が起こり、世の中は不況と戦争の影に脅かされはじめます。
子供たちに、とにかく生き抜いてほしい。
大石先生のこうした気持ちは、この時代では異質でした。
それを、教頭にとがめられた大石先生は、悩んだ末に、
新学期
ついに教壇を去ることにしました。
それから、八年が経ちました。
大石先生は、三人の母になっていました。
世の中は大きく変わり、国民の暮らしは戦争一色です。
岬の教え子たちは成長し、それぞれの道を歩んでいました。
昭和十六年、岬の教え子たちは出征して行きます。
出発の日、大石先生は餞別(せんべつ)に添えて、
一本松の写真を渡すと子供たちに言いました。
「名誉の戦死など、しなさんな。生きてもどってくるのよ。」
終戦の翌年、
夫を戦争で、一番下の子を病気で亡くした大石先生は、
臨時教員として十八年ぶりに岬の学校に戻りました。
大石先生の歓迎会が、かつての教え子たちによって
教え子のマスノが、営む料理屋で行われました。
乾杯が済み、やがて一本松の写真の話になると、
戦争で失明した磯吉がいかにも見えているかのように
一本松の写真に顔を向け、一年生のときの顔と同じ顔になり
全員の位置を示しました。

磯吉は、確信をもって、そのならんでいる級友のひとりひとりを、
ひとさし指でおさえてみせるのだったが、すこしずつそれは、
ずれたところをさしていた。あいづちのうてない吉次にかわって
大石先生は答えた。
「そう、そう、そうだわ。そうだ。」
あかるい声で息を合わせている先生のほおを、なみだのすじが走った。
《私の感想》
【二十四の瞳】は、学生の頃から、今まで何回か読みました。
そのたびに、胸に迫るものが熱く私の心を、押し上げてきます。
美しい瀬戸内海に浮かぶ小豆島を舞台に
若いおなご先生と、小学一年生の
十二人の個性に輝いている瞳。
そして、小豆島は何も変わらないのに、
世の中の情勢は大きく動き、軍国主義に包まれ
激動の時代に変わっていきます。
瀬戸内の美しい島、自然、、田舎、子供たちの将来の夢、希望、
戦争は何もかも奪ってしまいます。
十二人いた生徒も七人になってしまい、戦争で目がみえなくなってしまった生徒。
兵隊さんが、亡くなってしまっても、
「戦争だから仕方がない」
私は、この言葉に言いようのない憤りを感じてしまいます。
(戦争とは一体何だったのだろう)と。
加害者、被害者、戦争はなんの意味があるのかと。
壼井栄は、、反戦を、テーマにした小説家だと思います。

壼井栄(1-00~1967)
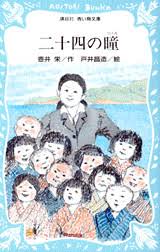
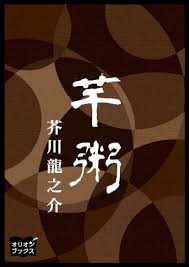
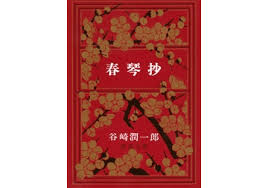
コメント