
【幼年時代】室生犀星(むろうさいせい)を読み
ふるさとは遠きにありて・・・・・を、思いました。

~~
ふさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異士の乞食となるとても
帰るところにあるまじや
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひ涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこにかへらばや
遠きみやこにかへらばや
~~
.明治22年、現在の石川県金沢市に生まれました。
父は、小畠弥左衛門吉種(こはたけやざえもんよしたね)
旧、加賀藩の足軽組頭を務めた人物。
母は、ハル。
ハルは小畠家の女中の身分であり、結婚したうえでの出産ではなかったのです。
そのため犀星は生後すぐに、市内にある雨宝院の住職、
室生真乗の内縁の妻に引き取られ、7歳の時に室生家の養子となりました。
本名は(輝道)
犀星は、その生い立ちを【幼年時代】などの小説に繰り返し描いてます。

【幼年時代】は、
室生犀星が初めて書いた小説で、小説家として文壇に登場した処女作です。
大正八年、当時の作家の登竜門と言われた雑誌
「中央公論」の八月号に掲載されました。
犀星が七歳の春から十三歳の年の暮れまでを、
自らが体験したことをもとに、フィクションも交えながら描いた自伝的小説で、
犀星の初期三部作の最初に当たる作品です。
《あらすじ》
私はよく実家に遊びに行った。
実家はすぐ裏町の奥まった広い果樹園にとり囲まれた、
小ぢんまりした家であった。
そこは玄関に槍が懸けてあって檜(ひのき)の重い四枚の戸があった。

父はもう、六十を越えていたが母は眉の痕の青青した
四十代の色の白い人であった。
私は茶の間へ飛び込むと
「なにか下さいな。」
すぐお菓子をねだった。
その茶の間は、いつも時計の音ばかりが聞こえるほど静かで、
非常にきれいに整頓された清潔な室であった。
「またお前来たのかえ。たった今帰ったばかりなのに」
茶棚から菓子皿を出して、客にでもするかのように、
よく、羊羹や最中を盛って出してくれるのであった。
長火鉢を隔って座って、母と向い合せに話すことが好きであった。
母は、小柄なきりっとした、色白なというより幾分蒼白い顔をしていた。
私は貰われて行った家の母より、実の母がやはり厳しかったけれど、
楽な気がして話されるのであった。
幼い頃、私は養子に出されました。
養子に行った家は、実家の近くだったので、
毎日のように遊びに行っては、実の母からから、
あまり来ては行けないと、たしなめられていました。
私は実の母の顔を見ると、いつも
「これが本当のお母さん。自分を生んだおっかさん」
と、心の底でつぶやいていました。
「おっかさんは何故、僕を今のおうちにやったの。」
「お約束したからさ。まだそんなことを判らなくってもいいの」
私は、何度も同じ質問したのを覚えています。
すると母もまた、いつも同じように答えます。
それでも私には、一粒種だというのに、養子にだされた訳が、分からなかったのです。

実の父は武家の出で、もの静かな人でした。
昼間はほとんど畑に出ていて、私は畑の手入れを手伝いました。
畑には、りんごや、すももなどあちこちに作ってあって
時々、アンズの実を懐にも手にも一杯に取らせてもらったりしました。
実家は楽しく、時の過ぎるのを忘れるほどでした。
養子先の母は、私がちょくちょく実家に行くのを快く思っていないようでした。
もちろん、私を可愛がってくれましたが、私たちの言葉と言葉の間には、
どこか親しみにくいものが、はさまっているように感じられたのです。

そんな家での楽しみといえば、姉との時間だけでした。
姉と一諸の部屋で暮らしていたので、実家からもらってきた(あんず)を姉にあげました。
姉は私よりも大分年上で、その頃は嫁ぎ先から戻って来ていました。
嫁いでいたのは、わずか一年でしたが、戻ってからの姉は
1人で沈み込んでいることが多く、いつも寂しそうに針仕事などしていました。
姉とは血のつながりはありませんでしたが、それでも私たちは次第に、
親しみを抱くようになっていました。
私はよく姉の床の中に入って、色々な話をしてもらいました。

やがて、七つになる頃には仲間たちと町を駆け回って、
梅やりんごなど、庭木になる果実を、(ガリマ)隊と称して
他の町の(ガリマ)隊に出会うと、石を投げ合ったり殴り合いになることもありました。
家ではおとなしい子どもなのですが、外ではわんぱくをしていました。
野町尋常小学校に上がてからも、暴れ者に見られていました。
先生は、私にだけ厳しくあたり、授業で何か一つでも間違えれば
必ず居残りです。
私はだれもいない教室に毎日のように一人立たされました。
姉だけが、私の心のよりどころでした。
実の父が老衰で亡くなったのは、私が九歳の時でした。
葬儀の日から四・五日して、実の母が実家に入った父の弟に、追い出されたのです。
それきり母の行方は分かりません。
実家に残された白い犬を連れて、母に会えないかと思い、
小さな心を痛めながら、犬と一諸に遠くの町まで歩き回ったものです。
この頃には、私が乱暴者だと学校中に知れ渡っていましたから、親しい友達も出来ようがありません。
私の寂しい心を理解してくれるのは、やはり姉だけでした。
姉なしには、私の少年としての生活は、続けられなかったかもしれません。

家の裏の犀川は美しい川でした。
ある雨、続きの日のことです。
川が増水し、上流から1尺ほどの石の地蔵が流されてきました。
私は家まで地蔵を運ぶと、庭にまつって、花や果物などを供え
それから、毎日のように花を換えたり、掃除をしました。
やがて、小屋をかけ提灯(ちょうちん)などをつけて、小さなお堂を作りました。
不思議なことに、地蔵をまつるようになってからは
小さな生き物の命が大切に思え、その一方で供養に没頭するほど、私はますます一人ぼっちでした。
もう、学友たちと、けんかをするのもばかばかしく、相手にすること自体が不愉快でした。
私は、十一歳になっていました。

母がなぜ、実家を出され行方不明になったのか、私は三年後にはもう知っていました。
実は、母は父の正式な妻ではなかったのです。
そのため母は、着物一枚も与えられず、追い出されたのでした。
今も、母はその生死さえ分かりません。
一方で、私の地蔵堂は、母への思いを映すかのように、日ごと立派になっていました。
ある日、隣の寺の和尚さんが、垣根越しに
「なかなか立派なお堂ができましたね。」
地蔵堂を褒めてくれました。
中へ、招き入れると、「なかなかお上手だ。」と言って、数珠をだし
地蔵経を読んでくれました。
私は、姉たちと相談しこのお地蔵さんを、お寺に安置してもらうことにしました。
このことが、きっかけとなり、
私は毎日のように、和尚さんのところに遊びにいくようになりました。
子どものない和尚さんは、私を大変可愛がってくれました。
そして和尚さんは、私に養子に来ないかと言ってくれました。
私は、お寺に行けば不幸な実の母のために静かに祈れると思いました。
そこで、
「坊さんにならなくってもいいならば行きたい。」
と言うと、
「坊さんにならなくってもよろしい。」
と言って、養子にしてくれたのです。

もちろん、寺に養子に行ったといっても、姉の家とは隣同士です。
姉はよく私の地蔵堂にお参りに来てくれましたし、
新しい父と三人でお茶を飲むこともありました。
この寺にきてから、私は自分の心が次第に父の愛や
寺院という全精神の清浄さによって、寂しかったけれど、
私の本当の心に触れ慰めてくれるものがあった。
私はまるで一疋の蟻のように小さく座って合掌していた。
私は人人の遊びざかりの少年期をこうした悲しみに
閉ざされながら、一日一日と送っていた。
ある秋の日のこと、
私が本堂の階段に腰掛けてぼんやり虫の音をきいていると、
姉が同じように階段に腰掛けました。
「あたしね。またお嫁にゆくかもしれないの。」
私はびっくりした。
「よく分からないんだけれど、お母さんがきめて
しまったんだから、行かなければならないわ。」
「あたし嫁(ゆ)きたくないんだけれど……..」
私は、だんだんと自分の
親しいものが、この世界から奪(と)られてゆくのを
感じた。
しまいに魂までが裸にされるような寒さを
今は、自分の統べての感覚にさえ感じていた。
それから四・五日して、姉は嫁いで行くことになりました。
姉を迎えに車が来ました。
姉がいなくなってから寺での生活は、父と二人きりの寂しいものになりました。
でも私は、父との生活が好きでしたし、
父のしてくれる、いろいろな話を聞くのも好きでした。
父は、そんな私によく言ったものです。
「姉さんがいなくなってから、お前はたいへん寂しそうに
しているね。」
父はよく私の心を見ぬいたように、
そんなときは、一層やさしく撫でるように
慰めてくれるのであった。
私は侘しい行燈(あんどん)のしたで、姉のことを考えたり、
母のことを思いだしたりしながら、いつまでも大きな目を
あけていることがあった。
うしろの川の瀬の音と夜風が、しずかに私の枕の
そばまで聞こえた。
私の十三の冬はもう暮れかかっていた。
《私の感想》
~~
【幼年時代】室生犀星
この頃の室生犀星の心情は多感な少年期でした。
どんな思いで、日々暮らしていたかと思うと、私は切なく
遣り切れない思いになってしまいました。
主人公には、二つの家があり
実家と、今の家、
幼い頃は理解出来なかったと思います。
父が亡くなり、父の弟が母親を追い出し、
母親は行方不明になってしまいます。
野町尋常小学校では、先生から受けた体罰、
道理に合わないことを押し付ける先生、
余りにも酷すぎて胸に迫ってきてしまいます。
室生犀星の心境は、余りにも深く計りしれないと思いました。

室生犀星(1889~1962)

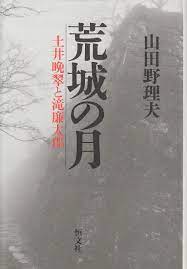
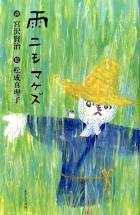
コメント