
【荒城の月】は、
私の思い出の曲です。
小学校六年生の時、学芸会で縦笛を演奏しました。
先生も気合を入れて、私たち生徒も毎日猛特訓の日々でした。

当日、私たち生徒は皆、
「緊張でドキドキしちゃう」と話してました。
いざ、本番では素晴らしい出来栄えでした。
皆で喜び合ったのを、今では懐かしい思い出です。

私は【荒城の月】を、滝廉太郎と思ってました。
(満24歳で肺結核を発病して自宅で亡くなっています。)

【荒城の月】の歌詞は、
土井晩翠の作詞
原曲は、
瀧廉太郎(滝廉太郎)の作曲
編曲は山田耕作です。
日本の歌曲・七五調の歌詞と、西洋音楽のメロディが融合した名曲です。
明治34年(1901年)に、中学校唱歌の懸賞の応募作品として作曲されました。
原曲は無伴奏の歌曲でありました。
歌詞は、東京音楽学校が、土井晩翠に応募テキストとして依頼したものです。
原題は「荒城月」

《歌詞》
1
春高桜(こうろう)の花の宴(えん)
巡る盃(さかづき)影さして
千代の松が枝(え)分け出でし
昔の光 今いずこ
2
秋陣営の霜の色
鳴きゆく雁(かり)の数見せて
植うる剣(つるぎ)に照り沿いし
昔の光今いずこ

3
今荒城の夜半(よわ)の月
変わらぬ光誰(た)がためぞ
垣に残るはただ葛(かずら)
松に歌う(うとう)はただ嵐
4
天上影は変わらねど
栄枯(えいご)は移る世の姿
映さんとてか今も尚
ああ荒城の夜半の月
〈歌詞の意味・現代語訳〉
1
春には城内で花見の宴が開かれ
回し飲む盃(さかづき)には月影が映える
千年の松の枝から こぼれ落ちた
昔の栄華は今どこに
2
秋の古戦場 陣跡の霜に静寂が満ちる
空を行く雁の群れの鳴き声
敗れた兵の地面に刺さった刀に映る
彼らの命の輝きは今どこに

3
今や荒れ果てた城跡を
夜半の月が照らす
昔とかわらぬその光
主も無く 誰のために
石垣に残るは葛のツタのみ
松の枝を鳴らす風の音のみ
4
天上の月が照らす影は今も変わらず
されど世の中の栄枯盛衰を
今もなお映そうとしているのか
ああ荒城を照らす夜半の月よ

《私の感想》
荒城の月は、仙台城がモデルとされたのではないかと
言われます。
荒城の月の真意は、仏教の心「無常」にあったといいます。
この世の中は移り変わるもの、
10年前、3年前と、今とでは違っています。
いつまでも、変わらないものはないと言うことだと思います。

土井晩翠(どいばんすい)
(1871~1952)
明治4年、現在の宮城県仙台市青葉区に、
父(林七)と母(あい)の長男として生まれました。
本名は(林吉)
実家は仙台にあり裕福な家でした。
この家は、大林寺という寺の檀家総代を務めていました。
幼いうちは、あまり信仰心は無かったようです。
しかし年を重ねるにつけ、仏教を深く信仰し、
理解も深めていったようです。
荒城の月の歌詞の中には、この仏教の根本的な教え、
「無常」という考え方が織り込まれていると思います。
土井家の菩提寺は、大林寺です。
ここには、土井晩翠の墓が今でも、残っています。
土井晩翠は、日本各地の学校の校歌を作詞しています。
子供のころ通っていた、母校の木町通小学校の校歌も作詞しています。
昭和25年、詩人としては初めての文化勲章受章者となりました。
文化功労者にも選ばれ、同時に仙台市名誉市民にもなっています。
荒城の月の作詞作曲は、土井晩翠と瀧廉太郎の
共同作業で完成したものでなく、
詩を考え、その詩に曲を付けたと言う経緯であったため
彼ら二人は、直接の面識はありません。

明治35年、帰国途中だった瀧廉太郎は、
ロンドン郊外のテムズ川、河口港に寄港したとき、
そこに居た土井晩翠と、日本郵船「若狭丸」上で初めて会っています。
この面会は、最初で最後の対面となっています。
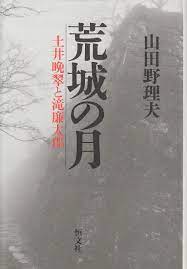
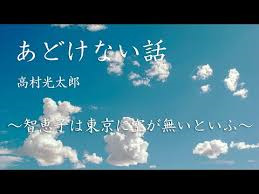

コメント