

~【地獄変】は、短編小説です。~
~物語は平安時代、地獄の様子を描いた屏風を、高名な絵師、
主人公(良秀)が、権力者の持つ大きな力について語る場面から始まります。~
《あらすじ》
堀川の大殿様のような方は、これまでは固(もと)より、
後の世にも恐らく二人とはいらっしゃいますまい。
噂(うわさ)に聞きますと、あの方のお誕生になる前には、大威徳明王(だいとくみょうおう)の
お姿が御母君(おんははぎみ)の夢枕にお立ちになったとか申す事でございますが、
兎に角お生まれつきから、並々の人間とは御違いになっていたようでございます。

大殿様の逸話は数多くありました。
その中でも、今では御家の家宝になっている「地獄変の屏風(びょうぶ)」の
由来ほど、恐ろしい話はございません。
主人公(良秀)は右に出るものはないと言われるほどの高名な絵師です。

年は、当時五十にさしかかったくらいで、見たところは
やせて背が低い意地悪そうな老人で、性格は卑しく、
唇が目立って赤いのが気味悪く、獣のような印象を与える人物でした。
口の悪い者が、立居振舞(たちいふるまい)が猿のようだとして
「猿秀」というあだ名をつけたこともありました。
良秀には、大殿様のお屋敷に仕えている十五歳の一人娘がいました。
この娘が、親に似ても似つかぬ愛嬌のある、しかも母親を
早く失ったせいか、思いやりの深い利口な子でした。
そのため、娘は大殿様の奥方をはじめ、女房たちに可愛がれていたのです。
ある日、お座敷に一匹の小猿を献上した物がおりました。
いたずら盛りの若様が、この猿を「良秀」と名付けると、
それをお座敷中のみんなが面白がって、「良秀、良秀」と呼び立てては
いじめるようになったのであす。

そんなある日のことです。
良秀の娘が廊下を歩いていると、猿の良秀が若殿様を追いかけているところに出くわしました。
娘はやさしく猿を抱き上げると、「どうか御勘弁遊ばしまし、
父が御折鑑(せつかん)を受けますようで、どうもただ見てはおられませぬ」と
若殿様に申し上げました。
これには、さすがの若殿様も、「そうか。父親の命ごいなら許してとらすとしょう」
不承不承におっしゃったのです。

それ以来、娘は猿を可愛がり、猿も娘の身のまわりを離れなくなりました。
娘が風邪を引いて寝込んだ時も、猿はその枕元に座り込んで
心配そうな顔をしながら、しきりにつめをかんでいるのでした。
そうなると不思議なことにお座敷の誰もが猿の良秀をいじめなくなりました。
しかし、娘の父親の良秀は、相変わらずの嫌われ者でした。
お屋敷の中だけに限りません。
比叡山の僧都(そうず)は、良秀の名前を聞いただけで
顔色を変えるほど憎んでいました。
というのも、良秀は、けちで、無慈悲で、恥知らずで、怠け者で、強欲な男だったのです。
特にひどいのは、いつも本朝第一の絵師だということを鼻の先にぶら下げて、
おごり高ぶっていることでした。
そして、絵のことに限ってならまだしも、
世間のあらゆる常識やしきたりを馬鹿にしていたのです。
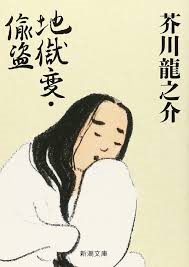
そんな良秀にも、たった一つ、人間らしい情愛のあるところがありました。
一人娘を、それはそれは可愛がっていたことです。
どこの寺にも寄付したことなど、したためしのしない良秀が
娘の着るものや髪飾りのことになると、惜しげもなく整えてやるという可愛がりようでした。
ある時、大殿様からのお言いつけで、見事な絵を描きました折
「褒美にはお望みの物をとらせるぞ」と言われ
良秀は、ぶしつけにも、
「娘をお屋敷仕えから自分の家に戻して欲しい」
と答えました。
大殿様は、機嫌を損ね
「それはならぬ」と、言い放ったのです。
このようなことが四、五回あったでしょうか。
そのたびに、大殿様が良秀を見る目は、冷ややかになっていったのです。
大殿様が良秀を呼びつけ
「地獄変の屏風」
を描くように命じたのは、そんなある日のことでした。
後に良秀が描き上げた「地獄変の屏風」は、他の絵師が描いたものとは
まったく違い、ひと目見たら忘れられない強烈なものでした。


地獄の風に吹き上げられた、その車の簾(すだれ)の中には、女御、更衣にも
まがうばかり、きらびやかに装った女房が、竹の黒髪を炎の中になびかせて、
白いうなじをそらせながら、悶え苦しんでおりますが、
その女房の姿と申し、又燃えしきっている牛車と申し、
何一つとして炎熱地獄の責苦を偲ばせないものはございません。
云わば広い画面の恐ろしさが、この一人の人物にあつまっていると申しましょうか。
これを見るものの耳の底には、自然と物凄い
叫喚の声が伝わって来るかと疑う程、入神の出来映えでございました。
さて「地獄の屏風」を描くように命じられた良秀は、五・六ヵ月もの間、
お座敷にも顔を出さず、ひたすら絵に取りかかっておりました。
そろそろ冬も終わる頃、
下絵が八分通り出来上がった辺りで、良秀の筆はピタリと止まってしまいました。
あの強情な良秀が、人知れず泣いていたのを見たという話しもありました。

また、父親が夢中で絵を描いていた頃から良秀の娘の方は、
次第にふさぎ込むのが目立ってきました。
大殿様が御意に従わせようとしているのだ、という、
うわさがささやかれていました。
それから半月後、良秀がお屋敷に現れ、大殿様にお目通りを願いました。
「地獄の屏風」は軌に既にほとんどできている。しかし一つだけ描けないところがある」
と言うのです。
良秀は、屏風の中に、牛車が一両空から落ちてくる場面を描こうと思っていると言います。
大殿様はどういうわけか、妙に悦ばしそうなご様子で吉秀の言葉を聞くと、
「それで?」
と先を促します。
すると、良秀は突然、かみつくように大殿様に言ったのです。

「どうか檳榔毛(びろうげ)の車を一輌、私の見ている前で、火をかけて
頂きとうございます。そうしてもし出来まするならば―」
大殿様はけたたましく笑いだしました。
そして
「万事その方が、申す通りに致してつかわそう」
とおっしゃいました。
大殿様は、まるで吉秀の、もの狂いに染まったのかと思うほどただならない様子でした。
「檳榔毛(びろうげ)の車にも火をかけよう。又その中にあでやかな女を一人
上臈も装をさせて遣わそう。炎と黒煙とに攻められて、
車の中の女が、悶え死をする―それを描こうと思いついたのは、流石に天下第一の絵師
じゃ。褒めてとらす。おお、褒めてとらすぞ」
それから、二・三日した夜のこと、大殿様は良秀を都のはずれにある山荘に呼び出し、
約束通り、牛車を焼く光景を良秀に見せたのでした。
月のない夜、時刻は真夜中近くでした。
庭には牛車が引きすえられ、その周りを火のついた松明(たいまつ)をもった男たちが
取り囲んでいます。
車には、すだれがかかっており中はみえません。
「良秀に中の女を見させて、つかわさぬか」と、
大殿様が言いつけると、近くのものが松明(たいまつ)を高くかざしながら、
つかつかと車に近づきすだれをさらりとあげました。

良秀は、この事態に半ば正気を失ったのでしょう。
ひざまずいていた良秀は急にとびあがったと思うと、
両手を前に伸ばしたまま車のへ走りかかろうとしました。
この時
「火をかけい」
と大殿様が命じ、男たちが投げる松明(たいまつ)の火を浴びて牛車は燃え上がりました。
白い煙が渦を巻き、火の粉が雨のように舞い上がる、
そのすさまじさと言ったらありません。
火に照らし出された良秀は、大きく目を見開き、頬の肉をひきつらせ、
恐れと悲しみと驚きに、これ以上ないと思われる苦しそうな顔をしていました。
その時私がみた娘の姿を、詳しく申し上げる勇気はありません。
あの煙に咽(むせ)んであお向けた顔の白さ、焔(ほのお)を掃(はら)って
ふり乱れた髪の長さ、それから又見る間に火と変わって行く、
桜の唐衣の美しさ
何と云う惨たらしい景色でございましたろう。
殊(こと)に夜風が一下(ひとおろし)しして、煙が向うへ靡(なび)いた時、
赤い上に金粉を撒(ま)いたような、焔の中から浮き上がって、
髪を口に噛みながら、縛(いましめ)の鎖も切れるばかりの身悶(みもだ)えをした有様は、
地獄の業苦を目のあたりへ写し出したかと
疑われて、私始め強力の侍までおのずと身の毛がよだちました。

すると、何か黒いものが、毬(まり)のように跳ねながら、
燃え盛る牛車の中に飛び込みました。
そして、のけぞった娘の肩を抱いて、鋭く叫んだのです。
それは娘が、可愛がっていたあの猿でした。
その時の良秀には、人間とは思えない怪しげな厳(おごそ)かさがありました。
その場にいた人たちは、荘厳(そうごん)な気持ちになって、
炎上する牛車と良秀の姿を見つめていました。
その中でたった一人、大殿様だけは口に泡をため、青ざめた顔をして、
のどが乾いた獣のようにあえいでいたのです。
その夜の事件は、すぐに世間に知れ渡りました。
目の前で娘を焼き殺されながらも、絵を描き続けた良秀を悪く言う人は少なくありませんでした。
ところが、これまで良秀をののしていた比叡山の僧都さえ、
完成した「地獄の屏風」を見た者は、不思議に厳かな気持ちに打たれるのでした。
やがて良秀を悪く言う者は、いなくなりました。

しかし、そうなった時分には良秀はもうこの世に無い人の数にはいって
おりました。
それも屏風の出来上がった次の夜に、
自分の部屋の梁(はり)へ縄をかけて縊(くび)れ死んだのでございます。
一人娘を先立てた、あの男は恐らく安閑として生きながらえるのに
絶えなかったのでございましょう。
死骸(しがい)は今でも、あの男の家の跡に埋(うず)まっております。
尤も小さな標(しるし)の石は、その後何十年かの雨風に曝(さら)されて、
とうの,昔、誰の墓とも知れないように、苔(こけ)蒸しているにちがいございません。

《私の感想}》
~【地獄変】強烈なインパクトで、心に響きます。~
~凄いの一言です。~
~最も愛している一人娘を、絵の追求のためとは言え、焼け死ぬ姿を
目の前で見るとは、芥川龍之介の狂意的な世界が垣間見えた気がしました。~
~芥川龍之介は、情熱のすべてを【地獄変】に注ぎ込むことで、完成した作品だと思います。~
~物語の最後で娘が可愛がっていた、お猿が炎に飛び込んでいく場面にも心が打たれました。~
~私の思いですが、大殿様は娘に惚れていましたが、娘は相手にしませんでした。
プライドの高い、大殿様の腹いせもあったのではないでしょうか。~
~【地獄変】悪魔的な要素と芸術的な圧倒される物語です。~

芥川龍之介(1892-1927)
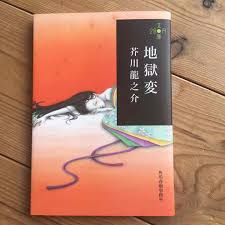
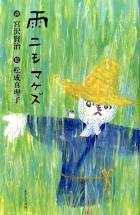
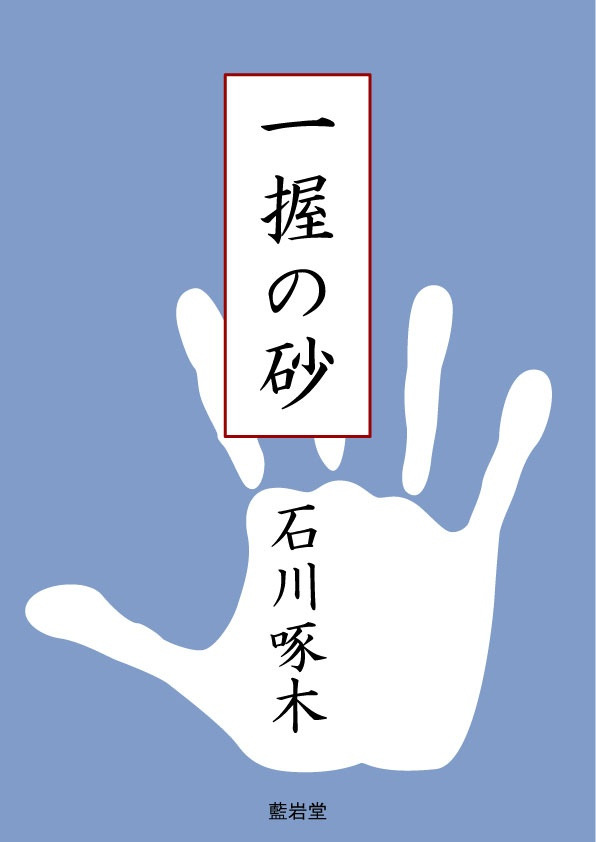
コメント