
【かじ屋鬼(やおに)】も鬼の話です。これは千本の槍を一晩のうちに作って美しい鍛冶屋の娘を妻にしょうとしたが、人間にだまされて失敗する間抜けな鬼の話です。
《 あらすじ 》
昔、富山県の稗田(ひえだ)という村に、たいそう腕(うで)のいい、大金持ちの鍛冶屋が住んでいました。

鍛冶屋の仕事場からは、毎日、毎日、
トン、トン、トン、トン ドン、ドン、ドン、ドン シャ-、シャ-、シャ-、シャー バン、バン、バン、バンと鉄を打つ音やふいごの音が、まるで音楽のように聞こえてきました。
この鍛冶屋には、目に入れても痛くないほど、大事に大事に育てている一人娘がいました。村でも評判の、気だてがよくて美しい娘で、村中の若者たちから嫁(よめ)にしたいと思われていました。

ところが鍛冶屋は、かわいい一人娘だからと、なかなか嫁に出すことを許しませんでした。
そして今日も、トン、トン、トン、トン
ドン、ドン、ドン、ドン シャ-、シャ-、シャ-、シャー バン、バン、バン、バンと音楽を、奏(かな)でるのでした。
けれど月日も過ぎ、さすがの鍛冶屋も、「そろそろ嫁に出さなくっては、大事な娘が売れ残ってしまうかもしれないな」と心配になりました。けれど、大切な一人娘のこと、なかなか決心がつきませんでした。
そこで鍛冶屋は、「よし、腕のいい若者を選んで婿養子(むこようし)にして、鍛冶屋を継(つ)がせよう」

と考えて、家の前に、「一晩で千本の槍(やり)を鍛(きた)えることのできた者を、娘の婿にする」という立札を立てました。
立札を見た村人は、

「そんなことができるわけがない」「結局、嫁にやりたくないだけなんだ」「一晩に千本の槍だなんて、とても人間技(にんげんわざ)じゃない」と、あきれ果て、鍛冶屋にちかづこうとする若者は一人もいませんでした。
そんなある日、見慣れぬ若者が鍛冶屋を訪ねてきて、「婿にしてくれ」と言いました。
「立札を見ての事か」「はい」「婿になるには、一番鶏(いちばんどり)が鳴くまでに、千本の槍を鍛えねばならぬことを承知の上か」「はい、承知です」鍛冶屋は半信半疑(はんしんはんぎ)ではあったが、若者を仕事場に連れていき言いました。
「ここにある道具は、どれでも自由に使ってよい。ただし、一番鶏が鳴いたら、その場で槍を鍛えるのは辞めるのだ。よいか、一番鶏が鳴くまでだぞ」すると若者は言いました。
「分かりました。ただ、ひとつ約束してください。明日の朝、一番鶏が鳴くまで、決して仕事場をのぞかないでください」「うむ、分かった」こうして若者は一晩で、千本の槍を鍛えることになりました。

鍛冶屋は、若者の仕事ぶりは気になったが、のぞかないと約束したので、床(とこ)に就(つ)くことにしました。だが、不思議なことに、仕事場の中からは、ときどき若者の荒(あら)い息が聞こえてくるだけで、鉄を打つ音もふいごの音も聞こえてきませんでした。そのうち、鍛冶屋はうとうと眠りに落ちました。
夜明け前、鍛冶屋がふと目を覚まし仕事場のほうへ行くと、あいかわらず、若者の息づかいだけが聞こえていました。「はて、どうしたことか」と仕事場のあまりの静けさに、鍛冶屋はつい若者との約束を忘れて中をのぞいてしまいました。

すると中にいたのは、大きな赤鬼でした。口から炎(ほのお)を吹き出して、鉄の棒をまるで粘土(ねんど)のように曲げたり伸ばしたりしながら、次々に槍を作りあげています。赤鬼の横には、すでにできあがった槍が山のように積まれていました。
鍛冶屋はびっくりして、鶏小屋にむかいました。「大変だ。早く一番鶏が鳴かないと、このままでは娘を鬼にやることになってしまう」鍛冶屋はあわてて眠っている鶏(にわとり)をつついたが、目を覚ましたものの、いっこうに時を告げようとはしません。それではと、鍛冶屋は桶(おけ)にお湯を汲(く)んできて、鶏の足元にそっと流しました。
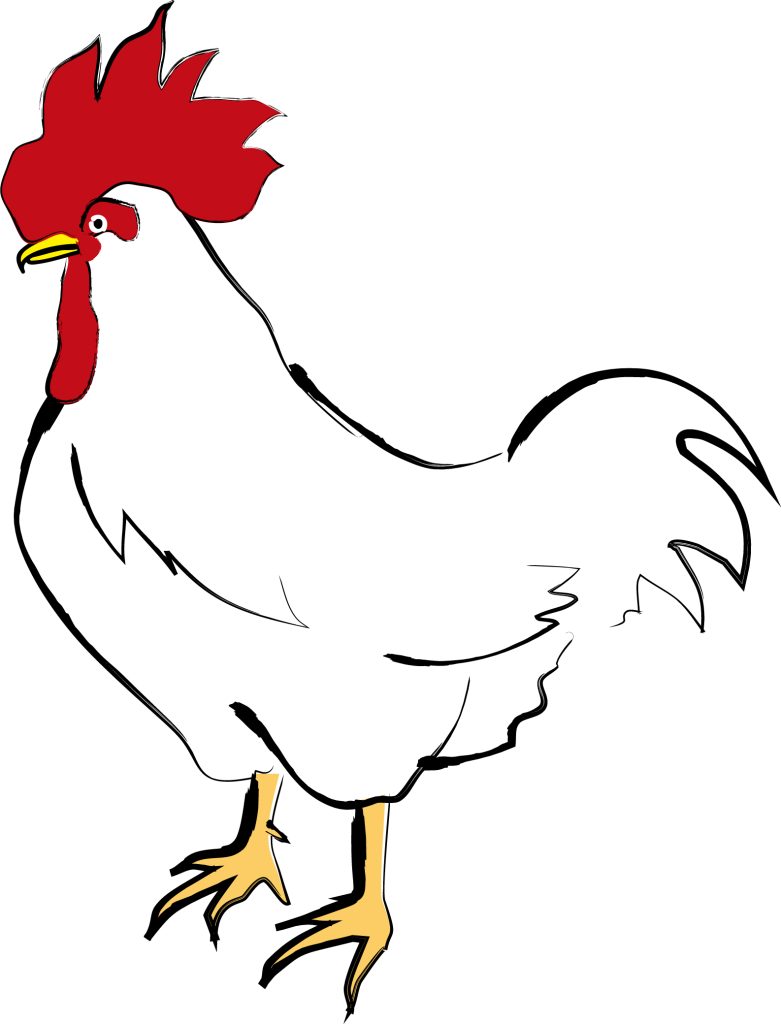
すると、足元があたたかくなった鶏は朝が来たと思い込み、とうとう、コ-ケッコ-と時を告げました。
仕事場では赤鬼がちょうど九九九本の槍を鍛え終わり、千本目にとりかかったところでした。
「おお、残念だ。あと一本だったのに」赤鬼は鍛え終わった九九九本の槍を抱え、仕事場の戸を蹴破(けやぶ)って、外に飛び出し、あっという間に姿を消してしまったそうです。
《 わたしの感想 》
他の昔話では、鬼が逃げ出した後に999本の素晴らしい槍が残されていました。この鬼の槍は、評判になり鍛冶屋はますます繁盛したとのことです。
【かじ屋鬼(やおに)】は、鬼が槍を抱えて逃げ出したので娘は鬼の嫁にならずにすみました。思ったことは、難問にぶつかっても想像力と勇気を持っことが大事ではないかと思いました。


コメント