
~【耳無芳一の話】は、小学5年生か6年生の時読んで
とても〈怖い〉記憶が、甦ってきました。
平家の怨霊に耳を引きちぎられる場面が、痛そうで、痛そうで
<ゾッ>とした
記憶が残っています。~
〈あらすじ〉
今から数百年前のこと、この関ヶ原に芳一という盲目の琵琶法師がすんでおりました。
芳一は琵琶を演奏し謡うのがとりわけ上手く、特に芳一の得意とするのは
壇之浦の戦いの歌を、謡えば涙を、こぼさぬ者はないと言われていました。
芳一は貧しかったのですが、類まれな琵琶の才能もあって
阿弥陀寺の住職から寺の一部屋を与えられておりました。
ある夏の暑い夜のこと、住職は法事のため檀家に呼ばれ
芳一だけを寺に残して出て行きました。
芳一のもとに、一人の武者が訪れ、歩くたびにカタカタという音で
その人が甲胄をつけていることが分かりました。
主人のために琵琶を弾いてくれと、芳一の手を引いて大きな屋敷へと案内します。
しかし、町のこの辺りには阿弥陀寺の大門以外に大きな門はありません。
芳一は、訝しく思いました。
でも、見えないながらもその雰囲気から、屋敷の主人は高貴なお方に違いないと思い、手をひかれ、
数え切れないほど、たくさんの柱の角を曲がり、驚くほど広い畳を敷いた床を通り、大きな部屋の
真中に案内されました。
座って琵琶の調子を合わせていると、ある高貴な老女が芳一に向かって言いました。

「壇之浦の戦の話をお語りなされ。その一条下が一番哀れの深い処で御座いますから。」
芳一は声を張り上げ、激しい戦いの様子を琵琶をかきならし、驚くばかりに見事に再現しました。
演奏が済むと、主人らは大いに感動し、先ほどの高貴な老女が
「これから六日間、毎晩ここへ来て琵琶を弾くように、このことは、他言無用」と芳一に言ったのでした。
次の日の晩もその次の日の晩も最初の晩と同じ侍に連れられて、
高貴な方のお屋敷に出向き、琵琶を弾きました。
しかし、夜中に芳一が黙って出かけることを心配した住職が
下男に「再び寺を出て行くようなことがあれば後をつけていくように。」と、言いつけたのです。
その晩、芳一が寺を抜け出して行くのを見た下男たちは、
芳一が阿弥陀寺の墓地の中から、盛んに琵琶を弾いている音が聞こえます。

雨の中に、安徳天皇の記念の墓の前に独り坐って、琵琶の曲をならし
壇之浦の合戦の曲を高く誦して。
それから至る処に、たくさんの墓の上に死者の霊火が蝋燭のように燃えていました。
いまだかつて人の目にこれほどの鬼火が見えた事はありませんでした。

住職は芳一を、問い詰め事情を聞いた、住職はすぐさまその話しを聞き
芳一の身が、危ういことを、知りました。
住職は「またも、その言うことを聴いたなら、いずれにしても早晩、芳一は殺される。」
住職は、その晩不運なことに、どうしても出かけなければならず
芳一の身体に経文を、胸、背、頭、
顔、手足と、身体の隅々に、いたるまで般若心経を書きつけ、言いました。

<どんなことがあっても返事をしたり動いてはならぬ。口を利かず静かに座ってなさい。」
日が暮れ、静かに座禅を組む芳一の前に例によって侍が「芳一!」と
底力のある恐ろしい声で呼んだ。
侍が、芳一の傍に止まった。
芳一は全身が胸の鼓動が、するにつれて震え、まったく森閑としてしまった。
侍は、「琵琶がある、ただ耳が二つあるばかりだ。殿様へこの耳を持って行こう。」
その瞬間に芳一は鉄のような指で両耳を摑まれ、引きちぎれたのを感じた!

こうして、一晩が経ち日の出前に住職は寺に戻って来ました。
そこで、住職が見たものは、芳一が血をだらだらと流しながらも座禅の姿勢を崩さない、
まま座っている姿です。
住職は思わず「かわいそうに芳一。」と叫びました。
芳一もその声を聞くと、とたんに泣きだしました。

住職は耳だけは寺の坊主に書くように命じ、確認しないまま出かけてしまったのです。
親切な医者の助けで、芳一の怪我はほどなく治った。
この、不思議な事件の話は諸方に広がり、たちまち芳一は、有名になった。
貴い人々が大勢、関ヶ原に行って、芳一の吟誦を聞いた。
そして芳一は多額の金具を贈り物に貰った。
それで芳一は金持ちになった。
しかしこの事件のあった時から、この男は【耳無芳一】という呼び名ばかりで知られていた。
〈私の思い、感じたこと〉
~どうして住職が、耳にだけ般若心経を、書かなかったのかが疑問に思いました。
昔ですから、ろうそくを頼りに住職と小坊主達と書いたと思いますがやっぱし
見落としたり、忘れたりすることもあるのかも?ですね。
それとも、住職が、芳一の心を試すことも考えられます。
芳一は、平家の幽霊たちと関わりを持ってしまいました。
住職は悪霊を取り除くために身体の隅々までに、般若心経を書いたと思いますが、
耳だけを書かなかったのは芳一の心、精神を確かめたかったのか?とも思いました。
私は、平家の幽霊に、引きずりこまれ八つ裂きにされるよりは
耳を引きちぎられるのは酷いですが
これで、二度と、幽霊が来ることは無いと思いました。
生きている、人間が死んだ幽霊とは関わりを持つことは、あってはならないことですし
芳一のように、仏様の道を歩んでいる者なら尚更のこともようにも感じました。~

1850年、アイルランド人軍医の父とギリシャ人の母の間に
ラフカディオ・ハ-ンとしてギリシャのレフカダ島に生まれる。
二歳の時に家族でアイルランドに移住するが六歳の時に父母が離婚。
大叔母に厳格に育てられ高い教育も受けたが、十七の時に学校を辞めて
十九歳で渡米。
二十代半ばに新聞記者になり、シンシナティやニュ-オリンズに暮らした。
ハ-ンが日本を訪れたのは明治二十三年(1890年)ニュヨ-クの雑誌者の通信員と
して来日するが、契約がこじれすぐに絶縁。
現在の島根大学の英語教師の職を得る。
翌年、士族の娘小泉節子と結婚したハ-ンは、松江から熊本の第五高等学校に移籍。
明治二十九年英文学講師として東京帝国大学に招かれると、日本に帰化し
小泉八雲を名乗った。
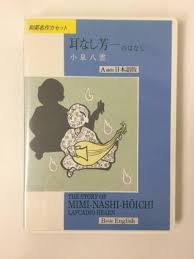
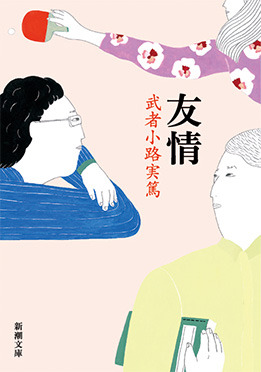
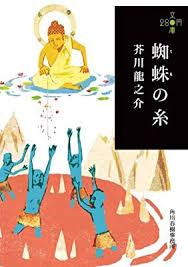
コメント