
私が、幼い頃、近所のお姉さんが
【聖徳太子】は
「10人が話すことを一度に聞くことができるの」と、
教えてくれたことが切掛けで興味を持ちました。

【聖徳太子】については、
古くから人々の信仰があつく、
多くの伝説的な物語も加わったため
史実と区別できない部分もあります。
とくに平安時代以降、太子の伝記を絵にした
(聖徳太子絵伝)や(太子像)がつくられました。

父は用明天皇(ようめいてんのう)
母は穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのこうじょ)
【聖徳太子】は用明天皇のすんでいた橘宮(たちばなのみや)
の厩(うまや)の前で生まれたため厩戸皇子(うまやどのおうじ)と
名づけられたといわれています。

14歳のとき、用明天皇がなくなりました。
この年、曽我馬子(そがのうまこ)の軍(ぐん)に加わり、
物部守屋(ものべもりや)をほろぼしました。
この戦いのとき、太子は四天王(してんのう)の像をほり、
勝てばこの四天王(してんのう)のために寺院をたてようと、
心に誓いました。
そこで守屋をたおした後、四天王寺(してんのうじ)をたてました。

593年、20歳の太子は皇太子(こうたいし)となり、
おばの推古天皇(すいこてんのう)の摂生(せつしょう)として、
実際の政治を決定しました。
太子は、10人が一度にうったえることを、ひとことも、もらさずに
聞き分けて答えたため、
豊聡耳(とよよみみ)ともよばれたといわれます。

太子には5人の夫人(ふじん)と、山背大兄王(やましろのおおえのおう)を
はじめ14人の皇子(おうじ)皇女(こうじょ)がありました。
21年後の643年、曽我入鹿(そがのいるか)によって斑鳩宮(いかるがみや)
の山背大兄王(やましろのおおえのおう)がおそわれ一族
ともども自害し、太子の上宮王家(じょうぐうおうけ)は滅びました。
【聖徳太子】略年表
574年:太子誕生

587年:曽我馬子(そがのうまこ)らが
物部守屋(ものべのもりや)をうちほろぼす。
太子(たいし)は馬子(うまこ)の軍にくわわる。

593年:摂政(せつしょう)となる。
四天王寺(してんのうじ)を建立(こんりゅう)する。
600年:第一回遣隋使(だいいちかいけんずいし)を派遣(はけん)する。
603年:冠位十二階(かんいじゅうにかい)を定める。
604年:憲法十七条を作成する。
605年:斑鳩宮(いかるがのみや)にうつる。
606年:(勝鬘経しょうまんきょう)(法華経ほけきょう)を講義する。
607年:第二回遣隋使(けんずいし)として小野妹子(おののいもこ)
を派遣。(新しい文化を取り入れる。)
620年:馬子(うまこ)と協力して(天皇記)(国記)を編さんする。
622年:太子49歳で死去(しきょ)。
磯長墓に(しながのはか) 横穴式石室(よこあなしきせきしつ)
太子の死後の世界の天寿国曼荼羅繍町(てんじゅまんだらしゅうちょう)
をつくりました。
河内飛鳥(大阪府太子町)に太子夫妻と母をほうむった
623年:皇子(おうじ)らが、太子の等身大(とうしんだい)の仏像をつくる。

643年:皇子山背大兄王(おうじやましろのおおえのおう)が
曽我入鹿(そがのいるか)におそわれ、一族はほろびる。

【聖徳太子】
出身地:飛鳥(現在の奈良県)
生年月日:574年2月7日
死亡年月日:622年4月8日(享年48歳)
別名:厩.ロ王子(うまやどの王子)
推古天皇の摂政(せっしょう)として実権を握る。
天皇中心の国づくりを目指す。
《まとめ》
日本が国としてまだ整っていなかった時代。
聖徳太子は、仏経をとりいれたり、役人の制度など国の
基盤づくりに貢献しました。
仏経の教えを取り入れ、天皇中心の国づくりをめざしました。
【聖徳太子】と呼ばれるようになったのは亡くなった後のこと。
人々から慕われ尊敬されていた事が、よく分かりました。

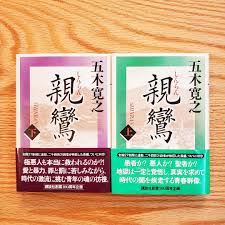
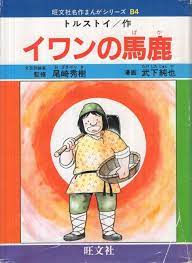
コメント