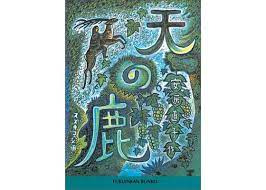
末娘みゆきと牡鹿との(運命の人)
せつなさあふれる物語。
この世と、この世でない世界(あの世)
そして運命的の出会い。
物語に一気に引き込まれていきます。
読み終わると不思議な寂しさ、切なさ、
柔らかく心に余韻が残ります。
《あらすじ》

猟師(りょうし)の清十さんは、鹿撃ちの名人でした。
鉄砲ひとつに、犬二匹つかって、これまでに
仕留めた鹿の数は数え切れません。
また、清十さんは、鹿笛を吹くのが得意でしたから、
秋の日暮れに、犬も連れずに、たった一人で
山へ出かけて行って、岩のかげにかくれて笛を吹きました。
ビイ、ビイ、ビイイ・・・・
牝鹿(めじか)鳴き声そっくりの鹿笛は、一山も二山も越えた
ところにいる牡鹿(おじか)をおびきだすのでした。
ところが、あるとき、ものをしゃべる不思議な鹿に出会って、
不思議な鹿の国に、連れられて行ったのです。
鹿の背にまたがり谷を三つも四つも越えたので、
清十さんは目がくらくらしてきました。
「山ぶどうが、ちょうど食べごろだ。あんたのかぶっている、
頭巾に一杯取ってくれないかね」
鹿に言われて、頭巾一杯ぶどうを入れて、
鹿は細いけもの道をびゆ-びゆ-とばしていきます。
そんなふうにして、はなれ山についたのです。
清十さんは、喉(のど)はからから声も出なくなりました。
「ほうら、鹿の市だ。あの松の木が、市の入口だ」
「のどがかわいたら、頭巾の中のお酒をのむといい」
清十さんは驚いて頭巾の中に入れたはずの山ぶどうは、
跡形もなくなって、かわりにとろりとした紫の飲み物が
たっぷり入っているではありませんか。
清十さんはそこで、こくこくと、その不思議なお酒飲みました。
中々、いい味でほんの三十分や四十分で出来たものとは
思われませんでした。
「残りは、頭巾の口を確りしばって、後から来る者のために
この松の木に、ぶらさげておいてほしい」
「さあ、下りて、後は一人で行くといい。
わたしは、とてもつかれたから、ここで休んで待っていよう」
「よし、それじゃひとつ、言ってみるか」
「この市では、何でも金貨一枚だ。 さあ、これでなんでも好きなものを
一つ買って、一時間でもどっておいで」
鹿は、静かに言いました。
「一時間経って、ふくろうが鳴くから、あんたがここへもどって
きたら、また、あんたを村まで送ってあげよう」
やがて、清十さんの耳に、笛の音(ね)や鈴や、太鼓の
音がにぎやかな呼び声も聞こえてきました。
清十さんはすっかりいい気持になり、ほいほい踊るような
足取りで進んで行きました。
鹿の市はほたる色をしたあかりがともっていました。
そして、そのあかりの下で、いく匹もの鹿たちが、店を出して
いたのです。
小さな茶色の帽子を頭に載せている鹿、たばこを吸っている鹿
鈴をならしながら大声で客を呼よんでいる鹿もいます。
その間をたくさんのお客の鹿たちが、ざわめきながら、
歩きまわっているのでした。

それは、村祭りの夜店の風景に似ていました。
鹿の目は澄んでいて、どうぞ買ってくださいというように
清十さんを見上げていました。
その顏は、どれもこれも、どこかで見たことがあるように
思われました。
あのうるんだ目、角のかたち、あの耳・・・・
どれもむかし見たようでした。
が、はじめて会う鹿のようでもありました。
きょろきょろ見まわすとありとあらゆる店があるのでした。
清十さんは、さて、どれを買ったものかと迷っているとき、
ひょいと目についたのが、紫水晶(むらさきすいしょう)の
首飾りでした。
さっき飛び越えた谷川の水の色に似ているように思えて
「こら、きれいなもんだ・・・・」
と取り上げたとき思いがけなく、長い首飾りでした。
紫のまるい玉が、ぶつかり合って、ぽろぽろといい音を
をたてました。
たった一枚の金貨とひきかえるには、指輪よりも、かんざしよりも、
これが一番いいと思ったのでした。
「よし、買った!」
清十さんは、金貨を鹿に渡しました。
すると、としとった牝鹿はじっと清十さんを見つめて、幾度も
うなずきながら、
「娘さんに、よろしくなぁ」と言いました。
もう、ほかのお客の相手をはじめました。
清十さんは「そうとも、娘は、三人いるんだ」
(鹿一頭つかまえた。売りにだしたら、こんな首飾りの三つは、
買えるはずだ。その上、おつりもくるはずだ)
そう思うと、清十さんは、わき目もふらずに走ったのです。
あの松の木のところにたどり着くと、牡鹿は静かに目を
つぶつていました。
清十さんは、ぶっきらぼうに言いました。
「もう少し、金貨をもらうわけにはいかんかねぇ」
牡鹿は、静かに目をあけ
「わたしの命の値段は金貨一枚だ。それであんたが宝石をひとつ買ったのなら、
それがわたしの命とおんなじだ」
どこかでほうほうと、鳴くふくろうの声を聞いたのです。
すると、そのとたん、あたりはしいんと静まり返りました。
ふり向けば、鹿の市は、あとかたもなく消えていて、はなれ山の赤い
岩を、月の光がこうこうとてらしているばかりでした。
「さあ、帰ろう」と鹿は言いました。
急に、気味が悪くなって、清十さんは鹿の背に飛び乗りました。
鹿は、またびゅうびゅうと、風を切って走りました。
走りながら鹿は、清十さんに、こんなことをたずねました。
「むかあし、鹿のキモを食べたのは、あんたの三人の娘のうちの、
どれだね」
いきなり、そんなこときかされて、清十さんはどぎまぎしました。
清十さんは、しばらく考えこんでから、しどろもどろに、こう答えました。
「さあなぁ。もう忘れたなぁ」
むかし、どの娘かが、病気をしたときに清十さんは、しとめたばかりの
牡鹿のキモをあぶってたべさせたのでした。
が、それを食べたのが、誰だったのか、とんと忘れてしまったのでした。
「本当に忘れたのかい」
鹿は、さびしそうにつぶやくと、あとは黙って走り続けました。
鹿の心が、悲しみに震えているのを、清十さんは感じていました。
またがっている鹿の体が、走りながらだんだんと痩せていくような気も
しました。

清十さんは、夜明けに家にもどりました
おかみさんに、不思議な出来ごとを話していると、三人の娘もいつの間にか
清十さんの話を熱心に聞いていたのです。
聞き手がふえたとわかると、清十さんは、ますます得意でした。
おかみさんは、青い壺の話になるとため息をつきました。
たえは、金銀のある反物(たんもの)を、是非ほしかったと言いました。
あやは、珊瑚(さんご)のかんざしを、ひと目見たかったと言いました。
末娘のみゆきは、大きな金色の梨(なし)をひとくち食べてみたかったと
ため息をつきました。
「あんた、もう一遍、その鹿に会うことは出来んもんかねぇ」
おかみさんは、つくづくと、言いました。
たえが、「わたしも、そんな鹿に会いたいなぁ」
つづいて、あやも「わたしも、会いたいなぁ」と、さけんだのでした。
ただ、みゆきだけは黙って、うつむいていました。
そんなにたくさん走りつづけて、その鹿は、喉がかわいたろうに、おなかも
すいたろうに、今ごろは、どこにうずくまって、荒い息をしているだろうか・・・・
そんなことを、みゆきは思っていました。
紫水晶の首飾りは結婚する娘のたえに、その宝ものを与えることに
したのです。
それから幾日かたった晩のこと、たえも牡鹿と鹿の市に行き、
さんざん迷ったすえ、紺地に白と、黄と、うす桃色の小菊が一面に
ちりばめられた反物にしました。
鹿を休ませず、せかして直ぐに家に帰るように鹿に頼みました。
鹿は、びゅ-びゅ-とばしながら
「大地が、焼きもちをやくから、声をだしたり話してはいけないよ。
大変なことになるからね」
たえは、声をだしてしまい反物の模様の
花はすっかりこぼれてしまいました。
たえは、「反物の模様、みんな、なくなってしまった」
悲しそうにつぶやきました。
たえは、鹿の市で買った反物を着物に仕立てて嫁入りの着物に
と思っていましたが模様の消えてしまった、ただの紺の布は
あんまり地味で殺風景でした。
「こんな反物は、もういらない!」
たえが、そうさけんだとき
「そんなら、わたしがもらった」
横からそう言ったのは二番目のあやでした。
「いくら地味でも、こんないい絹は、まずもてないもの。
着物にして、大事にしとけば、きっと役に立っよ」
そう言うと、あやは反物を姉からもらって、もうその日から
仕立てにかかったのです。
ところが、これまで木綿しか縫ったことのない上等の絹は、
ささくれた手にはひっかかるし、縫い針はすべりすぎるし、
待針は抜けてしまうしで、中々思うようにはゆきません。
さんざん、縫ったりほどいたりを繰り返したすえに反物が
やっとどうやら一枚の着物のかたちになったのは、それから
三日目の晩のことでした。
ひゆ-ひゆ-と吹き付ける風の音にまじって、家の外で
妙な声がしたのです。
「二番目の娘さん出ておいで
あんたにひと目会いたいよ」
「ああ、あの牡鹿が、呼んでいるんだ。
確かに、そうだ」
あやは躍り上がりました。
わたしも、鹿の市に行けるんだ。
あやは、そっと外へ出ました。
「鹿の市へ連れてってあげよう」
あやは、鹿の背にすわると、その首に確りつかまりました。
けれども、その夜は、月も星もない、真っ暗やみの闇夜(やみよ)でした。

「どうして、こんなに暗いんだろう」
「あんたが闇夜の着物を着てきたからだ。たった今、月も星も、
隠れてしまったんだ」
山じゅうの笹の葉のこすれるような音、うお-んと、妙な遠吠えが、
聞こえて耳をすませば、鬼の声も魔物の声も聞こえてきます。
それから、鹿は飛ばしていきました。
鹿の市で、あやは珊瑚のかんざしなんだと、そんなことを思いながら
鹿の市のざわめきの中に一息に飛び込んで行きました。
まえに父さんや姉さんがから聞いてた通り、さまざまな店が
あやの目のまえに続いていました。
あやの目には何と快く美しく眩しくみえたことでしょう。
宝石の店を見つけて大きなルビ-を、見つめていたとき、後ろで
「娘さん帰りは怖くないのかい。松暗闇だよ」
はっとして、あやがふり向くと、ランプの店がありました。

あやは帰りを思うと、かんざしを諦めてランプにしました。
「いいねぇ・・・・これで帰りは大丈夫だねぇ。お月さま一つ
ぶらさげているのとおんなじだ」
心が明るくなり、不思議なことに聞いてなかった店が
広がっていくのでした。
どこからか、かすかに、ふくろうのほうほうと、鳴く声が
聞こえてきました。
あやは「たいへんだ!」駆け出しました。
雑踏(ざつとう)をかきわけ、かきわけ松の木の方へ走り
つづけました。
走りながら、両側の店の明かりが、まるでろうそくの灯が風に吹き
消されるように消えてゆくのを知りました。
やっとの思いで、あの松の木にたどりつくと、木の下で
牡鹿は目をとじていました。
ランプを鹿の角にぶらさげて、鹿は走り出しました。
それまで、全速力で走っていた牡鹿が息をひそめてじっと
立すくんでいます。
「鹿が行く、鹿が行く、生きた鹿が行く」とかすれた声でいったのです。
ひと群れの鹿が二十頭くらいです。
最後の一匹が牡鹿に話かけたのです。
「おい、もどってこられないのかい?」
すると牡鹿はうなだれて、
「それができたら、どんなにうれしかろう」
と、言いました。
「そんなら、もう天にのぼるといいよ」
「ああ、本当に、そうしたいと、どんなに思ってるかしれない…」
こんなやりとりが終わると、最後の鹿は、真っ暗な山の中へ
消えていきました。
「あんなにたくさんの鹿、いつたいどこへ行くところだろう・・・・」
ふっと、あやがつぶやくと、牡鹿は、小さく首をふりました。
「どこおだろうなぁ・・・・生きた鹿のすることは、もう忘れてしまった」
そういって、牡鹿が、がっくりと首をたれたとき、角のランプがどさりと
池に落ちたのです。
ガラスのくだける音が響いて、たちまち、あたりは、真っ暗に
なりました。
そのとたん、けものの遠吠え、そのあとから、枯れ木が笑い、
つる草がわめきたて魔物はひゅ-ひゅ-と火吹き竹を吹いて
いるらしいのです。
あやは、震えあがり鹿は飛び上がり、そしてもう、
滅茶苦茶に走りだしたのです。
鹿は、「苦しい思いをして、あんたを、はなれ山へ連れて行ったけれど
わたしは、救われなかったなぁ・・・・」
それから、一年が過ぎました。
一年の間に清十さんの家では、たえもあやも、お嫁に行きました。
末娘のために、清十さんとおかみさんはいい縁談を
さがしていました。
「わたしの相手なら、もう決まっている」とみゆきは言うのでした。
ぽつりぽつりと、話し
「もう、長いこと、暗闇の谷で、たった一人で
泣いている人がいて、その人のところへ、わたしは、行こうと思う。
わたしは、その人を明るいところへ一諸に連れて行ってあげるんだ。
わたしは、小さいときから、そんなふうに思っていた・・・・どうしても、
そんな気がしてならなかた・・・・」
清十さんとおかみさんが、なんど聞き返しても、後は黙って
とんぱたとんぱた、木綿の布を織りつづけるのでした。
やっぱり秋の夕暮れどき。
みゆきは、川の土橋の下で、漬菜をあらっていました。
後ろでふっと、かすかな足音がして、あたたかい息が、
首にかかりました。
そこには、一匹の牡鹿が赤いこもれ陽(び)をあびて、鹿の背は
ビロ-ドのように見えました。
「わたしは、あんたを、はなれ山へつれて行ってみるつもりだ」
これを、聞いて、みゆきは、躍り上がりました。
鹿の背にのっていると、みなれた山の景色の何もかもが、
違って見えるから不思議です。
「ああ、山の木(こ)の葉が、みんな金で、できているみたいだ」
みゆきが、そうさけんで目をあけると、本当に山の木の葉は一枚残らず
本物の金で、できていて、風が吹くたびにぶつかり合って、ちりちり
音を立てるではありませんか。
「夕日が、あんたに贈りものをしているんだよ。早く金の葉をおとり」
みゆきは、三枚の木の葉をふところにしまいました。
鹿は「かすりのいい着物だねぇ」と、言うのです。
「そう。自分で糸をつむいで、、染めて織ってつくったんだもの」
みゆきは、苦心してこしらえた着物をほめられて、得意でした.

「どうやら天気がかわってきたぞ。
ゆきふる ゆきふる いそげやいそげ」
「あんたが、かすりの着物をきてきたからさ。
ゆきふる ゆきふる いそげやいそげ」
そこで、みゆきも、まねをして歌いました。
雪は、わんわんと、風に舞いながら黒い地面に、ほとほと、と
不思議な模様をつくってゆくのでした。
「あ、かすりの模様だ。わたしの着物みたいだねぇ」
歌いながら、みゆきはなんだかもう、楽しくって楽しくって、
このまま空のはてまでとんで行ってもいいと、さえ思いました。
鹿が、どんなに高く飛び上がっても、どんなに遠く飛んでも、楽しい
ばかりでした。
「あんたはいい声しているね」
みゆきは大きくうなずいて、
「歌は得意だもの。歌をうたっていたらこわいものなんか
ひとっつもないもの」
「さあ。市についたよ。のどがかわいたろうから、お酒をのむといい」
松の枝には、頭巾でこしらえた袋がぶらさがっていました。
お酒は、ほんの少ししか残っていません。
みゆきは鹿の口もとで、袋の口をあけて飲ませてやりました
鹿は大きな目をふっとうるませ「わたしの気持ちが、よくわかるんだねぇ」
みゆきは、「わたしは前からあんたを知てたみたいな気がするもの」
鹿はこくこく喉をならして、お酒を飲むと、一口だけ残して
みゆきにわたしました。
「あんたは、わたしのことが、よくわかるんだねぇ」
鹿とみゆきは、じっと目を見合わせました。
「さあ行こう」
みゆきは驚いて大きな声で「あんたも、一諸に行けるの?
ここで待ってないで一諸にいけるの?」
「これでやっと、わたしも天の鹿の仲間になれるんだ」
「わたしのキモを食べた娘に、やっと会えたからさ。
そうして、その娘がわたしに、優しくしてくれたからさ。
山ぶどうのお酒を、半分ずつ一諸に飲んで、道づれになって
くれたからさ。だから、わたしは、長い長いさすらいから救われて、
たった今、天の鹿になれたんだ」
ああ、やっぱりわたしが長いこと待っていた人、わたしの、おむこさんに
なる人は、この鹿だったのだ。むかし、父さんが殺してキモをわたしに
食べさせた、その鹿だったのだ・・・・。
「あんたの、ふところに、金の木の葉が三枚あるので三つ買うといい」
みゆきは、躍り上がりました。
鹿の市の青い灯のなかに、二人は飛び込んでいったのです。
みゆきは、真っ直ぐに、走りながら金の梨を売る店で、
「あれをたべよう」と鹿に呼びかけました。
「一番大きい梨!」と注文しました。
まるで、のぼりたての月のような梨を、皮もむかず食べました。
甘く冷たく、とびきりみずみずしい梨でした。
「ああ、おいしい」
思わず目をつぶったとき、みゆきの耳にまったく聞こえなかった音が、
遠い山並に吹く風の音や、松葉のこすれる音や、三つも四つも向こうの
谷で鳴いている猿の声までが、聞こえるようになったのです。
みゆきは、、梨を半分食べると牡鹿の口におしつけて
「ほら、おあがり」牡鹿は、それはおいしそうに食べたのでした。
そして、最後に、梨の種を、ほろりと口からこぼすと、
「この梨の夢を、わたしはこれまで何度見たかしれない」
みゆきは「おなかもすいているでしょう?きのこの雑炊の夢も
みたでしょう?」と、尋(たず)ねました
「ああ、雑炊の夢なら何度も見た。どれだけ食べたいと
思ったかしれない」
「そんなら行こう、一諸に食べよう」
牡鹿とみゆきは並んで歩きました。
はちまきをした鹿が、赤い大きなおわんを片手に、
大きな鍋のまえで、二人を待っていました。
「おいしい雑炊、一杯で、金貨一枚」
おわんのなかには、山芋、栗、大根、しめじ、まつたけ、しいたけも
入っていました。
その白い湯気が、ふうっと顏にかかったとき、ほのぼのとした幸せの
思いでいっぱいになりました。
赤いおわんを両手にかかえて、雑炊をちょうど半分すすると、みゆきの
体は、まるで厚い毛皮を着たように、あたたかくなりそして、とても
かるくなりました。
手足が、すんなり伸びたような気もして、自分が自分でなくなって
ゆくような気もして、みゆきの耳には遠いふもとの村の猟師の家の
屋根にふりつもる雪の音まで聞こえるのでした。
みゆきは、残りの雑炊を、鹿の口にもっていって、
「ほら、おあがりよ。わたしと半分ずつ」
「おいしいねぇ。からだが、あったまるねぇ。力がでるねぇ」
たべおわって、牡鹿はため息をつきました。
(こんどは、何を買おう)目と目をあわせて、二人は相談しました。
「こんどは花、やさしい花」みゆきが、歌うように答えたとき、
二人の目の前に、白い花の群れがふわりとひろがりました。
「お客さん、一束どうですか」花屋の子鹿の目が笑っていました。
最後の金貨をとりだして、白い枯梗(ききよう)をひとたば買いました。
その花たばを両手にだいたとき、何故かみゆきはほっとして、きゅうに
両足の力がぬけてゆくような気がしました。
「ああ、つかれた」みゆきはその場にすわりこみました。
牡鹿も同じことを言いました。
そうして、みゆきの横にすわると、そのまま倒れこむように、ひざの上に
頭をおとしました。
とろろん とろろん 花嫁さん
白い花抱いて おやすみなさい
あしたの朝の旅立ちまで
静かに静かに おやすみなさい
初雪が、山と畑と、家々の屋根をまっ白にした翌朝、猟師の清十さんは
自分の家のまえに、ぼんやりと立っていました。
きのう谷におりて行ったまま、帰らない末娘、一晩中捜しまわった
あとでした。
不安と悲しみでいっぱいで、自分の家のやぶれた板戸にもたれて
ふっと空をながめたとき・・・・
清十さんは、どきっとしました。

はなれ山の頂から、驚くほどたくさんの雲が、いっせいに湧き上がるのを
見たのです。
その雲は、みんな鹿のかたちをしていました。
何十頭もの鹿がひとかたまりになって、ゆっくりと、、空を走っていくように
見えました。
「おう」思わず、清十さんは両手をあげました。
鹿の群れのなかに、ひとりの娘のかたちを見たからです。
牡鹿の背に乗っているように見えました。
のぼりはじめた太陽をはれやかにあおいでいるようにも見えました。
が、その姿はたちまち、一頭の白い牝鹿のかたちにかわり、
やがて、ほかのたくさんの鹿のかげにかくれてみえなくなりました。
「おう、おう」清十さんは、わけのわからない声を、はりあげて
駆け出しました。
両手をひろげ、流れて行く白い雲を追って、山の道を、
どこまでもどこまでも走って行きました。
《私の感想》
清十さんとおかみさんは、末娘の良い縁談を
さがしていましたが、
.末娘みゆきは
「もう長いこと、くらやみの谷で、たった一人で
泣いている人がいて、その人のところへ、
わたしは行こうと思う。わたしは、その人を、
明るいところへ一諸に連れて行ってあげるんだ。
わたしは、小さいときから、そんなふうに思っていた・・・
どうしても、そんな気がしてならなかった…」
みゆきの心の奥底にはどこかで
鹿のキモとのつながりが運命的にあったように思います。
鹿のキモはみゆきにとっては命だったと思います。
この世の中には、理解できないことが色々と起きて
いるように思います。

安房 直子(あわ なおこ)
1943年 東京生まれ


コメント