
このお話は玖珠(くす)の盆地に巨大な楠がお天道さまをさえぎり、村に陽があたらず、田んぼや畑の作物の育ちが悪く村人が困っていたところから始まります。
《 あらすじ 》
昔昔、あるところに大きな楠(くすのき)がありました。

樹齢(じゅれい)八万年という、天にも届くほどのそれはそれは大きな木だったので、玖珠(くす)の盆地には陽(ひ)があたらず、田んぼや畑の作物の育ちも悪かったのです。
村人たちは、
「あの楠さえなければ、お天道さまの顔が見られるのに」
「なんとか、あの木を切り倒(たお)すことができないものか」
と代る代る楠に斧(おの)を打ち込みましたが、あまりの大きさに、傷をつけることさえできませんでした。
「わしの力では到底(とうてい)無理だ」
「どこかに、この木を倒せる大男はいないのか」
「そうだ。なんでも、木切り別当という木を倒す名人がいるという話を聞いたことがある。身の丈は山ほどもあって、大きなまさかりを持っているそうだ」
「よし、その男に頼もう」
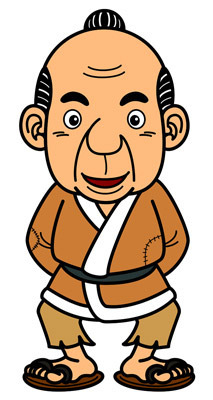
早速、村の頭(かしら)が別当に会いに行きました。
頭は、山のように大きな別当を見上げて言いました。
「お-い別当殿、どんな木でも切り倒せるというお前さまに、頼みがある。わしらの村のとてつもなく大きな楠が、お天道さまを隠(かく)してしまって、みんな困っとる。どうか、その木を倒してくれないか」
「ほう、そんなに大きいのか」
「ああ、樹齢は八万年。天にも届くほどの、大きな楠だ。どうだ、できるか」
すると別当は、畳百畳分(たたみひやくじょうぶん)もある大きなまさかりを肩に担(かつ)いで笑いました。
「このおれに倒せない木はない。案内しろ」
別当は頭を肩にちょんと乗せると、頭が三日かかった道のりを、三またぎ、
「ほっ、ほっ、ほっ」
と、あっという間に行きつきました。
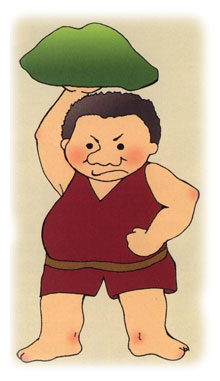
「別当殿、あの木だ」
さすがの別当でも、見上げるほどの楠の大木に驚きました。
「倒せるか、別当殿」
「そうだな。できるにはできるが、三年はかかりそうだ」
「何年かかってもいい。どうにかして、村に陽をあてて欲しいのだ。頼んだぞ」
「よーし、わかった」
別当は大きなまさかりを振り上げて、打ち込み始めました。
ゴキ-ン、ゴキ-ン、傷は、少しずつ少しずつ大きくなって、日が暮れるころには、切りくずが小山ほどになりました。
「よーし、今日はここまでだ」
と別当は近くの山を枕にして眠りに就きました。

ところが翌朝、別当がまさかりを担いで楠にむかうと、どうしたことか、昨日の切り口も、切りくずも見当たりません。
夜のうちに、すっかり元に戻ってしまったようです。
次の日も、次の日も同じでした。
さすがの別当も、
「これでは切り倒せない」
と、あきらめかけたその夜、枕元で小さな声が聞こえました。
「私があなたに、この楠をきり倒す方法を教えましょう」
別当はびっくりして飛び起きましたが、誰もいません。
すると、どこからかまた、小さな声だけが聞こえてきました。

「私は、ヘクソカズラの精(せい)です。何万年もの間、この楠から栄養をもらって生きて参りました。そのお礼として、楠が傷つけられたり、虫に食われたりしたら、私の汁を出して、傷口を治してやっていたのです。ところがこの大きな楠は、私の汁が臭(くさ)いと言って、嫌(いや)がるようになりました。楠のあまりの態度に、私は腹を立てているところです。
この楠を切り倒すのは、簡単なことです。切り口から出た木のくずを、その日のうちに焼き捨ててください」
そう言うと、それきり小さな声はしなくなりました。
翌日、別当はヘクソカズラの精の言ったとおり、その日の仕事を終えると、すぐに切りくずを集めて焼き捨てました。
それからというもの、楠の切り口がふさがることはなくなり、切り口は、少しずつ少しずつ広がっていきました。
そして三年三ヶ月経ったある日、とうとう楠はドドド-ンと大きな音を立てて倒れました。
こうして、村には陽があたるようになり、作物もよくできて、村人たちの暮らしは豊かになりました。そのときの楠の切り株が、今の伐株山(きりかぶざん)だと言われ、その名のとおり、切り株のかたちをしているそうです。

《 わたしの感想 》
ヘクソカズラは、やぶや道端など夏を中心にいたる所に生えている雑草です。
普段は、見下されていたヘクソカズラの精が知恵を授け、木くずを焼くことで木を倒すことができたという展開は、小さなお花にも大きな力があるということを感じさせられました。
切り倒された楠の切り株が現在の伐株山です。
(玖珠)という地名の由来にもなっています。
物語りは、ロマンを感じます。



コメント