
誰の心の奥底にもある、残忍性と禁断―。
それは理性の力でどんなに蓋(ふた)をしようとしても、
隙間(すきま)から漏(も)れ出し、生き延びてしまう…..。
昔ばなしに隠された「意外な真実」
日本の昔ばなしに,
しばしば登場する子殺しや子捨て、
それに継子(ままこ)いじめや、
山姥(やまんば)の子ども食いの話。
その他にも、さらりと語られているので見過ごしがちですが、
人間の本性の暗い面を、炙(あぶ)り出すような話が
たくさんあります。
大人になった今、改めて原典にあたってみると、
懐かしさより、恐ろしさを覚え、残忍さや狂気といった
残酷なイメ-ジがあふれているのに驚かされます。

《あらすじ》
「手なし娘」
昼さがりのことだった。
突然、、降って湧(わ)いたように娘の縁談が舞い込んできた。
相手というのは美濃(みの)の国の、(さんぜんさ)という長者の
跡取り息子だった。
資産家の息子には珍しく、商いだけでなく何事にも積極的で
その上、性格もいいという。
自分に見合った人は、やはり自分で見つけるしかないと考え、
嫁探しの旅に出た。
しかし、なかなかよい人に巡り合えず、諦めかけていた頃、
「大坂の鴻池(こうのいけ)に素晴らしく評判のよい姉妹がいる。
二人とも甲乙つけがたい器量よしだ」
という話を耳にした。

飛び上がって喜び、若い衆を一人連れて、一目散に鴻池に駆け付けた。
そして呉服屋を装い、二日三日と、姉妹の立ち居振る舞いを飽きもせずに
眺め続けた。
その結果、嫁にするのは姉娘のほうと心に決め、
美濃に戻って、正式に縁談の使者を出したのだという。
妻の長い夜が始まった。
彼女は小さな娘を連れて、夫に嫁いできた頃を思い出す。
夫は、呉服屋の小商いをいとなんでおり
自分と同じように娘がいた。
幼い二人の娘は互いに遊び、友だちができたといって喜び、
父親にも母親にも親しんだ。
暮らし向きは、かつかつというほどではなかったが、下の娘には
いつも姉のお下がりで,がまんさせた。
そこには夫への遠慮もあったが、何かにつけて上の娘を優先した。
夫はそんな気苦労に気づいていない様子だった。
(あの人は、あたしたちを大事にしてくれたけれど….
.何もわかっちゃいない…..)

妹は、姉と同じに鴻池でも評判の、器量よしに育った。
彼女にとって、自分の生んだ娘こそ
(美濃に嫁ぐにふさわしいのは、あたしの生んだ娘だ!)
彼女は恐ろしい力に打ちひしがれた。
妻は「あの娘はもう美濃に行ってしまうんだから、遊び友だちを
呼んで、別れぶるまいをしてやろうと思うんだけど…..」
夫は妻の娘への気づかいがうれしかった。
別れぶるまいの日、夫は商用で鴻池を空けていた。
その翌日のことだった。
「ねえ、あんた。こんなことは言いづらいんだけど、あの子はとても
嫁には出せないよ。きのう、とんでもないことをしたんだ…..」
「あの子はとても嬉しがって……友だちとはしゃいで遊んで…..」
娘は腰巻もつけないで、裸で踊り出したと妻は言った。
父親は俄(にわか)に信じられなかった。
気が遠くなりそうだった。
父親はこの十数年の幸せが一挙に崩れ去っていく思いを
味わっていた。
そんな娘を嫁に出せば、いっそう噂(うわさ)が広まり、
鴻池の誰も可も、好奇の目が注がれるに違いない。
夫は、妻の心が自分から離れてしまうことなどを、考えるのも
恐ろしかった。

夫は、
「そんな娘は嫁にやれんぞ」
と弱々しい声で呟(つぶや)くように言った。
すると、妻はすかさず
「それなら、今すぐ山へつれていって殺してちょうだい」
娘は裏山に父親と一諸に登った。
父親は、いきなり娘に飛びつき押さえ込むと、
懐(ふところ)に隠し持っていた出刃で
実の娘の両手を斬り落とした。
両手を失った娘を谷底へ突き落とした。
帰ってきた夫から、話を聞いた妻は薄笑いを浮かべて言った。
「しかたないよ、あんた。飢饉(ききん)で間引きすることだって
あるんだし」
女の目は蛇眼(じやがん)のような光をたたえていた。
あくる日。
妻は美濃の
「さんぜんさ」
に手紙を書いた。
「本当に申し訳ないことですが、上の娘は病気で死んでしまいました。
ついては妹娘を嫁にもろうてはくれませぬか。
姉娘も浮かばれると思います。」
しかし美濃の国からは届いた返書は、妹娘と祝言(しゅうげん)を
あげる気はしないというものだった。
母親は地団駄(じだんだ)を踏んで悔しがった。

姉娘は生きていた。
両手をもがれたうえ、谷川に落とされたのだが、
行きたい一心で、川から這(は)い上がっていた。
娘は、父親の豹変(ひょうへん)をいくら考えても、
父親の仕打ちの理由がわからない。
娘は、自分の現実を抱きしめて生きて、いこうと心に誓った。
すると、せめて自分を気にいって嫁にしたいと言った
人の顏を見てみたくなった。
意を決し「さんぜんさ」を訪ねていくことにした。
道中、手なし娘は好奇の目で見られた。
そのたびに、自分を好いてくれた、お人がいる
と思うと苦にならなかった。
目指す屋敷が見つかった。
たいそう立派な門構えだった。
門の脇には枝振りのいい、柿の木がたわわに実をつけている。
道中ろくに食べ物を口にして居なかった手なし娘は思わず……、
両手のない自分を目の当たりにするのだった。
精一杯、背伸びをして、口をつけて食べるしか方法はなかった。
夢中で手なし娘は貪り(むさぼ)り食った。
屋敷の大旦那が見ていて、何か訳ありと踏んだ大旦那に
うながさるまま、
手なし娘はこれまでの経緯(いきさつ)を語った。
「ならば、おまえさんは病でしんだという鴻池の娘さん?
そうとわかれば、うちの嫁と決まった。手なぞなくてもよろしい、息子の嫁になっておくれ」
上の娘は死んだと聞かされて、ふさぎ込んでいた跡取り息子も喜んだ。
こうして、手なし娘は嫁入りするのだった。

ある年のある日。
手なし娘は玉のような男の子を生んだ。
あいにく、若旦那は商用で九州に行っており留守だった。
大旦那はさっそく男子誕生の知らせを書き記し、
若い衆を飛脚に仕立てた。
事情を知らない若い衆は、途中、
若嫁の里、大阪は鴻池に立ち寄った。
話を聞いて驚いたの継母だった。
若い衆を酔いつぶして、九州に届ける手紙を盗み読んだ。
(玉のような男の子がうまれた。名前はなんとしょう)
継母は、むらむらと娘に増悪の炎がもえあがってくる。
継母は、手紙の書きかえを思いつき、こう書いた。
(鬼のような子が生まれてしまった。あんな恐ろしい嫁は家から出す
のがよいだろう)
書き終えた継母の双眸(そうぼう)には怪しい光が宿っていた。

それから、半年も経(へ)たない頃だった。
飛脚役の若い衆が酒を目当てで立ち寄っている。
言葉巧みに酔いつぶしてしまった。
継母は、美濃あての書きつけを懐(ふところ)から抜き出した。
(いくら鬼のような赤子でも、おれの子だ。嫁は家からださずにおいてくれ)
とあった。
継母は性懲(しょうこ)りもなく再び細工をした。
(そんな鬼のような赤子を生む嫁は、おれの嫁ではない。
すぐに追い出してくれ)と。
翌朝、若い衆は、書き換えられた書きつけを懐に、美濃に走った。
両親は、若衆から息子への返事を受け取って読むと、
さかんに首を捻(ひね)った。
息子の言うことがさっぱりわからない。
若い衆は、どこにも寄らずに住還するように厳命されていただけに、
鴻池に寄って酔いつぶれた話などできない。

一晩中、考えあぐねた大旦那は、息子の言うことに従うことにした。
手なし娘は返す言葉がなかった。
(私の生んだ子が鬼だなんて……ならば、私も鬼?)
しまいには、気がふれんばかりに思いつめていた。
手なし娘は背中に乳のみ子を負って、あてのない一歩を屋敷の
門から踏み出した。
舅(しゅうと)が持たせてくれた、過分な銭がせめてものなぐさめだった。
歩き出した手なし娘は、喉(のど)の渇きに苦しんだ。
背中の子の喉の渇きに、自分はどのようにしたらいいのだろう。
手なし娘は初めて、自分のおかれている立場を哀れに思った。
とめどなく涙が頬(ほほ)を伝った。
川の流れが手なし娘の目に飛び込んできた。
川端には地蔵も立っている。
手なし娘は思わず、仏様―と心の中で手を合わせていた。
手なし娘は転ばないっようにバランスをとりながら、
夢中で駆け足で寄った。
そして、勢いよく川端に跪(ひざまず)き、口をつけて飲もうとしたときだった。
背中の子があっというまに、ずり落ちたのだった。
(子が川に落ちる!)
手を、と思った瞬間だった。
ずらっと手なし娘の二の腕から手が生えて、子を押さえたのだった。
右の手も左のても生えそろっている。
娘は自分の手でしっかりと子を抱きしめた。
その感触は、えもいわれるほどの心地よさだった。
これでこの子と二人、なんとか生きていけると我にかえったときだった。
ふと見ると、さっきまであった地蔵の手がなくなっている。
(…..! この地蔵様が、私に手を投げてくださったのか)
(そうだ、私には銭がたくさんある。ここに小屋を建てて、地蔵様を
お守りしながら、子と生きていこう)
娘の建てた小屋は茶屋を兼ね、かつかつの暮らし向きだったが、
地蔵に見守られ、母と子は生き始めた。
ある年のことだった。
商用で九州に長逗留(ながとうりゅう)していた、
美濃の(さんぜんさ)の息子が屋敷に帰ってきた。
息子は、家に嫁も子もいないのに驚き
「俺の嫁はどうした、子はどこにいるんだ?」
と、かつて見せたことのない剣幕で親に詰め寄った。
親子は互いの手紙の内容を知って、愕然(がくぜん)とするのだった。
若い衆を呼び調べていくうちに、娘の継母の仕業(しわざ)だと悟った。
息子の怒りはおさまらなかった。
手なし嫁への愛しさが強烈にこみ上げてくる。
息子は屋敷中の者を四方八方に走らせた。
自らも嫁さがしに走った。
三日めのことだった。
隣村との境目に立つ、川端の地蔵のそばに、
ちいさな茶屋がでているのに気づいた。
歩き疲れた息子は足を止め、茶屋に入った。
すると、年のころ、三つばかりの男の子が駆け寄ってくる。
男の子は
「父さん、父さん」
と声を立てる。
「お客様にご迷惑でしょう。その方はよそ様の父様ですよ」
奥から声をかけながら顏をのぞかせた女を見て、
息子はわが目を疑った。
探し求めている嫁に瓜二つだった。
(…..でも手がある。ちゃんとあるからなあ…..)
世の中にはこんなにも顔立ちの似ている人がいるものなのだと
呆然とするのだった。
しかし、あまりに男の子がなつくので女に聞いてみた。
「お前さん、いつからここに茶屋を出しているんだい」
優しく問いかけられた女は、初めて正面からじっと男を見た。
(…..!)
女はまさかと思った。信じられなかった。
三年の月日は長くはなかった。
女は夢中で生きてきた。
気づいてみればそれだけの時間が流れていたにすぎない。
女の頬に、屋敷を出て三度目の、大粒の涙がこぼれだしていた。

《私の感想》
【手なし娘】は、人間がある状況におかれたときに無意識のうちに
(残酷さ)(醜悪さ)がでるものだと思います。
この物語に登場する夫婦は
連れ子(娘)のいる同士で再婚した男と女。
その娘は継子いじめにあうこともなく、
町での評判の、誰にでも好かれる、素直で気立てのよい、
器量よしの姉妹に育ちます。
でも、娘の縁談から(残酷さ)(醜悪さ)がでます。
望んでも、望めないような金持ちの良い縁談です。
継母は、自分の娘こそ、この相手とふさわしいと思います。
そうなると、夫の実の娘が邪魔になります。
邪魔になると、憎しみも湧き嫉妬もでます。
今まで夫と娘の仲のよさも、何もかも嫉妬します。
自分のために、何でもしてくれて当然という思い込みもでて
残忍の要求もしてしまいます。
夫は妻への愛が強いため、妻を失いたくないという思いで
実の娘を殺せという理不尽な要求を実行してしまう
(残酷さ)(醜悪さ)です。
私は、ここまでいかなくっても、大なり小なり
誰にでも心の中に潜んでいると思います。
でも、理性がそれを押さえていると思います。
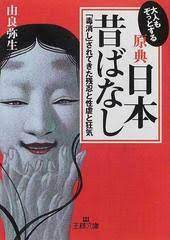

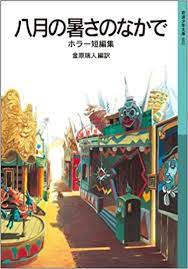
コメント