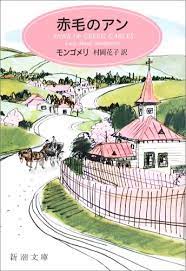
赤毛のアンの世界は、大人になってもたっぷり楽しめる作品です。
今とは違って、何をするにも時間がかかり手間もかかりますけど、
その分すべてが愛おしくなるものです。
★④赤毛のアンという女の子
(思いあらたに・アン看護に走る)
アンは、唇を真一文字にひきむすび、強い決意をしめて、教科書の入った
バスケットをかかえ、、びっくりしているマリラに
「わたし学校にもどろうと思うの、マリラ。心の友と無残に引き裂かれた今、
わたしの人生に残っているのは、学校以外にないんですもの。」
学校ではみんながあたたかく迎えてくれました。
ただ、残念なのは、ダイアナと話すことが出来ず、手紙を書いて渡すことしか
できなかったことでした。
すべてこの世の大きな出来事は、小さな出来事に関係があるものです。
カナダ首相某氏(しゅしょうぼうし)がプリンス・エドワ-ド島を
政治演説旅行に加えたことは、アンの運命とのかかわりがないようで、
また、あるようで。
首相がシャ-ロットタウンの大演説会に、あらわれたのは一月でした。
アンポリ-の人々は、たいていがこの首相の政党を支持していましたから、
ほとんどの男と女が、どっとばかり、五十キロ離れたこの町に出かけて
行きました。
レイチェル・リンド夫人は、自分がいなければ政治集会は開けないと、
信じているほどの政治好きですから、夫のトマスに馬車をしたてさせて
駆け付けました。

マリラもこっそり政治に興味を、もっていましたし、このチャンスを逃したら
二度と本物にお目にかかることはないと思いましたので、二つ返事で馬車に
飛乗りました。
そしてアンとマツシュ-に、翌日戻るまでの留守番を頼んだのです。
その夜アンとマシュ-はグリン・ケ-ブルズで気持ちのいい台所で
向かい合って食事を、おえてアンは地下室からリンゴを皿いっぱい
もってきた、丁度そのとき、次の瞬間勢いよく戸が開いて飛び込んで
きたのはダイアナが、ショ-ルを首から頭に巻きつけ、真っ青な顏をして
息を切らせているのです。
アンはびっくりして、皿もりんごも落としてしまいました。
ダイアナはもう、ほとんど泣き声でした。
「ミニ-・メイが酷くわるいの。お父さんもお母さんも留守でお医者さまを、
呼びにいってくれる人が誰もいないのよ。メアリ-・ジョ-は喉頭炎(こうとうえん)
らしいと、いうけれど手当が出来ないし,どうしていいか分からないの。
アン、ああ、もうわたし駄目だわ。」
マシュ-は黙って帽子と上着をとると、カ-モディ-にお医者さまを
迎えに馬車で出かけました。
アンは、「泣くことないわ、ダイアナ」力強い声で言いました。
「喉頭炎の手当なら、わたしよく知っているから。ハモンドのおばさんが、
双子を三度もうんだのよ。かわりばんこに喉頭炎になるんだから、いい加減
色んなことを覚えるわよ。イピカックの瓶を持っていくからね。お宅には
ないかもしれないからね。さあ、いきましょう。」
アンは、もちろんミニ-・メイのことはたいそう気が、かりでしたが
この夜のロマンチックな雪景色を素晴らしいと思わずにはいられませんでした。
そしてその素晴らしさを、もう一度懐かしい親友と分け合うことが出来たことが
いっそう嬉しかったのです。

三つになるミニ-・メイは本当に酷い病状でした。
台所のソファに寝かされた体は燃えるような熱で、苦しそうに耐えず身を
動かしています。
激しい息づかいは家じゅうに響きわたっていました。
メアリ-・ジョ-は若いフランス娘で、バーリ-夫人が留守の間子どもたちを
見てもらうために雇ったのですがこのような病気に出会っては、おろおろする
ばかりでした。
アンは直ぐ仕事にかかりました。
「ミニ-・メイは確かに喉頭炎だわ。そうとう悪いけれど、もっと酷いのを
看護したことがあるから。うんとお湯を沸かさなくっちゃ。メアリ-・ジョ-、
そのスト-ブ-にまきを入れて頂戴。メアリ-・ジョ-の気分を壊したく
ないけれどこのくらいのこと想像力があれば気がつくことじゃない。
さあ、わたしこれからミニ-・メイの服を脱がせてベッドに寝かせるから、
ダイアナ、フランネルの柔らかい着物を探してきてくれない。わたし、
とに角まずは、イピカックを飲ませるから。」

ミニ-・メイはイピカックを飲むのを嫌がりましたが、アンは無駄に三組の
双子を育てたわけではありません。何度も何度も、幼いミニ-・メイの喉を
薬がとおっていき二人の少女はかわいそうな女の子を
一晩中見守ったのです。
その間、メアリ-・ジョ-は出来るだけのことをしょうと、夢中になって火をたき
喉頭炎の小児病院一つでも間に合いそうなほど、お湯を沸かしました。
マシュ-が医者を連れて戻ったのは夜中の三時でした。
このときには、もう一番危険な峠は乗り切っていたようでした。
ミニ-・メイはかなりらくになったようで、ぐっすり眠りこんでいました。

アンは「一時は、もういけないかと思いました。今にも窒息して死ぬんじゃないかと
思いました。イピカックを一瓶飲ませて、最後の一回分になったとき、
ダイアナとメアリ-・ジョ-には心配させたくなかったので黙っていました。
けれど、本当は自分にこういいましたのよ。《これが最後の頼みの綱だけれど
なんだかおぼつかないわねぇ。》
けれども、飲ませて三分もすると、たんをはきだして、それからぐんぐんよくなった
のです。わたし、どんなにほっとしたことか、先生ちょっと想像してみてくださらない?
口じゃとても説明できませんもの。あの、言葉で説明できないものって
この世の中にあるでしょ?」
「そうだね。そうだとも。」と、医者はうなずきました。
医者は、喋りまくる目の前の少女を、深く考え込むような目つきで、 見つめて
いましたが医者も、また自分のことを、どう言葉にあらわしたらよいか分からない
ようすでした。
けれど、後になって医者はバーリ-夫妻に
「あのカスバ-ト家にいる赤毛の娘は、おそろしく利口な子ですね。
はっきり申し上げて、赤ちゃんの命を救ったのはあの子ですよ。
わたしが、お宅に着いたときには手遅れになっていたはずですからね。
あの年の子どもとしては、大した腕と落ち着きようというべきですな。
あの、わたしに病状を説明したときの、あの子の目の色。
ちょっと見たことがありませんなあ、ああいうのは。」
アンが、グリーン・ゲイブルズに向かったのは何もかも真っ白に氷ついた
冬の朝が明けそめたころでした。

寝不足の重い目をしていましたが、アンは元気いっぱいでした。
マシュ-は「とに角、直ぐベッドに入って、ぐっすり眠りなさい。
あとの細かいことはわしが、やっておくからな。」
アンは二階の寝室に行き、ぐっすりと長い間眠りました。
目が覚めたのは冬のバラ色の日差しが差し込む午後でした。
台所に行くとマリラが編み物をしていました。

「お帰りなさい。マリラ首相の顏見た?どんな顏の人?」
「あの顏だけで首相になるってわけにはいかなかったろうねぇ。
たいそうな鼻だよ。だけど、演説はたいしたものだ。
わたしゃ保守党なのがほこらしかった。
あんたの食事は、そのオーブンの中に入っているよ。
それから戸棚の中からスモモの砂糖漬けを出しておあがり。
おなか、すいているんだろ。夕べのこと、マシュ-から聞きましたよ。
おまえが看護の仕方を知っていて、本当によかった。
わたしは、喉頭炎の子どもなんて見たことがないんだからねぇ。
アン、食事がおわるまで喋らなっくてもよろしい。大丈夫、話は
くさりはしないからね。」
マリラ自身、まだアンに話すことがあるのでしたが、今直ぐ話したらアンが
興奮して食事も何も出来なくなるだろうと思って食べおわるのを待っていました。

「実は、アン、バーリ-の奥さんが午後にみえてね、あんたに会いたいって
いいなすったけれど、あんたを起こすのはやめたんだよ。奥さんはね、
あんたがミニ-・メイの命を救ってくれたのだ、スグリ酒のことでは、あんたに
気の毒なことをして本当にすまなかったと、いっていなさった。
今になって、あんたがダイアナを酔わせるつもりなどがなかったことがよく分かった。
今までのことは許して、もう一度ダイアナと仲の良い友だちになっておくれ、とね。
ダイアナは夕べ酷い風邪をひいて、今日は家にこもりきりだそうだから。
これ、アン・シャリ-、お願いだから落ち着きなさい。」
マリラが言いおわらなぬうちにアンは飛び上がり、顏は輝き、全身喜びのために
爆発しそうなようすでした。

「ねえ、マリラ。今直ぐ行っていい?このお皿洗わずに?帰ったら直ぐ洗うから。
だってこんなに嬉しくって、わくわくしているとき、お皿なんかとても
洗っていられないんですもの。」
「いいとも、いいとも。さ、いっておいで。」
マリラは甘い声で言いました。
「これ、アン・シャリ-、どうしたの、気でも狂ったのかい。
もどって何か着ていかなくっちゃ。まあ、まあ、風にむかって喋っている
ようなものだ。帽子もえり巻きもしないでいっちまったよ。
あの髪をなびかせて果樹園畑をぬけていくようすったら、
風邪でもひかなければいいけれど。」
今回の登場人物
●ミニ・メイ(ダイアナの妹)
●メアリ-・ジョ-(バーリ-家のお手伝い・若いフランス娘)
●お医者さま
★⑤赤毛のアンという女の子
(さいわいうすき白ゆり姫)
次回もよろしくお願いいたします。
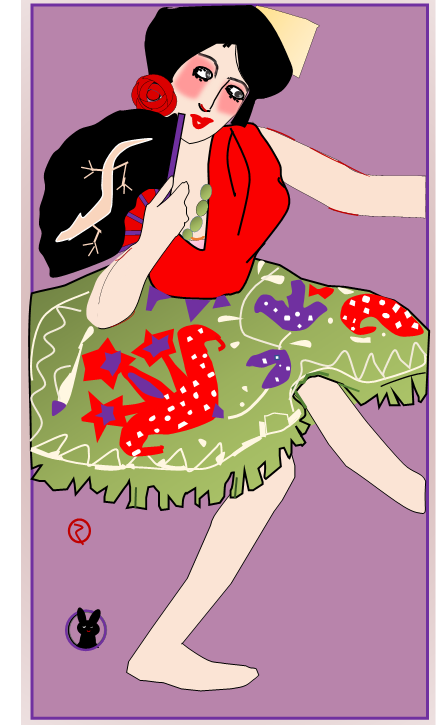

コメント