ホラ-であってホラ-ではない
サキの作品。
ストレ-トな怖さではないが、
作品の巧さは、たまりません
サキの作品のテクニックの巧さに
脱帽です。
神経衰弱の病状を診てもらうために
サプルトン夫人を訪れたフラントン。
通された部屋の窓は、
外が寒いのにもかかわらず、
開け放たれていた。
夫人はいつもこの部屋の窓から、
死んだ夫が帰ってくることを、信じているのだという……..。
《あらすじ》
「ナッテルさん、おばさんはすぐにやって来ると思います」
妙(みょう)に落ち着いた感じの十五歳の女の子が言った。
「それまで、わたしがお相手をしてもいい?」
フラントン・ナッテルは言葉につまってしまった。
この女の子に気に入ってもらえて、
「すぐにやってくる」
という、おばを軽(かろ)んじないような
返事が浮かんでこなかったのだ。
そもそも、会ったこともない親戚を、
一軒一軒訪(たず)ねてまわることが、
自分の神経症にいいのかどうか不安定だったのだが、
その不安もつのってきた。
「だいたい予想はつくわ」
フラントンの姉はそういった。
フラントンがこの田舎の村に住む準備をしていたときのことだ。
「あんなさびしいところにひとりで暮らして、
話し相手もいなかったら、
いよいよ落ち込むには目にみえているもの。
知っている人がいるから、紹介状を書いてあげる。
いまでも覚えてるけれど、何人かはとても親切だったわ」
フラントンは、サブルトン夫人、
つまり姉の紹介状をこれから渡そうと思っている相手が、
その親切な人のなかに入っていればいいがと思った。
「このあたりに知り合いはたくさん?」
女の子がたずねた。
フラントンが黙ったままなのを見て、
そろそろ声をかけてもいいと思ったらしい。
「いや、ひとりも。姉が教会でしばらく暮らしたことがあってね。
四年ほど前かな。
それで、ここの人たちに紹介状を書いてくれたんだ」
フラントンは最後のところを、あんなもの書いてくれなかったらよかったのに、
といわんばかり口調でいった。
「じゃあ、おばさんのことは何も知らないのね?」
落ち着いた感じの女の子がきいた。
「名前と住所くらいかな」
フラントンは、サプルトン夫人の夫が
生きているのか、死んでいるのかさえ知らなかった。
この部屋の雰囲気はなんとなく男性的な感じが強かった。
「おばさんは、とても悲しい事件を経験したの。
ちょうど三年前だから、お姉さんがお帰りになったあとよ」
「とても悲しい事件?」
フラントンには、こんな平和な村でそんな事件が起こるとは
とても思えなかった。
「そこの窓を開け放しているの、不思議だと思わない?
だって、十月だし、もう夕方だし」
女の子は床までる大きな窓を指さいていった。
その向こうは芝生(しばふ)だ。
「あの窓から、ちょうど三年前の今日、
おじさんがおばさんの二人の弟を連れて、
いつもの狩りに出かけたの。
そしてそのままもどって来なかった。
野原を突(つ)っ切って、いつもの猟場(りょうば)に
シギ撃(う)ちいく途中、草木で見分けがつかなくなっていた沼にのみこまれて
三人ともおぼれ死んでしまったの。
あの年の夏は驚くほどよく雨が降ったから、
ほかの年なら危(あぶ)なくもなんともないところが
いきなり深い沼になってしまって。
結局、死体はみつからなかった。
そのせいでとても恐ろしいことになったの」
そういうと、女の子はそれまでの落ち着きをなくして、
悲しそうにとぎれとぎれに話すようになった。
「かわいそうに、おばさんたら、みんなはいつか帰ってくる、
三人と一緒に沼に沈(しず)んだ
小型の茶色のスパニエル犬も一緒に、
以前みたいにあの窓から飛び込んでいるの。
だから、夕方になるとあの窓はいつも開け放して、
暗くなるまであのまま。
おばさんは良く私に、三人が出かけたときのことを話してくれる。
おじさんは白い防水のコートを肩にかけて、下の弟のロニ-おじさんは
『パーテイ、どうしてそんなに飛びはねる?』
を歌って、いつものようにおばさんをからかいながら。
おばさんはその歌を聞くといつもいらいらするの。
ときどき、
こんな静かで穏(おだ)やかな晩(ばん)、ぞくっとすることがあるの。
三人があの窓からもどってくるんじゃないかって・・・・・」
女の子は身ぶるいして口をつぐんだ。
そのときフラントンがほっとしたことに、おばが部屋に駆(か)け込んできて、
「遅くなってごめんなさい」
とあやまった。
「ヴェラはちゃんとお相手ができましたか?」
おばがたずねた。
「ええ、とても興味深い話を聞かせてもらいました」
「あの窓、開けたままでごめんなさいね」
サプルトン夫人がにこやかに言った。
「夫と二人の弟が狩りからもどってくるんですよ、いつもそこから。
今日は沼地の方にシギを撃(う)ちにいってるんです。
だから、カーペットが泥(どろ)だらけになっちゃうわ。
男の人って、みんなそんなもんでしょ?」
サプルトン夫人は陽気に狩りのことを話した。
最近は獲物(えもの)の鳥が少なくなったとか、
冬になるとカモがとれるとか。
フラントンはぞっとして、何とかもう少しましな方向に話題を変えようとしたが、
うまくいかなかった。
そしてサプルトン夫人はというと、フラントンの方などほとんどみもしないで、
フラントンの後ろにある窓とその向こうの芝生(しばふ)ばかりみつめている。
フラントンは、よりによって悲劇のあったこの日に、ここにやってきた
不運を、うらむばかりだった。
「何人もの医者から、安静にして、興奮(こうふん)しないようにして、
激しい運動を避(さ)けるようにと口をそろえていわれているんです」
フラントンは言った。
フラントンは世間の誤解を信じこんで、赤の他人や、たまたま出会った人は、
相手の病気や体の不調や、その原因や治療法の話をすれば耳を傾けると
思っていたのだ。
「ただ、どんなものを食べればいいかという点については
意見が一致しないんですよ」
「あら、そう?」
サプルトン夫人は、どうでもよさそうな調子で答えてあくびをした。
そのとき、はっとして注意を向けた・・・・・のは、
フラントンの話にではなかった。
「やっともどってきた!」
夫人は大きな声をあげた。
「ちょうど夕食の時間に間に合うわ。本当に、頭で泥だらけなんだから!」
フラントンは身ぶるいすると、
かわいそうに、このことだったんだねという顏で
姪(めい)の方を見た。
ところが窓の外を見つめる女の子の目には信じられないと
言わんばかりの恐怖がうかんでいた。
椅子(いす)に座(すわ)っていたフラントンは
氷水を浴びたようなショックを感じ、
体をぐるっと回して、そちらを見た。
濃くなってくる夕闇(ゆうやみ)のなかを、
三人の男が窓の方に歩いてくる。
三人とも腕(うで)に猟銃(りょうじゅう)を抱(かか)え、
そのうちのひとりは、白いコートを肩にかけている。
息を切らせたスパニエル犬が、三人のすぐ後ろをやってくる。
最初はなにも聞こえなかったが、
やがてしゃがれ声が薄闇(うすやみ)の中から
響(ひび)いてきた。
『バーティ、どうしてそんなに飛びはねる?』
フラントンはステッキと帽子をひっつかんで飛び出した。
玄関のドアも、砂利(じゃり)の私道も、門もほとんど目に入らない。
自転車で通りかかった人が、ぶつかりそうになって
生(い)け垣(がき)に突っこんだ。
「おおい、もどったぞ」
白いコートを肩にかけた男が窓から入ってきた。
「泥だらけだが、おおかた乾(かわ)いているからな。
ところで、おれたちが帰ってくる直前
とびだしてったやつは何者だ?」
「変な人。確かナッテルさんとかいってたかしら」
サプルトン夫人が答えた。
「病気のことをちょっと話しただけで、
さようならとも、失礼しましたともいわずに
駆(か)けだしていっちゃった。
ちょうどあなたがもどってきたときよ。まるで幽霊でもみたような顏をしていたわ」
「スパニエル犬のせいじゃないかしら」
女の子が平気な顔で言った。
「あの人、犬が大嫌いなんですって。一度、ガンジス川の岸で野良犬に追い
かけられて墓地かどこかに逃げ込んだことがあるらしいの。
それでひと晩じゅう、堀(ほ)ったばかりの墓穴に隠れてたんですって。
上の方では犬が吠(ほ)えたり、うなったり、
泡(あわ)のまじったつばを、たらしたりしてたっていうから、
怖(こわ)くってたまらなかったのも無理はないわ」
女の子は作り話がとても上手だった。
《私の感想》
本当に、妙に落ち着いた15歳の少女。
ひたすら、煽り続けるを、繰り返します。
ときに、フラントン・ナッテルは感情を
注ぎ込まれてしまいます。
最後の一行がすべて謎を解き明かしてくれます。
(女の子は作り話がとても上手だった。)
ホラ-ではなく、コントみたいです。
サキ(1870-1916)
第一次世界大戦に従軍
フランスで没する。
英国スコットランドの小説家
本名
ヘクタ-・ヒュ-・マンロ-
ペンネームの≪サキ》は
オマル・ハイヤ-ムの詩集
≪ルバイヤ-ト》の酒姫
[酌≪しゃく)をする美少年]
に由来するという。















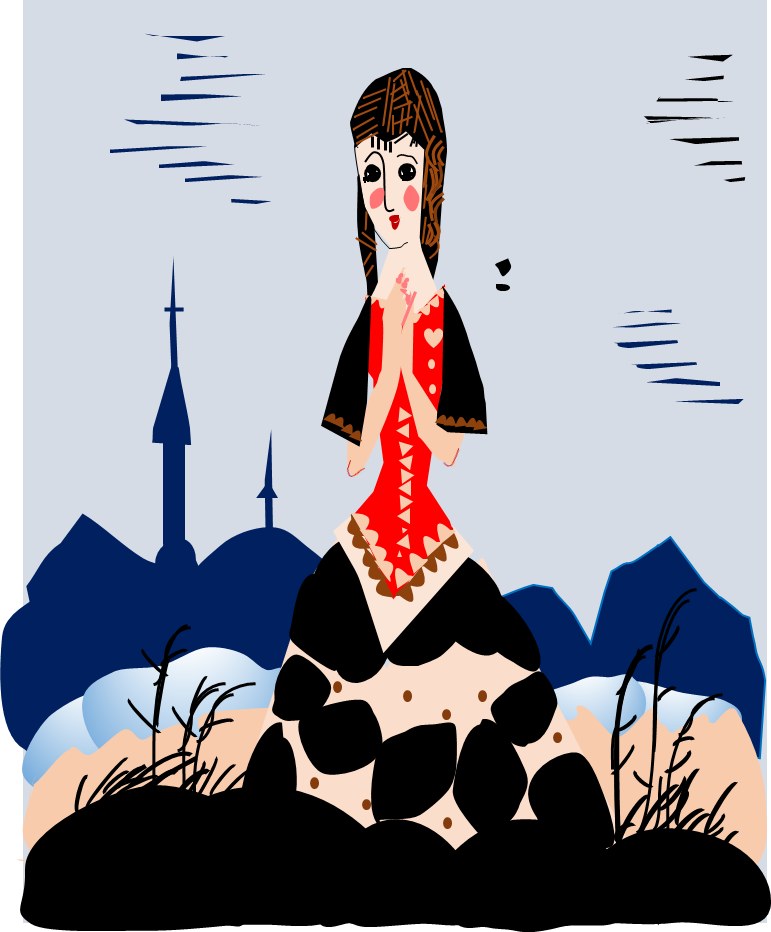
コメント