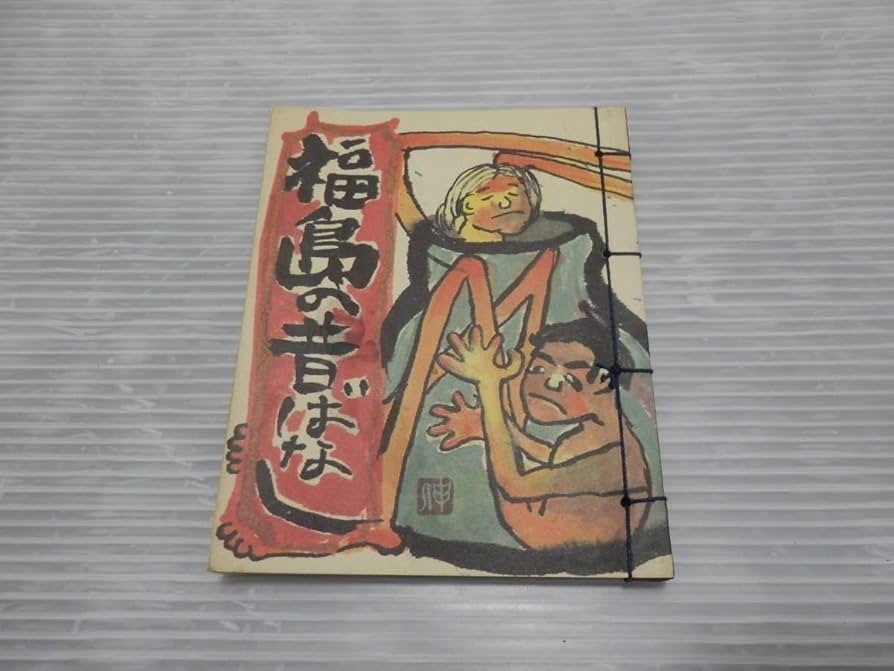

【貧乏神】(福島県)
【貧乏神】の昔話は、各地に伝わっています。
福島県の物語は、特に魅力的です。
多くの場合【貧乏神】は不幸や貧困を象徴する存在として描かれています。
福島県の昔話では、その先をユーモラスに語られています。
《 あらすじ 》
昔、とても貧しい家がありました。
「何でうちはこんなに貧しいのかなあ。そうだ。宮司(ぐうじ)さんに頼(たの)んでお祓(はら)いをしてもらおう」
じいさまとばあさまは相談すると、村中の人と宮司さんを呼びました。

宮司さんのお祓いがすむと、村の人たちは、
「酒持ってこい。魚も持ってこい」


と日が暮れるまで飲めや歌えのドンチャン騒(さわ)ぎをしました。
夜になって、村人たちはみんな帰っていきました。
ところが、宮司さんのような白い着物を着た人たちがまだ外にいます。
じいさまは、
(頼んだ宮司さんはとうに帰ってもらったはずなのに、あれは誰だ)
不思議に思って外に出てみました。
「おい、お前たちは誰だ」
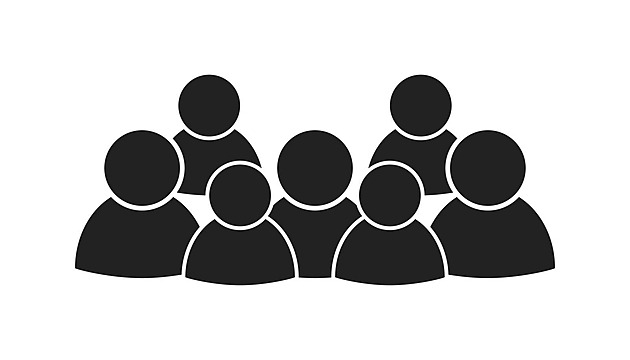
するとその中の一人が、
「おれは、お前たちにくっついている貧乏神だ」
と言いました。
「それじゃ、あっちは誰だ」
と聞きますと
「今日は、生まれてからこれまで、見たことがないほど、歌や踊りで賑(にぎ)やかやっているから、一人で見ているのがもったいなくて、あちこちの貧乏神に集まってもらったんだ」
と言うので、じいさまは驚きました。
「そんな、たくさんの貧乏神にいてもらっては困るから、すぐに帰ってもらいたい」
と、じいさま言いますと、

「ああ。貧乏神はつく人がっちゃんと決まっているから、みんなすぐに自分のところへ帰っていくよ」と言って、み—んな消えてしまいました。
その後、じいさまとばあさまのところへ酒屋(さかや)仕出屋(しだしや)がその日の酒やごちそうのお金を取りにきました。
けれど村人たちからもらったご祝儀(しゅうぎ)では、とても足りません。
じいさまとばあさまは、また相談しました。
「しかたがないねえ、どうやっても払えないから、夜逃げでもするか」
夜中に、そっと夜逃げの支度(したく)をしていると、縁の下で、トントントントンと音がします。

じいさまとばあさまは不思議に思って縁の下をのぞいてみると、さっきの貧乏神が一生見懸命わらをたたいていました。
「何だ。お前は。どうして人の家の縁の下でわらをたたいているんだ」
と聞くと、貧乏神は答えました。
「おれは、お前たちについている貧乏神だ。お前たちが夜逃げをするというから、もしその後で、この家に一生懸命働く人が来れば、とてもここにはおれん。だからおれはどこまでも、お前たちについていくために、わらじを作っているんだよ」
それを聞いたじいさまとばあさまは、またまた相談しました。
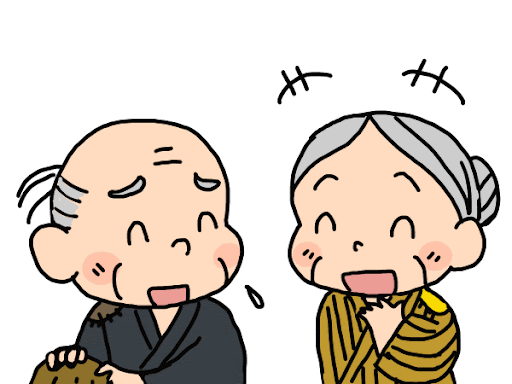
「これではどこに行ったって、この貧乏神がついてくる。働きさえすれば貧乏神は出て行くって言ってるんだから、夜逃げは止(や)めて、ここで働くことにするか」
それからというもの、じいさまとばあさまは朝早く起きて働き、自分の家の仕事がない時には、よその家の分まで手伝うって、働くようになりました。
そうして、借金もなくなって裕福になりましたから、貧乏神もどこかに行ってしまったそうです。
《 わたしの感想 》
貧乏神が家に住みついて困った主人公。
人間には人間の持つている適応力、逆境に立ち向かう精神力があります。
昔話の発想は、人それぞれの解釈によって違ってくるものだと思います。

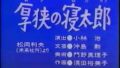
コメント